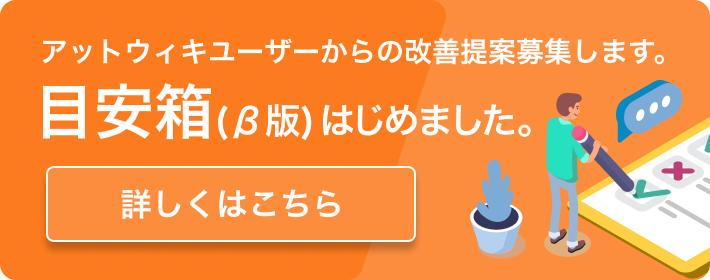「15-399」(2008/02/18 (月) 03:05:52) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
399 名前:翼よごらん[sage] 投稿日:2007/05/13(日) 22:51:04 ID:sn8Zj+DJ
日が傾くと共に、春の穏やかな日差しが徐々に黄昏の色に染まっていく。
「そろそろ今日は上がろうか」
父の声と共に家族皆が家の中に入ったあとも、少女は家の近くにある一本の大木の根元で、東の空に向かって祈りを捧げていた。
もちろん、宗教的な儀式ではない。祖母が教えてくれた、一種のおまじないのようなものである。
「お婆様、どうして東の空に向かって祈るの。東は怖いエルフが住んでいる土地なのでしょう」
この行為について疑問に思い、口にしてみたことがある。すると祖母は笑って答えてくれたものだ。
「昔ね、わたしの大切な人が東で姿を消してしまったの」
「死んじゃったの?」
「死んではいないわ。でも、ずっと遠くへ行ってしまったのね」
「大切な人なのに?」
「そうよ。その人も、わたし……いえ、わたしたちのことを大切に思っていてくれた」
「そんなのおかしいわ。それなのにどうして遠くへ行ってしまったの」
「そうね。その人はとても立派な人だったから。だからこそ、わたしたちの元にはいられなかったのよ」
「よく分からない」
「そうかもしれないわね。でも、わたしたちはお互いのことをとても大切に思っていたの。
だからこそ、わたしたちも彼を止めなかったし、彼も私たちを置いて帰ることができたのね」
結局、祖母の理屈を理解することは出来ていない。。
ただ、東の空に向かってお祈りをするのには、そういう経緯があるのだということは理解できた。
だから、彼女は今日も祈る。東の空に向かって、祖母の大切な人を想いながら、形にならない漠然とした祈りを捧げる。
「その人はとても強い人だったからね。きっと、わたしたちを見守ってくださるわ」
祖母は、そんな風に言っていた。
いつもは祖母と共に捧げる祈りだが、今日は一人きりだ。
祖母は三日前ほどに何かの便りを受け取り、以来魂が抜けたように呆けてしまっている。
今日は、祖母の回復を願って、いつもよりは具体的な祈りを捧げるつもりだった。
燃えるような夕日の色を背負いながら、もう夜に沈み始めている東の空に向かって手を組む。
400 名前:名無しさん@ピンキー[sage] 投稿日:2007/05/13(日) 22:52:30 ID:sn8Zj+DJ
ふと、何か聞きなれない音がした。顔を上げて、眉をひそめる。
何か、東の空から光るものが近づいてくる。最初は星に紛れてしまうような小さな光だったそれは、
じょじょに大きさと力強さを増していき、最後には目を開けていられないほどにまぶしい光になった。
そして、それはゆっくりと空から降りてきた。激しい音と風を巻き起こしながら、まるで鉄の竜のように。
夕日を浴びて鈍く光っているのは、明らかに鋼鉄で出来ていると思しき、どこか疲れたような感じのする体である。
竜ではない。その翼は真っ直ぐで、こんなものが今飛んでいたなどとはとても信じられなかった。
だが、それは事実飛んでいたのだ。夕日の光を跳ね返し、もう日の光も届いていない、東の夜空から飛んできた。
今は西の方を向いている鋼の竜から、不意に誰かが降りてきた。見慣れぬ服に身を包んだ、一人の老人である。
その老人は懐かしそうに周囲を見回してから、ふとこちらに気付いて声をかけてきた。
「やあ小さなお嬢さん。驚かせてしまったすまんね」
そう言ったあと、不意に何かに驚いたように目を瞬いた。
「これは驚いた。お嬢さん、あんた、俺の知り合いにそっくりだよ」
どう返していいか困惑するこちらのことなど気にもせず、老人は躊躇いながら質問してくる。
「ところでお嬢さん、あんたに聞きたいんだが、この名前に聞き覚えはないか。多分、結構有名な貴族なんだがね」
老人が口にしたのは、この国でも相当有名な貴族の名前であった。
黒髪の少女が頷くと、老人は興奮したように目を光らせて、さらに問いかけてくる。
「そうか、知っているか。それで、その領地はどっちの方向にある」
嘘をつく必要も感じなかったので、黒髪の少女は西の方角を指差した。
老人は暮れ行く空を見つめて、じっと目を細めた。その黒い瞳が、潤んだように煌いた。
老人は鋼の竜に近づき、何かが刻まれた左手で、その翼を愛しげに撫でた。
「翼よ見ろ、あれが俺達の目指していた空だ。おお、今すぐに会いに行くぞ、飛んでいくとも」
老人は元気に呟き、こちらに一つお礼を言って、また鋼鉄の竜に飛び乗った。
再び凄まじい音と風を巻き起こしながら、鋼鉄の竜が重々しく空に舞い上がる。
少しずつ小さくなりながら西の空に飛んでいくその影を見送っていたとき、家の扉が開いて誰かがこちらに走ってきた。
祖母だった。今朝、魂が抜けたような状態で椅子に据わっていた祖母が、何かに驚いた様子でこちらに駆けて来る。
手には、あの便りが握られていた。
「ああ、今、ひょっとして」
多分、祖母が聞いているのは先程の老人のことだろうと思った。だから、西の空に指先を向けた。
祖母はその方向を見て、遠ざかる影を見つけて息を呑んだ。そして、あの便りを握り締めて絞り出すように呟いた。
「ああ、あなたは約束通り帰ってきてくださった。でも、ほんの少しだけ遅かった。あと、ほんの少しだけでも、早く来てくだされば」
肩を震わせて涙を流す祖母の背中越しに、黒髪の少女は西の空を見つめた。
もう日が完全に沈みかけて、夕暮れから宵闇へと移り変わろうとしている、西の空。
東の夜空から飛んできた男が、今また、西の夜空へと消えていく。
少女と祖母は、完全に見えなくなってしまうまで、そこに立ち尽くしたまま鋼鉄の竜の影を見守っていた。
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: