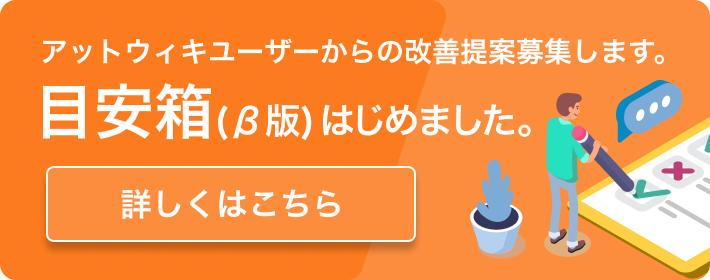「18-46」(2008/02/18 (月) 03:08:52) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
[[前の回>X00-05]] [[一覧に戻る>Soft-M]] [[次の回>X00-07]]
**ゼロの飼い犬9 月夜の晩に Soft-M [#r695ee8e]
■1
「……眠れねえ」
毛布を体の上からどかすと、身を起こしてベッドに腰掛ける。
色々あって体には疲れが溜まってるのに、目が冴えてしまって眠れる気がしない。
そういえば、数日前にもこんなことあったっけ。タバサと一緒に『月の涙』を
探しにいった夜だ。隣のベッドでギーシュが幸せそうに寝息を立ててるのも同じ。
違うのは、今日の宿はシエスタの実家だという点。宝探しの締めくくりとして
俺たちはシエスタの故郷であるタルブの村までやってきて、
シエスタの家に泊めてもらうことになったのだということ。
そしてもうひとつ。今度は”宝”が見つかったのだという点。
眠れないのはそのせいだ。色んな思いが胸の中にあって、興奮している。
思い出したら、余計に目が覚めてしまった。
俺はひとつ溜息をつくと、ベッドから降りてパーカーを着込んだ。
「どっか行くんかね、相棒」
目ざとく声をかけてきたデルフに、口の前に人差し指を立てて見せる。
「散歩だよ」と小声で言うと、デルフを部屋に置いたまま部屋を出た。
シエスタの実家から外に出て、森の木々のざわめきと虫の音しか聞こえない村道を歩く。
特に目的地を決めていたわけじゃないのだが、自然と足はある場所に向かっていた。
村近くの平原の片隅にある寺院。今日の昼間にシエスタに案内された、『竜の羽衣』が
安置されている場所だ。
寺院の中に入ると、『竜の羽衣』――いや、ゼロ戦に触れる。
この世界では明らかに異質な存在である、大日本帝国海軍の艦上戦闘機。
俺と同じく、地球の日本からこの世界に迷い込んだものであり、
そして俺以外にもこの世界に来てしまった人がいたのだということを証明するもの。
『固定化』とやらの魔法がかけてあるらしく、使用された当時のままの質感を
保っているのだろうその装甲を撫でる。レプリカでもなく、こんな綺麗な状態で
保存されているゼロ戦は地球にだって無いだろう。そう考えるとなんか不思議だ。
このゼロ戦を発見してしまったから。だから俺は胸がいっぱいになってしまって、
興奮しっぱなしになっている。それは、懐かしいとか故郷との繋がりを見つけたという
嬉しさだけじゃなくて……不安もある。
少なくとも、このゼロ戦と共にこの世界にやってきたシエスタのひいおじいさん、
海軍少尉佐々木武雄は地球へは帰れなかったのだから。
帰れなかったのか、帰らなかったのか。たぶん、両方だろう。
最初は当然帰るつもりで、でも方法が見つからず帰れなかったのだろう。
そのうち、この村に住むようになり、ここで働くようになり、奥さんをもらって。
シエスタの祖父か祖母にあたる子供もつくって……帰らないことを決めた。
でもこのゼロ戦を見るたびに思い出したはずだ。地球に想いを馳せたはずだ。
太平洋戦争はどうなったのか。日本はどうなったのか。家族や戦友はどうなったのか。
考えて、悩んで、でも知り得なくて、こちらの世界にも家族や生活ができて……。
ふう、と大きく溜息をつく。それって、もしかしたらこの後俺にも
繰り返されるかもしれないことなんだ。だから、こんなに不安になる。
「サイトさん?」
不意に寺院の外から声をかけられた。振り向くと、ゆったりした寝間着姿の影。
■2
「シエスタ」
「あの、驚かせちゃってすみません。誰かが家を出ていく音が聞こえて気になったから。
どうしたんですか? こんな夜中に」
「いや、別に何か意味があったわけじゃないんだけど、眠れなくて」
寺院から外に出る。月の光に照らされて、艶やかな黒髪が輝いていた。
シエスタは実家に置いてあったらしい、薄手の寝間着に上着を羽織った姿だった。
学院でシエスタの部屋に泊まった時の格好に似ていて、思わずどきっとしてしまう。
「眠れなかったんですか? わたしもです」
「シエスタも?」
「はい。なんだか色々考えちゃって……。
夕方にサイトさんにあんなこと言ってしまった後だったから」
シエスタは気まずそうに視線を逸らして俯いた。その姿を見て申し訳ない気持ちになる。
彼女はこの村で一緒に住もうとまで言ってくれたのに、俺はそれを断ったんだから。
「シエスタ、それは」
「いいんです。一生に関わることですもの。いきなり言い出した私がいけないんです」
言葉を遮られてしまった。そのまま、二人でどことも無しに歩いていく。
やがて、夕方にシエスタと一緒に話をした、平原が見渡せる丘まで到着した。
遙か遠くの山々まで見えるその場所は、夜でも十分すぎるほどの絶景だ。
「やっぱり星がもの凄く一杯見えるな」
日本で言う満天の星空なんて言葉が馬鹿らしく思えるほど、無数に星が輝く夜空。
見上げると、そのまま吸い込まれてしまいそうな錯覚まで感じる。
「サイトさんの故郷では違うんですか?」
「ああ、夜でも街の明かりが消えないから、星はあんまり見えないんだ」
「そんな。星の光が消えちゃうほどの明かりなんて、つけられるわけないじゃないですか」
冗談だと思ったのか、シエスタは小さく笑う。
たぶん、夜なのに昼間みたいに明るくなっているのを想像したんだろう。
俺も苦笑して返す。そんな冗談みたいなことが実際あるんだよな、地球では。
ある意味そっちの方がよっぽど魔法みたいだ。
「でも、夜でもそんなに明るいなら、暗くて迷ったりすることはありませんよね」
何かを思い出したのか、シエスタは視線を遠くへ向ける。それから少しして。
「あの……わたしの、つまんない昔話聞いていただけますか?」
シエスタは草地の上に座り込んで、ぽつりとそう言った。
「どんな話?」
言いながら隣に座る。シエスタは話し始めた。
「いつだったかな。たぶん、まだ10歳にもなってないころです。
わたし、あそこに見える森……。あの森にイチゴを採りに行って、迷ってしまったんです」
シエスタはこの丘から見える、村の側から広がっている深い森を指して言った。
「日が落ちるのも早くなっていた時期で、どんどん辺りは暗くなっていって。
そのうち、右も左もわからないくらいになってしまいました。
お父さんやお母さんの名前を呼んでも返事が無くて。
疲れて、転んだり木や草に擦ったりして傷もいっぱいできて、もの凄く怖かった。
しまいにオオカミの遠吠えなんかまで聞こえてきて……」
シエスタは淡々としゃべり続ける。当時のシエスタの不安まで伝わってくるみたいだ。
「やがて歩く気力も助けを呼ぶ気力も無くなってしまって、木の陰に座り込んで
泣き出してしまったんです。その時思ったのが……」
シエスタは目を閉じて空を仰いだ。
■3
「空が飛べたらいいのに、って。
その時のわたしでも、貴族という偉い方は魔法を使えるってことくらい知ってました。
それでも、ただ漠然と羨ましいなぁなんて思ってただけだったんですけど。
森で迷って木陰で震えているわたしは、もしわたしにも魔法が使えたら、
空を飛んであっというまにお家に帰れるのにって思って、悲しくなりました。
そう思ったら、自分がどれだけ弱くて何もできない存在なのかっていう自覚が
どっと襲いかかってきて、ただ怖くて不安なだけじゃない、嫌な気持ちになったんです」
シエスタは大きく息をついた。胸の奥に溜め込んでいたものを吐き出すように。
「その経験からも来てるのかもしれませんね。わたしが空を飛んでみたいって強く思うのは。
もちろん、一番大きいのは『竜の羽衣』の話を聞いてたからだと思いますけど」
今の話でシエスタは”空を飛んでみたい”って気持ちになったことを強調したけど、
たぶんそれは正確じゃない。
それだけじゃなくて……その時初めて、シエスタは貴族――魔法使いに対する
羨望とか劣等感とか、あるいは畏怖を感じたんだ。
そしてその感情は、この世界の平民が遅かれ早かれ感じることになり、
平民が貴族に付き従うという社会制度をつくる下地のひとつとなるものなんだと思う。
この世界で貴族が平民より上の地位に立っているのは、地球での階級制度とは意味が違う。
貴族はただ権力があるだけじゃなくて、魔法が使えるから平民よりも上の立場にある。
魔法が使えるか否かという明確な差に加えて、それによって『平民は貴族に劣る』
という意識を生活の中で刷り込まれてしまうから、この社会システムがより堅固になる。
「わたし、魔法学院に奉公してますから、貴族の方の側にいる機会が多いです。
だから、いつのまにか当然だと思ってました。
平民は貴族の方よりも弱くて、劣っていて、命令をされても見下されても当たり前なんだって。
普段はそれを嫌だとか不満だとかも思わないようになっていました。でも……」
シエスタは顔を俺の方へ向けた。星空よりも深くて綺麗な、黒い瞳で見つめられる。
「やっぱり本心では悔しいとか、惨めだなっていう気持ちはあって。
平民だって貴族の方よりも弱いだけの存在なんかじゃないんだってことを示してくれる人が
現れないかななんてことを、心の底では考えてました。もちろん、ただの夢想だって知ってて。
『イーヴァルディの勇者』みたいなお話の中でしか有り得ないことだって、わかってたんですけど」
俺の顔を見ていたシエスタの表情が、不安そうに歪む。シエスタは俺の袖を掴んだ。
「だから……サイトさんが現れて、ミスタ・グラモンを負かしたって聞いたとき。
学院を襲った盗賊を捕まえたのは、本当はサイトさんの手柄なんだって聞いたとき。
わたし、夢みたいだって思ったんです。想像の、お話の中にしかいないはずの、
貴族の方を見返してやれる平民の人がいたなんて、本当に夢みたいで……」
シエスタは言葉をくぎるように続ける。
「夢じゃないですよね。サイトさんはここにいますよね。
でも、サイトさんがいつかは故郷に帰るんだって聞いたら、不安になって……
サイトさんの存在も、サイトさんがしてくれたことも、
少しの間だけの夢になってしまうんじゃないかって思って、怖くて……」
そこでシエスタは言葉に詰まった。
「ごめんなさい。こんな事言ったらサイトさん、故郷に帰りにくくなるってわかってるのに。
ただの自分勝手な泣き言だってわかってるのに。なのに……こんなこと言ってでも、
わたし、サイトさんに遠くへ行って欲しくないって思ってます。
我が侭ですよね。迷惑ですよね。でも、でも」
かけてやれる言葉が見あたらない。シエスタの気持ちが痛いほど伝わってくる。
シエスタは掴んでいた俺の袖を放して、俺の側に寄ろうとしてから、その体を自ら引き留めた。
そんな行為も、ただ俺を束縛するだけの我が侭になる思ったのだろう。
胸がぎゅうっと締め付けられる。今日の夕方、俺はシエスタに残酷なことを
言ってしまったのだということを、改めて理解する。
■4
「ごめん、シエスタ。俺はずっとここにいるとは言えない。けど」
けど、何だよ。結局の所、俺はこんなに想ってくれるシエスタを置いて
日本に帰るつもりなんじゃないか。シエスタが悲しむのを見たくないから、何か弁明して
納得してもらうつもりか? 悪者になりたくないのか? 自分の気持ちに虫酸が走る。
「……謝らなくていいです。わかってます」
シエスタは気持ちにある程度整理がついたのか、ふっきれたように笑いながらそう言った。
「サイトさんにずっと側にいて欲しいって思うのは事実ですけど、
そのために好きになったわけじゃありません。サイトさんがいつかは故郷へ帰ってしまうんだと
しても、それでもわたしの気持ちは変わりません。もちろん、もし帰る方法が見つからなかったら、
その時サイトさんの居場所になるのはわたしの隣であって欲しいですけど」
どきんと心臓が高鳴るような直球勝負の言葉をかけられて、頬が熱くなる。
「だって、サイトさんは今ここにいるんですから。夢なんかじゃないんですから。
だから、それが一番大事なんです。ごめんなさい、泣き言を聞かせてしまって」
シエスタはにっこり笑った。この世界に来てから何度も助けられた、魅力的な笑顔。
今言ったのが本気なのかどうかはわからない。けど、シエスタが俺の気持ちと、
自分の気持ちを眠れなくなるくらい考えて紡ぎ出してくれた言葉。
自分の心の弱い部分もさらけ出してくれた言葉。
そんな言葉を俺に向けてくれたことが、凄く嬉しかった。
「ありがとう、シエスタ」
「お礼も言わなくていいんですよ。わたしはサイトさんを困らせる我が侭を言っただけなんですから」
悪戯っぽく言うシエスタは、少なくとも表面上はいつもの調子に戻ったみたいだ。安心した。
「……ところでさっきの昔話だけど、道に迷ったシエスタはどうやって助かったんだ?」
「木陰で泣き疲れて眠ってしまって、次の日の明け方に探しに来たお父さんに起こされたんです。
実はそんなに深いところまでは行ってなかったみたいで。つまんない話だって言ったでしょう?」
俺とシエスタは顔を見合わせて笑った。
少しして、そろそろ家に戻ろうかといった雰囲気になった。
俺はちょっとしたことを思いついて、立ち上がったシエスタに声をかける。
「シエスタ、ここら辺で一番高い木ってどれかな?」
シエスタは不思議そうな顔をした後、首をめぐらせてここからそう離れてはいない、
森の入り口に立っている巨木を指した。
「たぶん、あの木だと思いますけど」
なるほど、ひときわ高い。しかも丁度良く高台にある森に立っている。
「ちょっとついてきて」
シエスタを手招きして、その木の下まで移動する。下から枝の様子を見上げると、
これならいけそうだと判断できた。
「シエスタ、ちょっと俺におぶさって」
背中を見せて屈み込む。
「え、どうしてですか?」
いいから、と強い調子で言うと、シエスタは遠慮がちに俺の背中に乗った。
さすがにタバサよりは重いけど、子供の時に誰かにおんぶしてもらうのに慣れているのか、
なかなか上手い具合にしがみついてくれた。
パーカーのポケットから、『月の涙』の探索の時に作った石器を取り出して意識を込める。
ルーンが熱を持ったのを感じると、俺は再び上を見上げ、木の枝を駆け上がった。
「わっ、わわわ、わあっ!!」
シエスタが慌てふためいた声を上げる。枝や葉に引っかからないよう気をつけながら
すいすいと登っていき、あっという間に登頂近くまでたどり着いた。
丈夫で足をかけやすそうな枝の隣で止まると、シエスタは意図を察したのかそこへ降りる。
やはり子供の頃は木登りなんかも頻繁にしたのか、危なげない足取りだった。
■5
「代わりと言っちゃ何だけど、まだ『竜の羽衣』は飛ばせないから」
俺も安全な足場に立つ。シエスタは呆然とした顔で、そこから見えるものに心を奪われていた。
ここら辺で一番高い木のてっぺんからは、シエスタの生まれ育ったタルブの村も、
その周辺の森も平原も、もっと遠くの山々も川も道も一望できた。
高さでいったら、山の上やタバサの風竜の上よりもずっと低い。
けれど、木の上から眺める景色というのは一味違う。俺も子供の頃経験がある。
「凄い……これ、いつも見上げてたあの木なんですよね」
シエスタが感極まった声を上げる。喜んで貰えたみたいだ。
「こんな風に見えるんだ。わたしの家があんなに小さい。すごいなぁ……」
シエスタは夢中になって景色を眺めている。切り揃えられた黒髪が風にたなびく。
その嬉しそうな横顔を見ていると、こっちも楽しくなってくる。
「星もお月様も、なんだか近くなったような気がします。手が届きそう」
「『竜の羽衣』……飛行機があればメイジじゃなくても、ここよりずっと高く飛べる。
風竜よりも、空に浮かんでるアルビオン大陸よりも。
魔法が無い俺の故郷で、それだけのことができてるんだ」
それどころか、月まで行けてしまう。まるで魔法のようで、魔法じゃない。
「だから、なんていうか」
魔法が使えなくたって、魔法より凄いことだってできる。
魔法の有無にかかわらず、もっとずっと色んなことができる。そこまで言ったら
さすがに説教臭いだろうか。そう思って言葉に詰まると、シエスタは俺の方へ振り向いて、
「わたし、今すごく嬉しいです。ありがとうございます!」
この景色にも、星空にも二つの月にも負けないくらいの笑顔を見せてくれた。
それで十分だった。
「あの山を越えたら、魔法学院ですね」
ひとりきり眺めを堪能した後、シエスタは遠い山脈を指して言った。そうなのか。
「サイトさん、明日になったら帰ってしまうんですよね」
寂しそうに言うシエスタ。明日になったらギーシュのコネでドラゴンを借りて、
ゼロ戦を魔法学院まで運ぶことになっている。シエスタはここに残るという話だったけど。
「ああ」
答えると、シエスタはくすっと笑った。
「どうしたの?」
「いいえ、サイトさん、わたしが『帰る』って言葉を使ったら、自然に答えましたから。
サイトさんには故郷以外にも、帰る場所がもうあるんだなって」
そう言うシエスタの言葉に、俺ははっとした。
「サイトさんが『帰る』ところって、あのヴェストリ広場に作ったテントじゃありませんよね。
ミス・ヴァリエールのところですよね」
「それは……」
否定しようと思ったけど、否定できない。俺は魔法学院のことを思い出して、
最初にイメージしたのはルイズの部屋だった。もちろん、ルイズとセットで。
俺は無意識のうちに、そこに『帰る』つもりでいた。今はクビにされてるはずなのに。
「やっぱり、ミス・ヴァリエールが羨ましいです。
貴族だからっていうんじゃなくて、サイトさんと一緒にいられるから」
ルイズ。俺のご主人様。考えたらこの宝探しの間も、俺はいずれはルイズの所に
戻るつもりだったんじゃないか? 宝探しには『出かけている』つもりだったんじゃないか?
俺自身も気付いていなかったことを、シエスタが見抜いていた。
「サイトさん、今はミス・ヴァリエールと喧嘩なさってますよね。ミス・ヴァリエールのこと、
我が侭でわからずやな方だと思ってるんじゃありませんか?」
「まぁ、そりゃね」
頬を掻きながら答える。学院に戻って、どんな顔でルイズに会えばいいのかわからない。
■6
「いいことを教えて差し上げます」
シエスタは内緒話をするいたずらっ子みたいな顔を、少し俺の方へ寄せた。
「ミス・ヴァリエールは、サイトさんが来てからすごく変わったんですよ」
そうなのかな。確かに俺に対する待遇は良くなってたけど、
外から見て明らかなほど変わっているようには思えない。
「疑ってますか? 確かに、サイトさんには『サイトさんが来る前のミス・ヴァリエール』
のことは知りようがありませんからね」
その通りだ。当たり前だけど、シエスタは俺より先にルイズを見知っていたわけだ。
「ミス・ヴァリエールはお気が強くて、他人に何でもずけずけ言うように
見えるかもしれませんけど……でも、サイトさんが来る前は違ったんです」
「ほんとに? あのルイズが?」
「ええ。ミス・ヴァリエールは学院の生徒の方の中でも特に高貴な身分ですから、
絶対に粗相が無いようにって顔と名前を覚えさせられました。
けれど、ミスはそれだけ高い身分の方なのに魔法が苦手でしたから。
だから孤立して、お昼休みも放課後も、ほとんど独りだったんです」
言われて、なんとなく頷けてしまった。そういえばルイズって友達らしい友達が
まるでいない気がする。休み時間も昼休みも放課後も、俺にばっかり構ってくる。
「独りで、思い詰めた顔で本や教科書を読んでいて。
お勉強は頑張っているみたいなのに、やっぱり魔法はできないみたいで。
他の生徒の方がミスの悪口や陰口を言っているのをよく耳にしました」
それは俺も聞いた。でも、ルイズへの悪口はただのからかいじゃない。
ただ成績が悪いだけならともかく、ルイズは家柄が最高級なんだから。
そのプレッシャーと現実との差にルイズはピリピリして、周りと壁を作って、
孤立してしまったんだろう。
「それで、今年の新学期になってサイトさんがミス・ヴァリエールに召還されて。
それからです。ミス・ヴァリエールが今みたいになったのは。
ミスが怒鳴ったり暴れたりするなんて、それまではほとんど見なかったんですよ。驚きました」
今まで鬱憤が溜まっていたところに、明らかに目下な存在ができたからじゃないのか。
そう思うのは簡単だけど、きっとそれだけじゃない。
なんというか……俺は、ルイズにとっての”友達”でもあったんじゃないのかな。
一般的な意味での友人とは違うけど、遠慮なく物を言える相手。喧嘩できる相手。
「それって凄い事です。公爵家のミスと本気で喧嘩できる方なんて、貴族の方でも
滅多にいません。ずっと張り詰めてて、お友達もいなくて、独りでいたミスを
サイトさんは変えていたんです。きっと、サイトさんにしかできなかった事です」
不意に、数日前の『月の涙』の谷での、タバサの言葉が蘇った。タバサは、ルイズが本気で
俺のことを犬同然だとは思っていないと言ってくれた。今のシエスタもそう。
俺とルイズが仲違いしていることについて、外からの視点で慰めと助言をしてくれている。
俺はルイズに裏切られたと思って、一方的にルイズを悪者だと思ってたけど……
俺の方も、ルイズの本心を考えていなかった? 周りが見えていなかった?
「わたし、サイトさんはわたしが夢想していた『貴族を見返してくれる人』みたいだって
言いましたけど、本物のサイトさんはわたしの夢想よりもっと凄い人なんですよ。
サイトさんはただの平民の味方じゃありません。平民とか貴族とか、そういう立場とか身分に
関係なく物事を考えられる人です。だからミス・ヴァリエールを変えることができたんです」
かいかぶりすぎだよ。それができるのは、俺が身分差別の無い別の世界から来たから、
貴族だ平民だってのにピンと来ないだけ。空気が読めないからって言ってもいい。
でも、そのおかげでルイズが変われたっていうのなら、俺が日本から召還されたのは、
やっぱり何か意味があってのことなのかもしれない。
■7
「だから……わたし、メイジじゃありませんから、使い魔と主人の関係がどういうものなのかは
よくわかりません。けど、やっぱりミス・ヴァリエールには、サイトさんが必要なんだと思います」
シエスタの髪が風にふわりと流され、月の光を反射してきらきらと輝いた。
「あはは、わたし、何言ってるんでしょうね。昼間はサイトさんにこのままこの村で
暮らしてくださいなんて言ったのに。なんか矛盾してますね」
ううん、矛盾なんかしてない。シエスタは俺のことを思ってくれてるから。
だから言ってくれたんだろ。わかる。痛いほどわかる。
シエスタは自分の気持ちを押し殺しても、俺のために。
俺がルイズと仲直りしやすいように、言葉を連ねてくれた。
それが嬉しくて、同時に申し訳なくて。胸が締め付けられてたまらなくなる。
この女の子の気持ちに、応えてあげたくて仕方なくなる。
「シエスタ」
もう一度手製のナイフを握ると、シエスタを抱きかかえた。今度は背負うのではなく、
いわゆるお姫様抱っこ。ルーンの力を発動させると、シエスタの体は羽毛みたいに軽くなった。
トントンと枝から枝へ飛び降り、無事に地面へ降り立つ。
シエスタの体を降ろそうと思ったら、パーカーの前をきゅっと掴まれた。
「もう……本当に、夢かおとぎ話みたいじゃないですか、こんなの……」
薄暗い月明かりの下でも、シエスタの瞳が潤んでいるのがわかった。
その色っぽくも幻想的な雰囲気に、思わず心臓が高鳴る。
「じゃあ、せっかくだしこのまま家まで運びましょうか?」
芝居がかった口調で言うと、シエスタはふにゃっと顔を崩して俺の手の中から降りた。
「遠慮しておきます。だって、ここにいるサイトさんは夢でもおとぎ話でもないんですから」
シエスタは草原に駆け出すと、くるっと振り返って俺に笑いかけた。
シエスタの家に帰ってきた。物音を立てないように廊下を歩き、シエスタの部屋の前で止まる。
ここで俺はおやすみを言ってあてがわれた部屋に戻るべきなんだろうけど、
足に根が張ってしまったようにそれができない。シエスタとこのまま別れたくない。
シエスタは自分の部屋の戸を開けると、遠慮がちに俺の服の袖を摘んで引っ張った。
それだけでわかった。シエスタの方も同じ気分なんだ。
誘われるままに入った部屋は、物がいっぱいに積み上げてあった。
シエスタが学院に奉公に出てしまったので、物置代わりにされていたのだろう。
ベッドとその周りだけは片づいていた。シエスタが整理したのかも。
「あの……サイトさん、明日になったら学院に戻ってしまいますよね。
そうしたら、しばらく会えませんよね」
ベッドの隣まで来て、もじもじと肩を揺らしながらシエスタは口を開いた。
「その……だから、あの……」
自分の寝間着の胸をぎゅっと掴むシエスタ。薄暗い部屋の中でも、
その顔が真っ赤になってるのが想像できる。
そして、ここでシエスタが何をしてほしいのかわからないほど俺は馬鹿じゃない。
「シエスタ」
呼びかけると、シエスタは意を決したように俺の方へ顎を上げて、目を瞑った。
少し力が入って引き結ばれてしまっているその唇に、俺の方から唇を合わせた。
シエスタは一瞬身を震わせた後、体の力を抜いた。固くなっていた唇がとろけそうなほどに
柔らかくなる。シエスタとキスをするのは、確かこれで三回目。
「んっ…ふ、ぁ」
唇を離すと、シエスタは俺の首に手を回してきた。そのまま引っ張られそうになったところで、
シエスタは身を横に倒した。シエスタのベッドの上に、二人で倒れ込む。
■8
「サイトさん……サイトさん、サイトさん……!」
俺の名前を呼びながら、今度はシエスタの方から何度も唇を重ねてきた。
今まで押し殺していたものを解きはなったみたいな、貪るようなキス。
ベッドに仰向けになった俺の体にのし掛かるような格好になって、
シエスタはそこにいる俺の感触を確かめるように、力を込めて抱きついてくる。
温かくて、柔らかくて、包み込まれてしまうようなシエスタの体。
抱きしめ返すと、シエスタは喉の奥から幸せそうな吐息を漏らした。
「っは……はぁ……やっぱり、駄目ですサイトさん……」
「え?」
シエスタはキスを中断すると、耳元へ口を寄せて甘えるように言ってきた。
「こんなの……こんなに甘くて、嬉しくて、気持ちいいこと教えて。
わたし、あの夜からサイトさんのことばっかり考えてるんです。
またキスして欲しいって。抱きしめて欲しいって。そんなことばっかり」
首筋に押しつけられた唇が上がってきて、耳たぶに触れた。
「こんなに素敵なこと知ったら、大好きな人に触れるのがこんなに幸せだって教えられたら、
どんなことしてても離したくなくなっちゃいます」
シエスタは俺自身を味わおうとするみたいに、そしてささやかな抗議をするみたいに、
耳たぶを甘く噛んだ。ぞくぞくする感触に背筋が震える。
シエスタの言葉に、心の奥が痛む。俺もそうだ。つい先日シエスタと一緒にお風呂に入って、
その後一緒のベッドで眠ったとき。その時のシエスタの温かさを知ってしまって、
俺はシエスタを離したくないと思ってしまった。欲しいと思ってしまった。
シエスタの前で俺はいつか故郷に戻るとはっきり言ったのに、
それでも俺を待ってくれると言ってくれるシエスタの言葉を嬉しいと思ってしまった。
それはつまり……帰れなかったときの次善策として、
シエスタをキープしておこうなんて思ったってことじゃないか。
「シエスタ、俺はそんな立派な人間じゃない。だって」
「いいんです。関係ないです。だってわたしだって綺麗じゃないですから。
心に汚いところがいっぱいあって、それをサイトさんに見せまいとしてるんですから」
言葉とは裏腹に、その内側に汚いところがあるなんてとても思えない潤んだ瞳が俺を見る。
「……サイトさん。今ここで、わたしにお情けをくださいますか?」
シエスタは目を細め、何も知らない少女みたいな笑顔で、とんでもないことを聞いてきた。
「え、その、それは……!」
俺がしどろもどろになると、シエスタは小さく吹き出した。
「わかってます。今はまだ駄目ですよね。それにここでそんなことになったら、
さすがに家族とかミス・ツェルプストーたちにばれてしまいます」
ほっとしたような、残念なような。
「でも、わたしだって不安なんですよ。わたしはただのメイドですから。
貴族の方に勝れるところなんてほとんどありませんから。
だから……はっきりした、証しみたいなものが欲しくなってしまうことだってあります」
「あ、証しって」
恥ずかしそうに言うシエスタに、俺はどう返していいのかわからなくなる。
「関係ないって! 前にも言ったろ、シエスタにはどれだけ感謝してもしたりないくらいだって」
「それでも不安なんです」
シエスタはずいっと俺の方へ体を寄せた。
何だかその顔は強ばっていて、勢いに身を任せてるような印象さえ見受けられる。
■9
「あの……、その、だだ、だからですね」
口元に指を当て、所在なさげに視線を彷徨わせながら言うシエスタ。
そのまま深呼吸をすると、意を決したように口を開き、でも小声で、
「…………ご奉仕、させていただきたいんです」
そう言ってきた。
……はい?
脳が一瞬思考停止する。
「え、それ、どういう」
「わかってるんじゃありませんか? サイトさん、意地悪です」
シエスタは涙目になって俯き、俺を上目遣いに見つめながら言ってきた。うぅ、可愛い。
いや、見とれてる場合じゃない。少し頭が飛んじゃったせいで素で聞き返しちゃったけど、
つまりその、ごごご奉仕って、えっちぃ意味でってこと?
考えがまとまる前に下半身に何かが触れ、ぞくりと刺激が走った。
「シ、シエスタ!?」
前にも同じ感触を味わったことがある。シエスタが俺のズボンの前に手を這わせたのだ。
「不安なんです。だってわたし、サイトさんに喜んで貰えるようなもの、
この身体しか持っていません。なのに、まだ愛してはいただけないから、だから……」
「そんなことない! シエスタは俺にもっと色んな事を」
シエスタの手から腰を引いて逃げながら、必死で言い返すと。
「わたしがしたいんですっ」
そう言い切られた。唖然としていると、シエスタは居直ったように俺の瞳を見返した。
「だっ、だから汚いって言ったじゃないですか。サイトさんに喜んで欲しいのは本当です。
サイトさんにわたしを好きになって欲しいのも本当です。
そのためにこんなことするのだって、汚いことだけど……それよりも、もっと汚くて」
シエスタは俺の胸に顔を埋め、頬を押しつける。
「私の部屋に泊まって貰ったあの日から、忘れられないんです。
サイトさんの声も、吐息も、匂いも、体の感触も。ずっと消えなくて、頭から離れなくて」
シエスタはすうっと息を吸い込んだ。まるで匂いでも確かめてるように。
「はしたないってわかってるのに。いやらしくて汚いのに。
なのに、サイトさんとまた同じベッドで眠りたいって、毎晩考えていたんです。
サイトさんの方から求めて下さらないかななんて、ずっと考えてたんです」
ほとんど自虐に近い口調で、シエスタは一気に吐露した。
「……こんな、サイトさんの気持ちも考えてない汚い子なんて、
愛して頂けるわけないんです。だからお情けなんて望みません。
わたしに……奉仕させてください。わたしがサイトさんのためにいるっていうしるし……」
「シエスタ、ちょっと待って……!」
シエスタは俺の制止も聞かず、それこそ一緒に眠った晩を繰り返すかのように
ジーンズのホックに指をかけた。あの時と違うのはあっという間にそのホックが外され、
流れるようにチャックまで下ろされてしまったこと。おかしい。いくらなんでも手際が良すぎる。
「嫌ですか? でしたら逃げて下さい。こんな汚い子に触られるのが嫌なら、今すぐ」
陶然とした顔を向けてくるシエスタに、あの時と同じように問われる。
そう言われて、逃げられるわけがない。だって、嫌じゃないんだから。
こんな淫靡な表情で見つめられて、もう体は期待と興奮に支配されているんだから。
シエスタは俺の様子から全てを悟ったかのように、くすりと微笑んだ。
まるでその瞳に魅了の魔法がかかってるみたいに、心を鷲掴みにされ、動けなくなる。
■10
「……失礼します」
シエスタは俺の下着をするりと下げ、壊れ物を扱うような手つきで中の物を取り出した。
ひんやりとした部屋の中の空気に、ガチガチに硬直したものが晒される。
シエスタにそれを眼前で直視されてしまい、何か致命的な一線を越えてしまったような
罪悪感が襲いかかってきた。
「凄い……こんな、こんな立派なの……」
譫言みたいに、シエスタは口の中だけで何か言った。そして先端を手で包み込むと、
全体の形を確認するように指を根本まで撫で下ろす。
緩い刺激が腰から背中を駆け上がり、意識せずに手がベッドシーツを握りしめる。
「あぁ、これです。あの時と同じ。熱くて、固くて、大きくて」
シエスタの瞳が無くしてしまった宝物を探し出した子供のように輝き、
指が根本から再び先端まで滑る。また降りる。それを数往復。
以前はそれを繰り返されただけで、シエスタの手の中に果ててしまった行為の再現。
あの時より無理がない体勢だから? 前よりずっと快感が大きい。
「あの……サイトさん、びっくりしないでくださいね。わたし、今から」
手で俺のペニスを擦るのを止めないまま、シエスタは聞いてくる。
俺はといえば、ただ手を上下させているだけのシエスタの与えてくる快楽に
必死で耐えていることしかできない。
「今から……たぶん、すごくいやらしいことしますから」
「え?」
これ以上いやらしい事って。それが何なのか聞く前に、シエスタは行動に移った。
横髪を耳の後ろに流すと、シエスタはすぐ眼前にあった俺のペニスにさらに顔を近づけ、
そのまま……先端に口付けた。
「あっ……!」
驚きと刺激に、短い悲鳴と同時に腰が跳ねる。揺れたペニスが唇をなぞって離れた。
「あん……動かないでください。初めてだから、危ないかもしれませんよ」
シエスタは弟のイタズラを咎める姉みたいな声でそう言い、
ペニスの根本を両手で固定する。そして改めて、その唇が亀頭の先端に触れる。
ちゅ……と粘膜同士が触れ合う微かな音がいやに大きく耳に飛び込んだ。
「ふっ……ぁ、シエスタっ……!?」
俺の困惑の声が届いていないのか、無視されているのか。
ついさっき自分のキスを重ねたシエスタの熱くて柔らかい唇の感触が敏感な部分に広がる。
それだけでも頭の処理が追いつかないような未知の感覚だったのに、あろうことかその唇が
割り開かれ、さらに熱い舌が鈴口に触れた。
「ひぁっ!」
まるで女の子みたいな情けない悲鳴が漏れる。ぴちゃりという水音と共に、
びりびりと痺れるような快楽が弾ける。そのままシエスタは唇を大きく開いて
亀頭の上半分辺りを覆うと、ストローで物を飲むみたいに吸い付いてきた。
「…………ッッ!!」
声にならない声を喉から漏らし、反射的にシエスタの頭を掴んでしまう。
ほとんど無理矢理押し退けたも同然な状態でシエスタの顔を離すと、その唇とペニスの間に
銀色に輝く唾液の糸が引き、ぽたたっ、とシーツの上に雫が落ちた。
「す、すみませんっ! 痛かったですか!? ごめんなさい!」
シエスタは口元に垂れた涎も、掴まれて乱れた髪も気に止めず、
こちらが驚くくらい頬を蒼白にして俺に謝ってきた。
「いや、俺の方こそ。いきなり頭を掴んだりして」
「いいの、勝手な事したのはわたしですから。それで、痛かったんですか? お嫌でしたか?」
粗相をしてしまったことで飼い主に許しを請う飼い犬のような怯えた目を向けられた。
その視線と態度に、俺の心中の暗い部分がぞくりと刺激されたのを感じる。
■11
「いや、痛くはなくて、むしろ良すぎて驚いちゃったくらいなんだけど」
「そうなんですか? よかったぁ……」
シエスタは、今度は飼い主に誉められた子犬のように一転して瞳を輝かせ、
心底安堵したという風に相貌を崩した。そして、再び上体を俺の股座に戻す。
「あの、それじゃ、嫌ではないんですよね?」
その様子に、またも心の奥の部分が震えた。今度はその姿が、餌をお預けされている
飼い犬を連想させたからだ。何か、どこかでおかしい。ただ目の前の女の子が
熱心すぎる奉仕をしてくれているというだけじゃ済まないような気がする状況。
「じゃあ、続けさせていただきます」
その違和感の正体に気付く間もなく、シエスタは口を小さく開けて、
唇だけでペニスに噛み付くみたいに亀頭を挟んだ。
シエスタは首を横にすると、唇で竿を掃除でもするかのように唾液を撫でつけながら
根本まで顔を下ろした。俺の太股にぺたんとシエスタの頬が当たると、
今度はまた上がってくる。
歯を食いしばらないとまたみっともない声が出てしまうそうな刺激に震えていると、
亀頭のところまで登ってきたシエスタの口が、再びちゅるりと鈴口を吸った。
今度はシエスタの頭を掴んだりはしなかったけど、腰が跳ねるほど気持ちいい。
「ん、ぷはっ、はぁ…」
「ふぅ……はぁ、はぁ、はぁっ……」
シエスタはそこで顔を引き、唇を離すと、自分が今まで奉仕していたペニスを眺めた。
俺の方は、その様子をぼやけた視界で見ていることしかできない。
シエスタより俺の方が息が乱れているくらいだ。
「サイトさん、どうですか? わたし、よくわからないから、サイトさんの方から
どうしたら気持ちいいのか言って頂けると嬉しいんですけど」
冗談だろ。シエスタの与えてくる快楽に耐えるだけでいっぱいいっぱいだ。
これ以上どうしろなんて言えるわけがない。むしろ手加減して欲しいくらいだ。
「そ、それより、どうして急にこんなこと?」
また吸い付かれたりしたら我慢する余裕もなくシエスタの口にぶちまけてしまいそうなほど
高ぶっていたので、熱を冷ます時間を得る意味も兼ねて聞く。
「言いましたよね? あの夜のことが頭から離れなくて、
サイトさんがわたしで良くなってくれたことを思い出すだけでたまらなくなってしまって。
それで、もっと良くなってもらうにはどうしたらいいのか勉強して」
「べ、勉強ですか」
シエスタは口を離して俺の様子を見ている間も、俺のペニスを掴んだ指を
やわやわと動かしてゆるい刺激を与えてくる。まさか無意識にやっているんだろうか。
「あっ、もちろん、わたしサイトさん以外の殿方にこんなこと絶対しません。
その、同じ部屋の子に聞いたり、自分で想像したり……それだけです」
布団を持って行かれてしまった時といい、シエスタと同室の子って一体。
「それで、”これ”が男の人は凄く気持ちいいって聞いたから、ずっとして差し上げたくて。
してみたくて……。サイトさん、気持ちいいですか? ちゃんとできてますか?」
とろんとした目つきで、唾液に濡れたペニスをにちゃにちゃと扱きながら聞いてくる。
「……良い。凄く気持ちいい」
正直に答えると、シエスタは顔をほころばせて再び口を開いた。
「じゃあ、もっと良くなってくださいね」
今まで我慢していたような勢いでシエスタはペニスの先端に唇を当て、
そのまま……ずるりと奥まで飲み込んだ。
■12
驚愕するくらいの感覚だった。口腔を通り越して喉まで
入ってしまっているんじゃないかというほど、シエスタの顔が腰に近い。
それに、ペニスがシエスタの口の中の、固かったり柔らかかったり、
どこがどこなのか判断もつかない部分に満遍なく触れている。
それだけでも頭がオーバーヒートしてしまいそうな感触だったのに、
さらに想定外の刺激が襲いかかってくる。
ペニス全体が、熱くてぬるぬるしたものの中にひたされている。
俺の持っている『人間の口の中』というイメージからかけ離れた感覚。
その理由に一瞬迷った後に気付いた。唾液が大量に溜められているんだ。
「んんぅっ……!」
じゅるじゅるじゅるっ、と下品と言っていいような水音を立てて、
シエスタはくわえ込んだペニスを先の部分まで引き戻した。
溢れた唾液が根本の方まで落ち、更に袋の方まで垂れてくる感覚に背筋が震える。
亀頭だけをくわえた状態になったシエスタは、俺の顔を見て少し考える様子を見せた後、
あれだけペニスに塗りつけて口の中から零したのにほとんど水気が減ったようには
思えない口腔の中で、口をゆすぐみたいに唾液をぐちゅぐちゅと動かした。
「あ……あ、あっ…!!」
どんな刺激が与えられるのか、漠然とでも予想できていればいくらかは耐えられる。
けど、これは想像を遙かに超えた感覚だった。
敏感な亀頭だけが、熱い頬裏や舌に擦られる。それだけならまだしも、
ぬるぬるの唾液によって攪拌され、翻弄される。
俺の口元からも、だらしなく涎が零れた。自分のものと比較して、改めて理解する。
シエスタは普通の人より間違いなく唾液が多い。平均の倍じゃ済まないんじゃないか。
さっきまで薄々感じていた違和感のひとつの正体はこれだ。
頭を掴んで引き離してしまったときに、水音を立ててシーツに落ちるほど零れた唾液。
まるで餌を待つ犬を連想してしまうほどに濡れていた口元。普通より明らかに多かった。
それに、ただ唾液が多いだけじゃない。粘度も高い。
まるで男を悦ばせるためにあつらえられたみたいな口腔が、再びペニスを中ほどまで
飲み込む。舌が裏筋を中心に竿に絡みつき、吸い付かれながら引き上げられる。
気持ちいい。良すぎる。目の前に火花が散るような刺激。
シエスタは目をきゅっと閉じて、頬を真っ赤に染めながら俺のペニスにしゃぶりついている。
聞いたり自分で考えただけ、と言っていた。たぶんそれは間違いない。
シエスタの口奉仕には熟練しているとか技巧があるといった雰囲気は感じられない。
ただ、一心不乱にしゃぶりついて、ぐちゃぐちゃとねぶっているだけ。
それなのにこんな、意識が飛んでしまいそうなほど気持ちいいのはシエスタの才能だ。
口を大きく開いて俺のものをくわえ込んでいるのに、えずいたり苦しそうになったりという
ところが無い。鼻からの息継ぎだけで、ずっと行為を続けている。
それに、遠慮というものがない。最初は俺の反応を確かめるように少しずつ
舌や口の中を動かしていたけど、俺が”良さそう”な反応をする力の入れ方を覚えると、
次からは絶対にそれを下回らない。物足りないと感じるどころか
さらに強い攻めを試してきて、あっという間に苦痛となるギリギリまで追い立てられる。
そして、多少無茶をしても緩衝剤となり、それどころかさらに快感を加速させる
大量で、かつ粘性の高い唾液。俺の物を簡単に飲み込めてしまう口腔と合わせて、
ただくわえられているだけでもすぐに果ててしまいそうなのに。
これで技巧なんてものが備わったらどうなってしまうのか恐ろしい。
いや、既に恐ろしい状態になっている。
その上……、時々薄目を開いて俺の顔を見つめるシエスタの表情には、
つらいことをしているとか、屈辱的なことをしているとか、そういう色が全く見えない。
俺のことを気遣って、俺の喜ぶことをして。それが何よりの幸せなんですと言わんばかりの、
いつものシエスタそのままの目。俺と目が合うと、恥ずかしそうに目を閉じる。
■13
そんなシエスタの様子と、彼女が行っていることの乖離が混乱と背徳感を生むのと同時に、
俺の胸の中に暗い情動に火を灯す。この子は、シエスタは俺の物だ。
俺の為だけに存在する。
そんな許されるわけが無い、けれどもあまりに甘美な幻想が心の奥底に弾ける。
肉体だけじゃなく精神までがシエスタの与えてくる快楽に溺れていくうち、
次第にどこをどうされてるのかという感覚すら次第に失われて、
ただ快楽だけが腰から脳髄まで駆け上がってくる。シエスタの口の中で
俺のペニスは溶かされてしまったんじゃないか、なんて妄想すら浮かぶ。
ひょっとしたら、もうとっくに果ててしまっているのかもしれない。
だって、シエスタの口の中は粘性の高い唾液で満たされていて、射精してしまっても
ほとんど感覚は変わらないのではと思えたから。
だが、そんな想像も長くは続かなかった。感覚がイレギュラーすぎて体の方が
混乱していたとしか思えない、そうでなければ今まで保ったことが不思議なくらいの
射精感が腰の奥に膨らみ、じわじわと登ってくる。
「シエスタ、シエスタっ……!!」
思わず、先刻そうしたようにその形の良い頭を掴んでしまう。
止めてもらわないと、そう思った。思ったはずだった。なのに体がそれを無視した。
俺の両手は、シエスタの頭を抱え持つと……それを引き寄せたのだ。
「んぶっ…!?」
驚いて目を見開くシエスタ。急に口の中に入っている部分が増えたため、
その分の唾液が溢れて腹の方にまで跳ねた。やってしまってから、
自分がとんでもない暴虐を働いたことに気付き、すぐさま腰を引こうとすると。
シエスタは逃げようとする俺を捕まえるかのように、腰の後ろに両手を回した。
そして何もかも受け入れた表情で目を瞑り、口の中に溜まった唾液を集めて吸い上げ、
ごくりと飲み込んだ。
それが、抵抗しようもない引き金だった。ペニスをシエスタの舌や唇や頬の肉、
顎や歯までが扱き、唾液ごとペニスもその中身も吸い込まれてしまいそうな感覚に、
我慢するという発想すら生まれる余裕すら与えられず限界が打ち破られた。
俺が放出したというよりも、シエスタの吸い出されたというような射精だった。
体の内側にドロドロと渦巻いていた衝動と快感が、一気にそこに集まって爆発する。
そして――俺は、意識が焼き切られてしまうような絶頂の快楽の間、
シエスタの頭を離さなかった。逃げる余地も与えず、そこで受け止めるのが当然だと
言わんばかりに、腰に引き寄せたシエスタの頭をそのままにしていた。
それに気付いたのは、全て吐き出してしまったのではないかと思えるほどの放出が
収まってきた時だった。
呆けそうなほどの余韻の中で俺は俺自身がしていたことに気づき、
心臓が跳ねるようなショックの後、今さら過ぎる中でシエスタの顔を解放しようとした。
けれども……シエスタは、抵抗した。自分の口の中に出させることに抵抗したんじゃない。
まだ射精の終わっていない俺のペニスから口を離すことに、抵抗した。
俺が押し戻そうとする手に髪を擦られるのも厭わず、竿の部分についた
唾液や精液を唇の裏でこそげ落とすように締め付けながらゆっくり顔を引き、
それを亀頭のすぐ下に来るまで続けたころ俺の射精が完全に終わったのを確認すると、
僅かに零すのすら勿体ないとばかりにちゅるんと音を立てて吸い上げながら
先端から唇を離した。
「あ、あの……シエスタ」
何と声をかけていいのかわからない。無体なことをしてしまったのに対して謝る?
でも、シエスタはまるで不快や苦痛を感じているようには見えない。
それ以前に、その時のシエスタの、どこを見ているのかもよくわからない
とろけきった表情の色っぽさに、意識を釘付けにされてしまっていた。
■14
シエスタは軽く顎を上げ、口元に手を当てる。まさか、と思った次の瞬間、
ごくりとこちらまで聞こえる嚥下音をさせて、大量に口中に溜まったものを飲み下した。
「シエスッ…!!」
呼びかけるか呼びかけないうちに、シエスタは糸が切れたように
ふらりと俺の方へ倒れ込んできた。太股へ頬をつけ、ぐったりと体から力が抜ける。
「え……シエスタ、どうしたんだよ!?」
シエスタの髪を流し、表情を見る。夢から覚めたようにシエスタは目を薄く開いた。
そして、その眼前にまだ萎えきっていない、半勃ち状態のペニスがあるのを確認すると、
よろよろと顔を上げてその竿に舌を這わせてきた。
「ちょっと! ちょっと待てシエスタ!」
今度ばかりはその肩を掴んで引きはがす。シエスタは俺のペニスを物欲しそうに
呆然と眺めていたが、唐突に瞳に生気を戻らせたかと思うと、はっとして辺りを見回した。
「あ……あれ、わたし……」
シエスタはこちらが唖然としてしまうほど”いつも通り”の様子で頬に手を当てた。
「良かった、どうしたのかと思った」
胸を撫で下ろすと、シエスタはその時初めて俺に気付いたかのように俺を見る。
「あれ、サイトさん。あ、わたしってば、ごめんなさい! 続けます」
シエスタは急に慌てたかと思うと、再び俺の腰の上に屈み込んでペニスに顔を近づけた。
「ええ!? 待った待った! それは終わったでしょ!」
そこを手でガードして言うと、シエスタはぽかんとした表情で俺を見て、
「え、終わったって…。あ、そうですね。わたし、サイトさんにお口の中に頂いて……」
何言ってんだ大丈夫なのかシエスタ、と思っている間に、シエスタはぼっと頬を赤くした。
「あっ、あああ、そうでした。終わっちゃったんでした……」
羞恥に顔を俯かせながら、自らの唇に指を当てる。その後、舌を出してその唇を
ぺろりとなぞった。
「あの……ごめんなさいサイトさん。わたし、途中で何がなんだかわかんなくなってしまって。
サイトさんにご奉仕しなくちゃいけないのに、勝手な事。今度は、ちゃんとしますから……」
シエスタは今にも泣き出しそうな不安げな顔で、俺を見つめてきた。
「な、何言ってんだよ! 俺は滅茶苦茶良かったから。こっちの方こそ酷いことしちゃって」
「ほんとですか……?」
シエスタは半信半疑な様子。あんなに良くしてくれたのに、何が不安なんだろ。
「本当! ほんとにほんと! 信じられないくらい気持ちよかった」
シエスタを説得するために力説するも、かなり恥ずかしいことを言ってることに気付いて
思わず赤面。シエスタの方もはにかんで両手を胸の前でもじもじさせた。
「それなら嬉しいですけど……サイトさんにご奉仕してたら、わたしの方がその、
き、気持ちよくなってしまって。そのうち、頭がとろんとしてきて。
こんなんじゃご奉仕になりませんよね。次は、もっと頑張りますから」
頭がくらくらしてきた。まさか、意識もはっきりしない状態での行為であそこまで
翻弄されてしまうとは。もっと頑張られてしまったらどうなるのか、想像も追いつかない。
とりあえず、気を取り直す。俺はシエスタの肩に手を乗せると、こちらを向かせた。
今は、何よりシエスタに言わなければいけないことがある。
シエスタはまだ潤んだままの瞳で、俺を見返す。俺はコホンと一つ咳払いをして、
「その……ありがとう。シエスタのしてくれたこと、凄く嬉しかった」
一瞬間を置いて、シエスタは花が咲き開いたような笑みを見せた。
そのまま、俺の胸に顔を埋めてくる。
■15
「えへ……良かったぁ」
誉められた子供みたいに甘えてくるシエスタ。柔らかな体を押しつけられて、
さきほど果てたばかりなのに、また体が興奮してくる。
「えっと、じゃあじゃあ、サイトさんもまたして欲しいって思ってますか?」
「う、うん。思ってる」
わざと恥ずかしいことを言わせたいのだろうか。シエスタはいたずらっぽく聞いてくる。
「また、していいですか?」
「うん……いいよ」
これは新手の虐めか。
「それなら、今これからもう一回っていうのは?」
「……それは遠慮しておく」
もぞもぞと手をお腹の方へ滑らせてきたシエスタを制止する。
今、俺はシエスタを本気で怖いと思った。色んな意味で。
翌朝。タルブの村の前の草原に、ギーシュの呼んだ竜騎士隊が到着した。
一匹でも迫力満点なドラゴンが何匹もそろい踏みしている光景に圧倒されつつ、
寝不足の目を擦る。
「何だね、堂々の帰還だというのに不景気な顔をして」
欠伸を堪えている姿を、ギーシュに呆れられてしまった。
結局寝たのは明け方になってしまった上、精魂尽き果てたというか吸い取られたからな。
ゼロ戦に着々とロープがかけられていく様を眺めていると、軽快な足音が迫ってきた。
「サイトさんっ!」
振り向くと、日の光の下に輝くシエスタの笑顔。どきっとするのと同時に、
昨晩の月光の下での妖艶な姿とのギャップに女の子の不思議さを実感。
ところで、シエスタも寝不足なはずなのに嫌に顔色が良くてツヤツヤして見えるのは
気のせいでしょうか。
「シエスタ、どうしたんだその格好?」
シエスタは明らかによそ行きな服装に、宝探しに持ってきた大きな荷物を提げている。
「やっぱり、学院に戻ることにしました。正式な休暇になったらここに帰ってきますけど」
「え、なんで急に」
聞くと、シエスタは含みのある笑顔を俺に見せた。
そして、ちらりとキュルケとタバサの様子を確認する。
「さて、どうしてでしょう? あ、そろそろ準備が終わるみたいですよ」
シエスタは『竜の羽衣』に向かって軽快に走り出す。
「ふむ……? あのメイドの子、なんとなく変わったかな?」
黒髪が揺れる後ろ姿を見ながら、ギーシュが顎に手を当てて言った。
「そ、そうかな? 俺にはよくわかんないけど」
「親しすぎると見えないこともあるものだよ。まぁ、女性は魔物だからね。
いついかなる姿に変わるかわからないものなのさ」
肩をすくめてしたり顔で言うギーシュ。こいつがどこまで女性のことを
わかってるのかは怪しいが、ちょっと同感できる俺は苦笑するしかない。
でも、関係ないか。シエスタが俺にとって大事な女の子なのは間違いないんだし。
俺は荷物を担ぎ直すと、遠くで手を振るシエスタのところへ駆けだした。
つづく
[[前の回>X00-05]] [[一覧に戻る>Soft-M]] [[次の回>X00-07]]
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: