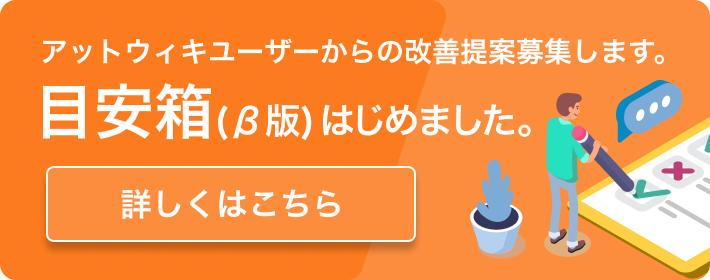「19-20」(2008/02/18 (月) 03:09:53) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
[[前の回>X00-07]] [[一覧に戻る>Soft-M]] [[次の回>20-72]]
**ゼロの飼い犬11 人形姫の溜息 Soft-M [#r695ee8e]
■1
「はぁ〜〜〜」
透き通るような青空の下、爽やかな午後の陽気に不似合いな深い溜息が響く。
俺がついたものではない。ベンチの隣に座ってるルイズのものだ。
ヴェストリの広場にやってきてから、今ので何回目なのか数えるのも馬鹿らしい。
「ダメだわ、やっぱりわたしなんかに詩作なんて無理よ」
その愚痴も何度目かわからない。ルイズはここ数日間の間、アンリエッタ王女様の
結婚式の際にルイズが唱えるという、祝辞の言葉を考えている。
しかし前に聞いた限りでは、ルイズの作った詩は出来が良い悪い以前に
詩と呼べるのかどうかすら怪しいもので、俺がダメ出しをして以来ちっとも進展がない。
今日もルイズは祈祷書とやらを眺めてうんうんと唸っており、
俺は意味もなくそれに付き合わされている。だって逃げると機嫌悪くするし、こいつ。
けど、ルイズはこれだけ苦心していて、何度も無理だ駄目だと繰り返しているわりに、
諦めて投げ出すとか姫さまに断りに行くといったことはしない。
プライドが高いのか、責任感があるのか。それに根気も一応伴っている。
その点は尊敬できるのだが、何せ致命的に詩のセンスが無いのが涙を誘う。
「あのさ、思うんだけど、参考にするものが何にも無い状態から
素人が詩を作ろうってのがそもそも無茶なんじゃないのか?」
見かねてそう聞いてみると、
「でも、この始祖の祈祷書を持って詔を考えるしきたりになってるんだもの」
ルイズは頬を膨らませた。白紙の本を眺めて何が変わるというのか甚だ疑問だ。
「そういう決まりなのかもしれないけどさ……」
地球にいたころ学校の課題で作文やレポートを書かされたことを思い出す。
そういうとき、いきなり原稿用紙やワープロを前にしたって何も書けない。
課題の題材に見合った資料とかと照らし合わせて書く内容を決めたはずだ。
ルイズが考えなくてはいけない、祝辞の詩の場合どうだろう。
図書館で詩の本を読んで参考にしてみる、とか?
頭を捻っていると、広場の端っこを小さなマント姿がてくてく歩いている姿が見えた。
身長より高い杖を重そうに持っているあの子は、タバサ。
無口で何を考えてるのかわからなくてとっつきにくいと思っていた彼女だけど、
この前の宝探しの時に色々あって、少し話しかけやすくなった。
タバサが小脇に小難しそうな本を抱えているのが目に入って、ピンとひらめく。
彼女にだったら相談できるかもしれない。
「ルイズ、ちょっと来い」
「え、何よ急に?」
ベンチから立ち上がって、ルイズの手を引きタバサのところまで走っていく。
「タバサ」
すぐ後ろまで行って呼びかけると、彼女は静かに振り向いた。
「?」
「悪いけど、ちょっと相談に乗って欲しいことがあるんだ。これから何するつもりだったんだ?」
「図書館に」
タバサは本を持った手を少し動かして、そう答えた。
「ちょうど良かった。実はだな……」
ルイズが姫さまの結婚式のために祝辞の詩を作らなければいけなくなったことと、
ルイズにも俺にも詩を作る技術なんかなくて、行き詰まっているという事情を話す。
「――それで、迷惑じゃなかったらでいいんだけど、参考になりそうな詩の本とか
そういうのを知ってたら教えて欲しいんだ。ほら、タバサっていつも本読んでるし」
手を合わせてタバサにお願いする。恩を着せるつもりじゃないけど、
タバサは『月の涙』の探索の時に俺に助けられたことについて、まだ義理を感じているらしい。
体で”続き”を払うっていうのは流石に冗談だと思うし本当にそんなので払われても困るので、
こういうお願いを聞いてもらうことでお礼の代わりにしてもらえないだろうか。
■2
「ちょっと、この子にそんなこと頼んだって……」
「いい」
ルイズが呆れた声で俺の脇腹をつついたが、タバサは短くそう返事をする。
「え?」
「構わない、協力する。図書館まで来て」
タバサは俺とルイズの顔を交互に見た後、踵を返して図書館の方へ歩き出した。
「相談に乗ってくれるってさ。ほら、行こうぜ……って、いてて!」
後を追おうとしたら、ルイズに耳を引っ張られた。
「ちょっと、いつの間にあの子を手懐けたのよ」
「手懐けたって、宝探しの時にうち解けただけだよ。痛いから離せって」
「ほんと? それだけ?」
ジト目を俺に寄せてくるルイズ。ごめんなさい、本当はそれだけじゃありません。
「今はそんなこといいだろ、早く追いかけようぜ」
「あ、ちょっと待ちなさいよ!」
ルイズをどうにか振りほどいて、俺はタバサの向かった先に走り出した。
「使えそうなのは、これとこれと、これ……」
タバサは図書館に着くなりそびえ立つ本棚の塔の上の方まで飛んでいき、
本をいくつか選び取って戻ってきた。それらを読書机の上に積み重ねる。
「各国の冠婚葬祭で使われた詩が解説されてるのが、この本。
こちらは有名な詩人の、四系統を季節になぞらえて詠われた詩の全集」
タバサはそのうち何冊かを取り上げて、ルイズに差し出した。
「あ、ありがと。でも、こんなのを参考にしちゃったら、盗作なんじゃないの?」
「まず、詩を読み慣れていないことには詩作なんてできない。
遠回りに思えるかもしれないけど、とりあえず自分で作ることは忘れて読んでみるべき」
タバサはルイズの目を真っすぐ見つめてそう言った。ルイズもその言葉と視線に
気圧されたのか、やや納得しきれない顔をしつつも椅子に座って読み始める。
タバサのやつ、ルイズをあっさり説得するとは俺も見習いたいもんだ。
「んー、俺はどうしようかな」
ルイズが詩集を読み始めてしまったので、俺は手持ち無沙汰になった。
何気なくタバサが持ってきた本のひとつを手にとってページをめくってみる。
さほど厚くもなく、挿し絵がちらほら載っている本だ。児童書か何かかな。
凛々しい剣士が宝探しやら幻獣退治やらをしている様子の絵が描かれている。
「これって、ひょっとして『イーヴァルディの勇者』?」
「そう。イーヴァルディの勇者を題材にした、詩……というより、童謡集」
タバサに聞くと、すぐに答えが返ってきた。あまりルイズの詩作の助けには
ならなそうだけど、どうしてこんなの持ってきたんだろう。
「ここは何て書いてあるんだ?」
童謡だけあって文章も簡単そうだ。最初のページを開いて聞いてみる。
「『イーヴァルディ、勇気ある少年、心優しい少年。剣を振るのは友のため……』」
タバサは指で文字をなぞりながら、中身を朗読してくれた。
「……あれ?」
「どうしたの?」
何だか変な感覚に襲われる。タバサが読んでくれた部分が、急に”わかる”ような
気がしてきたのだ。この単語が『イーヴァルディ』で、その単語が『少年』で、という風に。
「えっと、隣のページには何て?」
「『イーヴァルディは友のため、深い森に向かう決意をした。
病気で伏せる友のため、魔物の巣くう森の中、薬草を採りに踏み行った』」
やっぱり。タバサに読んでもらう前から、そのページには『イーヴァルディが友人のために
何かすることになった』といった内容の文章が書かれていることが何となくわかった。
■3
一度教えられた単語をすぐに覚えて、別の文章の中でどのように使われているのかが
一瞬で判断できてしまったことになる。俺ってこんなに語学力あったっけ?
首を傾げつつも、ルイズがメモを取るために持ってきた紙とペンをひとつずつ拝借する。
これならわりと簡単にこの世界の文字が読めるようになりそうだ。
「悪いけどタバサ、ちょっと言葉を教えてくれないか? そうだな、まず『ルイズ』」
タバサは俺の態度を見て何か感じ取ったのか、隣に座って紙にペンを走らせてくれた。
アルファベットを崩したような字が六文字。その隣にカタカナでルイズと書いておく。
その調子で、読めたら後々便利そうな単語をタバサに書いてもらってリストにした。
英語の授業で単語帳を作ったのに似ている。
その後にもう一度イーヴァルディの童謡集を読んでみたら、やはりさっきよりも
わかる部分が増えている。単語帳を参照しなくても大丈夫なくらいだ。
まだ知らない単語はタバサに教えてもらいつつ、本を読み進めていく。
「……ちょっと。人が詩の勉強してる横で、何してんのよ」
しばらくの後、不意に禍々しい怒気を孕んだ声が聞こえてきた。
気がつけば、俺とタバサの顔は目と鼻の先まで近付いて、肩を寄せ合って
本を覗き込んでる状態。俺は慌てて離れて、ルイズに誤魔化し笑いを向ける。
「えっと、ほら、俺たちも勉強だよ。せっかくだし字を学ぼうかな〜って」
言い訳すると、ルイズは俺を睨みつけた後、その視線をぎろりとタバサに向ける。
「……何かヘンじゃない? どうしてタバサがそんなにアンタの言うこと聞くようになってるのよ。
やっぱり何かあったんじゃないの?」
ぎくっ、鋭い。普段は誤解ばっかりするくせに、なぜこういう所でだけ鋭いのか。
「差し当たり、それは問題じゃない。あなたは詩作に専念すべき」
タバサはルイズのガン見にも動じず、そう言い切った。ルイズはむぐ、と言葉に詰まる。
「後できっちり説明してもらうかんね。覚悟しときなさいよ」
タバサの正論に何も言い返さず、ルイズは詩の本に視線を戻した。
助かったけど今夜大変なことになりそうだ。
溜息をつくと、タバサがまた俺に肩を寄せてくる。まだ本を読むのに付き合ってくれるらしい。
やっぱり、タバサの方も『月の涙』の時の恩返しのつもりなのかな。
すぐ近くにタバサの顔が迫って、吐息まで感じられる。あの夜素肌で抱き合ったことを
思い出して胸が高鳴ってしまいながら、タバサの好意に甘えて勉強を続けることにした。
∞ ∞ ∞
夕食前の時間までわたしたちは図書館で過ごすことになり、ルイズとサイトは
わたしに礼を言った後、本をいくつか借りてから帰って行った。
夕食を済ませて部屋に戻ったわたしは、懐から一枚の紙を取り出す。
今日、成り行きでヒラガサイトに字を教えることになった時、
彼は見たこともない字を書いていた。この紙は、その字をこっそり模写したものだ。
わたしがトリステイン公用語の単語を紙に書いて教えた後、彼はその単語の意味を
”自分の使っている字で”その横に書き加え、簡易的な辞書のようなものを作っていた。
つまり、彼は文字が扱えないわけではなく、母国語の字は使えるがトリステイン公用語は
読み書きできない状態であるのだということがわかる。
彼が書いた単語の写しを眺める。彼の主人の名前、『ルイズ』。わたしの偽名、『タバサ』。
それぞれ三文字。最初から母音と子音が合わさって一文字になっているのだろうか。
次の単語に目を向けると、『平賀才人』。これで彼のフルネームを意味するらしい。
彼が書いた単語のうち、『ルイズ』や『タバサ』、あるいは『トリステイン』等に比べると、
明らかに複雑な文字が使われている。
■4
さらに見ていくと、『学校』『魔法』『姫さま』『街』……。正確に写せているのかどうか
自信が無いくらい込み入った文字が並んでいる。
そして、『火』『水』『風』『土』。四系統を示す言葉が、それぞれ一文字で表されている。
これで大体の予測がついた。彼の母国語は、トリステイン公用語が表音文字であるのに対し、
表意文字という形式のものなのだろう。東方にはそういった字を使う国もあると聞いている。
けれど、わたしが知っているどんな文字とも合致しない。完全に異質な言語。
その紙を机の上に置くと、わたしはベッドに腰掛けた。
彼は自称していたロバ・アル・カリイエよりも、もっと遠い所から来たんじゃないだろうか。
容貌や常識がわたしたちとは大きく離れていることに加えて、
『月の涙』探しに巻き込んでしまった時に彼がわたしに言った言葉が印象に残っている。
昔の人間は摩擦熱で火をつけていたとか、人間が他の動物に負けなかったのは
武器を扱えたからだとか。彼はさも当然のような口調でそう言った。
そんな話は聞いたことがないのに、完全な出鱈目だとも思えない口ぶりと内容。
以前から疑念を抱いていた。彼はそもそも、貴族と平民の身分差や……それどころか、
魔法すら存在しない土地からここに召還されたのでは、と。
大きく溜息をつく。どうしてこんなに真剣に彼のことを考えているのだろう。
ただの好奇心? それとも?
思い当たるところがある。それは、彼が始祖ブリミルの使い魔であったという
『ガンダールヴ』なのではないかと思えること。左手のルーン、武器を自在に扱える能力、
そして人間の使い魔であるという特殊性。
それらの観点から、ヒラガサイトは伝説の使い魔なのではないかと予測できる。
ならば、誰だって多少の関心は持つに決まっている。
――けれど、仮に彼が伝説の使い魔だったとして、だから何?
わたしは宝探しの時の一見で、彼に恩と借りを感じている。それは返すべき。
重要なのはそれだけであって、彼の素性は関係がないはず。
無用な詮索も勝手な想像も、まったく意味がない。
そう頭を切り換えようとしたとき、窓が開き、夜風と共に人影が室内に転がり込んできた。
「あいたた……やっぱり慣れないのね、きゅいきゅい」
長い髪を纏った裸身をよたよたと立ち上がらせてそう言うと、わたしの使い魔、
風韻竜のシルフィードがベッドの側に寄ってくる。
視線で何か用? と聞く。彼女が人間の姿に化けてまで自らわたしの部屋に来るのは希だ。
「お姉さまが何だか悩んでるみたいだったから。最近のお姉さま、何だか様子が変なのね」
そんな自覚はないけど。遠目からでもわかるくらい変わった態度をとっていただろうか。
「シルフィを甘く見ないで欲しいのね。お姉さまのことなら何でもわかるの。
ずばりお姉さま、あの平民の子のこと考えてたでしょう?」
シルフィは得意げに指をくるくる回しながらそう言った。当たっているのが少し癪だ。
彼女にまで言い当てられて、わたしの心がちくりと痛む。
「……わたしは、打算的なことを考えてる」
自分でも後ろめたかったからだろうか。話し相手が出来て、わたしは柄にもなく口を開いた。
「? どういうことなの?」
「彼……サイトのことが気になってるのは事実。けれど、それは彼に窮地を助けられたから。
彼が有能で、頼りになる存在だと知ってしまったから。
だから……わたしは今後何かあったときに彼の協力を得るために、彼のことを知って、
彼にある程度近付いておきたいと考えている」
わたしは胸の中に渦巻いていたものを一気に吐露した。そう、結局こういうこと。
わたしは独りで戦うと決めていた。それは他人を巻き込まないためという意味と、
他人に甘えないための意味があった。
でも、わたしは『月の涙』の探索の時に、彼が強い人……、ただ能力があるだけでなく、
機転を利かせることも仲間を勇気づけることもできる人だと知った。
そんな人と協力することがどれだけ有効なのかも知ってしまった。
■5
そして何より、彼が損得抜きで他人のために助力してくれる、優しい人だと知ってしまった。
もしわたしが甘えて頼っても、受け入れてくれる人だと。
だからわたしは、彼に付け入ろうとした。報いだなんて言って体を差しだそうとしたのも、
その後に冗談交じりに思わせぶりなことを言ったのも、今日彼の相談に乗ったのも。
全部彼に近付くため。わたしに関心を持って貰うため。
そして、いざというときが来たら、彼の力を”使わせてもらう”選択肢を得るため……。
彼の正体についてのヒントを調べているのも、その一環に過ぎない。
突き詰めればそういうこと。自分の浅ましさを改めて認識する。
「わたしは目的のためだったら汚い手だって惨めな手だって使う。
それを確認してただけの話」
自嘲してそう言うと、シルフィは眉をひそめて額に人差し指を当てた。
「きゅい、お姉さまの考えることはごちゃごちゃしててシルフィにはよくわからないのね」
「あなたにはわからなくていい。わからない方がいい」
そう返すと、シルフィは腕を組んでわたしをじっと見た。
「もっと簡単に言って欲しいのね。つまり、お姉さまはあの子……サイトのことが好きなのね」
「え?」
あっけらかんとした口から飛び出してきた言葉に、わたしは一瞬呆ける。
「だって、頼りになる男の子のことが気になって、その子と仲良くなりたいって思うのは、
要するにお姉さまがその子のことを好きだってことなのね。ちがう?」
「ちが……!」
何を言ってるのかこの使い魔は。とんでもない台詞に混乱しかけてしまう。
「そんな浮ついた感情じゃない。もっと不純で、即物的な……」
「また難しい言葉でややこしくするの。そんなこと言われてもわかんないのね」
シルフィはやれやれと肩をすくめた。とりつく島もない。シルフィの言い分を
否定する言葉を探すけど、見つからない。自分でも不思議なくらい動揺している。
違う。恋っていうのはもっと純粋な……、いや、わたしだって恋愛がそんな
綺麗で甘美なだけのものじゃないことくらい知ってる。お互いの立場とか条件とか、
感情だけで済まない周囲の環境要素も含めた上で恋愛というものは成立する。
そもそも恋愛感情というのは男女がより優秀なパートナーを見つけ出し、
その相手と結ばれることを目的として存在するものだ。つまり、簡単に言えば
自分に対しより多くのメリットを提供してくれる異性を”好き”になるようにできているはず。
……あれ? 待って。そうすると自分を助けてくれた、自分にとって頼りになる異性に
恋してしまうのはむしろ必然? しごく当然のこと?
おかしい。落ち着いて。シルフィの言葉を否定するつもりだったのに、
これじゃあ逆に肯定することになってしまう。
いつも冷静であるように努めてるのに、頭が熱くなってくる。
「……なんだか余計に悩んじゃってるみたいなのね。でも恋をすると悩むって話なの。
じっくり一人で悩むといいのね、お姉さま」
「あ……シルフィ!」
シルフィは呆れた声で言うと、窓から身を躍らせて風竜の姿に戻り、飛び去ってしまった。
わたしを混乱させることだけ言って帰るなんて、一体何をしに来たのか。
とっさに立ち上がってしまい……わたしは、いつになく自分が興奮していることに気付く。
ただ座っていただけなのに心拍が早くなっている。頬に手を当てると、熱くなっていた。
■6
「彼のことが、好き……」
シルフィが出て行った窓を閉めると、わたしはベッドに身を横たえて呟く。
ヒラガサイト。ゼロのルイズの使い魔。あらゆる意味で普通の使い魔とは異なる、
変わった存在。彼に対してまったく興味がないといったら嘘になる。
彼については、あの『月の涙』探しの一件よりも以前から、ある程度関心があった。
その理由は……彼が、強いからだ。ギーシュ・グラモンに決闘で勝ったこと。
『破壊の杖』を使って盗賊フーケを捕まえたこと。わたしは直接は見ていないけど、
アルビオンでスクウェアメイジであるワルド子爵を倒したということ。
メイジの強さとは質が違う彼の能力。その正体を知りたいとは思った。
けれどその関心は、わたしが知識を得るために本を読みあさるのと
同等のものであるはずだった。興味があるのは彼の能力であって、彼自身ではない。
それは今だって変わらないはず。
「……本当に?」
自問する。自分の感情を考え直す。
『月の涙』の探索の際にわたしが杖を手放してしまい、また彼も剣を失ってしまったとき。
その時、わたしは彼に助けられた。魔法が使えなくなり、また毒により体力も奪われていた時、
わたしは剣を持っていない、普通の平民とさほど変わらないはずの彼を頼った。
わたしはあの時……安心した。あれだけの窮地で、生きて帰れる公算が極めて低い状況で、
彼が側にいてくれたことで。彼がわたしのためにしてくれたことで、安心してしまった。
平時の学院にいても意識することなどない安心。あの夜のわたしはそれを感じた。
目を閉じて、あの時の感覚を思い出す。冷えた体。失われた体力。
意識もはっきりしない状態で、わたしは彼の肌が、彼の体温が、心地よかった。
彼がわたしを慈しむように抱きしめ、温めてくれたのが嬉しかった。
嬉しかったからこそ、わたしはそれに溺れてはいけないはずだった。
他人の温もりに甘えたら、そこから決心や覚悟が鈍る。いざというときに自分一人で
窮地を切り抜けることができなくなる。だからわたしは、彼の優しさを拒むべきだった。
――なのに。
胸の中に、熱く切ない物が膨らむ。
わたしは彼の優しさを享受してしまった。それどころか、自分の方からもっと求めてしまった。
自分を律することができなかった。それほどまでにあの時のわたしは心も体も弱っていて、
そして彼の温もりが、彼の言葉が甘美だった。
それがわたしの弱さ故のことならばまだいい。けれど、あの時わたしは彼に対し、
わたしに関心を持たせるようなことを言った。彼の能力と優しさを、
後々利用できるようにするために。自分の弱さにも汚さにも、嫌気がさす。
こんなわたしの感情が、恋なわけがない。
それに。わたしは目を瞑ったまま、自分の胸にブラウス越しに手を当てた。
その指を腹部の方に滑らせていき、腰から足まで移動させる。
下級生まで含めて、この学院で一番貧相なんじゃないかと思える子供そのままな体。
こんな体でわたしは、彼に媚びを売って関心を持ってもらおうなんて思った。
お笑い種。身の程知らずもいいところ。惨めさと滑稽さに、自嘲の笑みまで浮かぶ。
あの夜自分が彼に言った言葉を思い出して、羞恥が湧き上がってくる。
やっぱり、あの時のわたしはどうかしていた。
仮に恋であったとしても、こんな体で恋愛だなんて文字通り十年早い。
わたしは内面でも外見でも、恋をするに足る資格が無い。
自分の体の幼さを再び確認するかのように、
足まで這わせた手を胸の方まで戻す。すると――。
■7
『タバサ、可愛い……』
あの時。わたしが彼に無茶な要求をして、体を弄らせた時の言葉が頭の中に響く。
そう言われたとき、彼はわたしの胸を触っていた。この、まるで膨らんでいなくて、
乳房とも呼べない胸を。こんな風に。
指に力を入れて、胸全体を撫で回す。じわじわと甘い痺れが湧き上がってくる。
心臓が早く鼓動しているのが感じられる。
彼にされたときは、こんなものじゃなかった。もっと、頭も体もとろけてしまうような……
甘くて温かくて、なのにもどかしい感覚だった。
『本当だよ。絶対に嘘なんかついてない。俺は小さい子が好きだからタバサに
下心持ったんじゃなくて、タバサが可愛いから下心持ったんだよ。わかるだろ?』
その後、やや焦ったような口調で彼はそう言ってきた。耳元に吐息が当たって、
耳たぶを舌でくすぐられて、小さく噛まれて……。まるで自分の体が自分の物で
なくなってしまったみたいに、未知の感覚に震えた。
わからない。彼がわたしに下心を持ったなんて言ったのは、わたしが言わせたから。
彼がこんな体に興奮なんてするわけない。だって、キュルケや彼と仲が良いメイドの、
女性らしい体つきに目を奪われていた。彼女たちに近寄られて嬉しそうにしていた。
あんなの、ただわたしに気を遣っただけの方便。
『可愛い、綺麗……』
「……っ!!」
その声を思い出して、体がびくんと跳ねた。ベッドがきしむ。嘘? 本当に嘘?
あんなに優しく、労るような手つきでわたしを撫でてくれたのも。
その時かけてくれた言葉も。全部嘘? 演技?
違う。彼はそんなことができる人じゃない。そんなことをする人じゃない。
嘘がつけない人で、真っ直ぐで……わたしとは正反対で。
だから、わたしはあの時彼に――惹かれたんだ。
「ふっ……は、ぁ……ぁあ……!」
それを認めてしまったとき、体中にびりびりと快楽が走り抜けた。
抑えていた吐息があられもなく口から漏れる。
あの時の彼の指。ブラウスの上からじゃ再現できない。
シャツのボタンを外すと、前をはだけた。その下のシミーズを胸の上まで捲り上げる。
あの時と違って自分の背中に触れているのが温かい肌ではなく、
冷たいベッドのシーツだということを物足りなく感じながら、露わになった胸の先に
指を持って行く。
指先で引っ掻くと、弾けるような刺激と共に胸の奥が締め付けられる。
わたしの乳首、虫さされの跡か何かと区別がつかないような小さな部分が、
固く熱くなっていた。夢中になってその部分を摘み、揉みほぐす。
勝手に顎が持ち上がった。喉の奥からよくわからない声が絞り出される。
両脚が突っ張り、足の指がシーツをぎゅっと握りしめる。
気持ちいい。頭がとろけそう。でも、彼にされたときはもっと良かった。
もっと満たされた。わたしが記憶を頼りに真似をしたって、とても追いつかない。
触り方が違うっていうのもある。けど、一番違うのは……温もり。
彼の胸の温かさ。彼の指の温かさ。彼の吐息の温かさ。彼の言葉の温かさ。
それが、わたしを包み込んで。わたしの心を覆い隠した雪を溶かすみたいな
柔らかい灯りになって、わたしを弱くした。わたしを安心させてしまった。
体だけでなく、心まで愛撫してきた。
わたしは、その心地よさを、温かさを。また得たいと思ってしまった。
だからだ。『それじゃ納得できない』だの、『続きは後にしてもいい』だのと彼に言ったのは。
彼への恩や借りという名目こそ、わたしが彼に使った方便。
■8
わたしは今日、中庭で彼に声をかけられて、期待してしまった。
もちろん、彼が正直にわたしの言った『続き』を求めてくるなんて思っていなかった。
けれど、彼がわたしに話しかけたということは、
わたしにいくらかの関心を持ってくれたということだから。
そして、彼の隣に彼の主人であるルイズがいるのを見たとき……落胆した。
彼のわたしへの頼み事が、ルイズを助けるためのものだということを知って、
残念だと思った。
彼に対して何か明確なものを求めていたわけではないのだけれど……。
それでも、わたしの中には確かな不満が生まれた。
わたしが彼に対して借りがあるのだから、わたしから何か求める権利なんて無いのに。
その気持ちは何なのだろう。彼と一緒に本を読んでいたときに、ルイズから咎めるような
声をかけられて”邪魔をされた”と思ったのは。
二人で連れ添って部屋に帰って行くのを見送って、胸に嫌な気持ちが灯ったのは。
わたしは何を求めていたというのだろう。
火照った身体の中に、甘い快感と、切ない苦みが同時に溜まっていく。
あの夜の感覚を思い出すようにして、指を胸から下の方へずらす。スカートのホックを外して
膝の方まで下ろし、下着の上から”そこ”に触れると、じんわりと湿気を帯びていた。
彼の指は、壊れ物を扱うみたいに、繊細にここを触れた。わたしの女性器。
恐らく、子供を産むための機能どころか、男性を迎え入れるための機能すら
備えていないであろう、未発達の性器。
下着の中に手を差し入れて、直接触れる。発毛もない。濡れ方もたぶん少ない。
スリットを開いて膣口と思しきところに指を差し入れようとしてみても、すぐに苦痛が襲ってくる。
今までさして気にしていなかったのに、不安になる。このままわたしの体が
ろくに成長しなかったらどうしよう。そう思ってしまう。
凍り付いたように時を止めてしまった体。それが、今さらながら疎ましく感じられる。
誰に差し出すわけでもないのに。誰に抱かれるつもりでもないのに。
けれど、もし、ちゃんと成長していたら……身長も、肉付きも、年齢相応のものだったら。
そうしたら、あなたは――。
身体の奥に膨らんだものが、今にも弾けそうになってきた。
彼にそうされたように、片手の指をスリットに当てて滑らせる。もう片方の手は胸を弄る。
この心の雪を溶かしてしまいそうになったのだから、もしかしたら、この身体の氷まで
溶かしてくれますか。まともにものを考えられなくなった頭に、幻想に似た思考が浮かぶ。
そのままわたしは指を動かして、追いつめられていって……。
あの夜、彼に抱かれながらの時よりもずっと冷たく味気ないベッドの上で、独りで達した。
波が引いた後、荒くなった息を整えながら衣服を整えようと身をよじらせると、
手に何か固い物が当たった。引き寄せると、それは一冊の本。
寝る前に読んでそのままベッドの上に放置してしまったものだ。
『イーヴァルディの勇者』の研究書。題材が創作物語なので、一般的な意味での
学術書ではない。その中では、イーヴァルディの勇者とガンダールヴの類似性が
指摘されていた。もちろん、ただの俗説に過ぎない。
わたしはその本のページをぱらぱらとめくった後、枕元に戻して再び目を閉じる。
胸の奥から深い溜息が漏れる。彼の腕の中の温かさと、彼の背中の広さとを
思い出してしまって……。一人でいるこのベッドの上が、やけに寂しく感じられた。
つづく
[[前の回>X00-07]] [[一覧に戻る>Soft-M]] [[次の回>20-72]]
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: