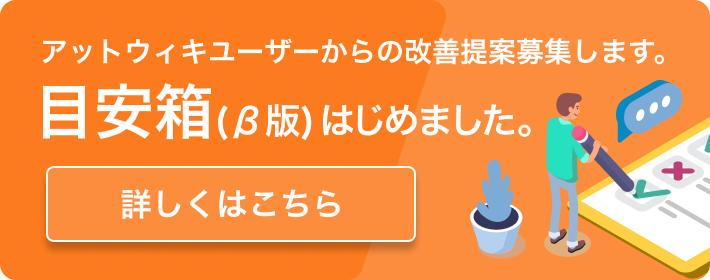「27-684」(2008/02/18 (月) 03:21:52) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
彼女の計画
それは丁度2月になったばかりの頃だった。
私は図書館である本を探し回って色んな本棚を行ったり来たりしていた。
探し始めてからもうかれこれ3時間は経過しているが、一向に目的の本は見つからない。
そういう事に興味を持つ以前、というよりは彼とそういう仲になる以前に見つけて、その時はどうでも良いと捨て置いてしまったのが今になって悔やまれる。
「うー…、見つからない…」
誰かが既に持ち出してしまったのだろうか?もしそうだったら絶望的。
私は半ば諦めながら本棚に寄りかかる。その拍子に本棚がぐらりと揺れ、上から数冊の本が落ちてきた。
「いっ!ったぁぁ…」
そのうちの一冊が私の頭に直撃して私は頭を押さえながら少し悶絶してしまった。
片付けなきゃと思い、落ちてきた本に手を伸ばすが、取ろうとした本のタイトルを見て私は飛び上がりそうなほど嬉しくなった。
「あった…!」
これをちゃんと読めば、彼をきっと喜ばせれるはず。
私はその本を大事に抱えながら図書館をいそいそと出て行った。
「決戦は2週間後…」
彼から聞いた、女の子が意中の人に愛を囁く日。
そう、確か彼はバレンタインデーと呼んでいたはずだ。
準備は抜かりないように、彼と最高のバレンタインデーになるように、私の計画は始まった。
#br
2月14日当日。空は晴れ渡り、とても気持ちの良い朝だった。
前日無事に約束を取り付け興奮しっぱなしだった私は、なかなか寝付けなかったものの、何とか空が明らむ前には寝れていたと思う。
ベッドから出てカーテンと窓を開けると、以前見かけた時と同じように彼は素振りをしていた。
彼も興奮して早く起きてしまったのだろうか?もしそうだとしたら私は嬉しい。
私は手早く何時もの服に着替え、杖とタオル持ち、前々から念入りに準備をしていた荷物をバスケットに積めて窓から飛び出した。
少し驚かせてみよう。そう企んだ私はすぐさま呪文を小声で唱える。
「レビテーション」
私の身体が重力に逆らうようにふわりと軽くなる。そのままふわふわと彼の元へ降りていった。
「サイト」
「ん?おわっ!?」
彼はふわふわと降りてくる私を見つけると素っ頓狂な声を上げた。
どうやら成功したようだ。
「いきなり上から降りてくるなよ…。それに…、パンツ見えてたぞ?」
彼の言葉に驚き、私は地面に着地しているにも拘らずスカートを抑えてしまった。
見られてたなんて…、ちょっと失敗…。
「サイト、約束覚えてる?」
「あー、あぁ…、覚えてるよ」
「じゃあ、今から出かける?」
彼は顎に手を置きながら、うーん、と悩んでいる。約束はしていたけれど、こんな早い時間からでは迷惑だっただろうか?
でも、出来れば彼と一分一秒でも長く一緒に居たい。
「…駄目?朝は何か予定ある…?」
「いや、ないよ。うーん…、分かった。行こうか」
そう言って彼は笑いながら私の頭を撫でてくれた。
きゅんと胸が震え、嬉しさと恥ずかしさ、色んな感情が溢れてくる。
私はやっぱり彼のことが本当に好きなんだと改めて実感しているような気持ちだった。
「それにしてもシャルロット、凄い荷物だな。中は何が入ってるんだ?」
彼は私が持っているバスケットが気になるのか覗き込もうとするが、私は背中にさっと隠す。
これを見られてしまっては今日の計画が頓挫してしまう。
「ん…、着くまで秘密」
「気になるなぁ…。それじゃあ、着くまで楽しみにするかね」
「じゃあ、シルフィ呼ぶね」
私は空に向かって口笛を吹いた。
すぐに聞き慣れた羽音を響かせながらシルフィードが降りてくる。
彼女にも今日の計画のことは話をしている。詳細を聞かせると、「お姉さまもやっぱり恋する乙女なのねー」なんて言いながら快く承諾してくれた。
「きゅいー。お姉さま、サイト、おはようなのー」
「あぁ、おはよう。朝からごめんな?」
「気にすることはないのねー。今度美味しいもの食べさせてくれればそれでいいのねー」
「大丈夫。ちゃんと用意する」
私とサイトはシルフィの背中に乗り込んだ。
シルフィはそれを確認するとすぐに上昇を始める。
「何時もの場所へ」
「はいなのねー」
以前に使ってから、サイトとの逢瀬の時には頻繁に利用する例の泉の場所まで向かってもらう。
私は何時も通り彼の膝の上に乗り、彼にもたれるようにして座った。
彼も慣れたもので、私が座ると胸の下に両手を回して抱き締める様に私を包んでくれる。この時が私の一番幸せな時。
素振りをしていたせいなのだろうか?少し彼の匂いが強いように感じる。
「ねぇ、サイト」
「ん?」
私が頭を上に向け、彼を見上げると、にっこりと微笑みながら私を見つめてくる。
「サイトの匂いがする…」
私は鼻先を彼の胸に擦り付ける様にしながら、胸一杯に彼の匂いを吸い込む。
「素振りしてたから、汗臭いだろ?」
「ううん…、そんな事ない。私は貴方の匂いが好き。こうして抱かれながら貴方の匂いを感じる事が出来て私は幸せ」
「はは、嬉しいやら恥ずかしいやら」
彼は困ったような笑顔で私の頭をまた撫でてくれる。照れくさいのか少し乱暴に、だけど優しさが伝わるような感触に私は目を細める。
「サイト…、私…、んっ!?…ちゅっ、ん、ふぁ…、んん…」
いきなりのキスに驚いたけれど、すぐに彼とのキスに没頭する。
彼は丹念に私の歯や歯茎まで嘗め回し、舌に吸い付いてくる。
私もそれに応えるように舌を絡ませていく。
「んふ…、ちゅ、んっ、んれろ、んちゅっ、ぢゅるる、んふあっ…、ちゅぅっ、ちゅるっ、んっ、ちゅっ…。」
そのまま彼とのキスは泉に着くまで続いた。
「じゃあ、ごゆっくりなのねー。サイトー、お姉さまの事よろしくなのねー」
「あぁ、分かってるよ」
2人が何かを話しているようだけど、私は長い時間のディープキスに頭の中まで掻き回されたようにとろとろになっていて、何を話しているのかあまり聞こえなかった。
「シャルロット、大丈夫か?」
地面にへたり込んでぼんやりとした表情をしながら荒い息をついている私を心配したのか、彼は私の傍まで来て覗き込んでくる。
「う、うん…、らい、じょうぶ…」
呂律が回っていないけれど、なんとか答えられた。
立ち上がろうと思ったが、足が震えて力が入らず、それも叶わなかった。
「サイト、そのバスケット取って…」
「ああ」
彼はバスケットを取ってくると私の前に置いてくれた。
「ちょっと、準備が、あるから、はぁはぁ…。サイト、こっち見ないで…」
「ん、分かったよ」
彼が少し離れ、私に背を向けるのを確認してから、私は着ている服を脱ぎ始める。
全裸になってからバスケットの中を開け、持ってきた物を取り出した。
彼の居た世界ではチョコレートという物を用意するらしいけれど、それがどんな物か私には分からなかった。
彼が言うには甘いお菓子という事なので、代用としてジャムを用意した。
それともう1つ、3メイルほどある真っ白なリボンを自分に巻きつけていく。
本に書いてあった事、私の身体をプレゼントとして用意し、彼にジャムを塗ってもらってそれを味わってもらう。
欲を言えばクリームとかを用意したかったけれど、そうもいかなかったので何種類かのジャムを用意した。
これならば、色んな味の私を味わってもらえる…。
何度か転びそうになりながらも何とか私は自分の身体にリボンを巻いた。
乳首とアソコにリボン当たって擦れるたびに声を上げそうになるが、声を上げてしまうと彼は確実にこっちを振り向くだろうと思い、必死に我慢する。
「ん…、っくぁ…、ひぅ…」
快感に負けないように、歯を食いしばりながらリボンを結んだ。
乳首は完全にぷっくりと硬くなって、溢れた愛液がリボンに染みを作っていく。
「サ、イト…、こっち向いていいよ…」
「ん、何やってたんだ?シャルロットおおおおーー!?」
彼が中庭で上げたような声と同じぐらいかそれ以上の声で驚いている。
「今日、バレンタインだけど、チョコレートって分からなかったから…。代わりに、このジャムで私をたくさん味わって…?」
何度も練習した台詞、何とか言えた…。
「シ、シャルロット…」
彼はぷるぷる震えながら私を見つめてくる。
もしかして、私は何か間違ってしまったのだろうか…?そんな不安が頭をよぎった。
「最高に嬉しいバレンタインのプレゼントだよ!!」
良かった。失敗じゃなかった…。
その後私は持ってきたジャムが無くなるまで彼に味わい尽くされた。
サイト、貴方を愛しています。
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: