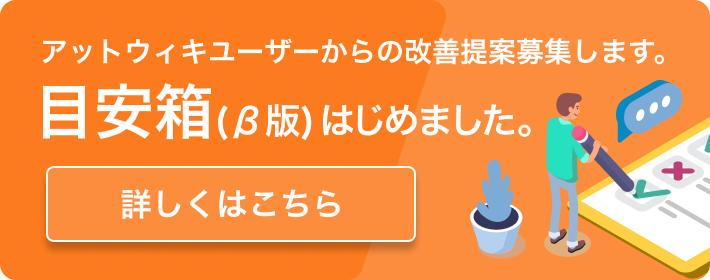「X00-28」(2008/02/18 (月) 03:37:52) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
[[前の回>X00-27]] [[一覧に戻る>Soft-M]]
ゼロの飼い犬17 真夏の雪風 Soft-M
■1
「ちょっとサイトくん、いいかしら?」
日が変わるまで開いている『魅惑の妖精亭』のクローズの仕事がようやく終わって、
さぁ何か食べてから寝るかと大きな伸びをした夜明け前。
未だに慣れない鳥肌が立つような野太い猫撫で声で呼び止められた。
「スカロン店長。なんですか?」
声の方に振り向くと、これまた慣れない、派手で露出の多い服装から
筋肉質の体がはち切れそうになってる男性。俺の雇い主のスカロン店長に聞き返す。
「明日……、うぅん、もう今日ね。今日、サイトくんに呼び出しがあったのよ」
店長はウィンクしながら片指を立て、にっこり笑ってそう答えた。
明日はラーグの曜日で、このお店の定休日になっている。
「呼び出し? 誰からですか?」
「それがね、昨晩の営業中にタバサちゃんが来てね、
サイトくんに予定が無いなら、待ち合わせの伝言を伝えて欲しいってお願いされたのよ」
「タバサが?」
タバサといえば、数日前にキュルケやギーシュ、モンモランシーと一緒に
この妖精亭までやってきた。あの時はキュルケのせいで酷い目に遭ったのだった。
「以前のお礼と、この前のお詫びがしたいって言ってたわよ」
「まだそんなこと気にしてたのか……、俺に直接言ってくれればいいのに」
「そしたら多分遠慮されるからだって。あの子、サイトくんの性格をわかってるわね」
くすくす笑う店長。タバサめ、そんなことまで計算して店長に言伝を頼んだのか。
「今日のお昼の11時に、チクトンネ街の中央広場の噴水で待ってるって。
明日の夜はお店の定休日だから、帰るのが遅くなっても構わないわよ」
「わかりました。行ってみます」
「確かに伝えたわよ〜。それじゃ、お・や・す・み! 楽しんできてね♪」
店長は俺に投げキッスをすると、腰をふりふり厨房から出て行った。
タバサから、お礼の呼び出し。未だにそこまで恩を感じてくれてることにむず痒くなって
しまいつつ、どんなことをしてくれるのかとちょっと楽しみになる。
そうと決まったら、遅刻しないようにさっさと寝ておこう、と部屋に戻るべく廊下へ出ると。
「サイト」
「うぉっ!?」
戸を開いたすぐ前にルイズが居て、思わず後ずさりしてしまう。
「何よその反応、失礼ね。ちょっと声が聞こえたけど、店長と何か話してたの?」
「え? あー、うん、ちょっとね。店長に頼まれて、明日の昼前に出かける用事ができた」
つい、そんな嘘をついてしまった。女の子と待ち合わせすることになったなんて言ったら、
何をされるかわかったもんじゃない。
「あんた一人で?」
「あ、ああ」
じっと俺の顔を見つめるルイズ。何か不自然だったかな。正直に言うべきだったか……。
わたしも行く、なんて言われたらどうしよ。いや、別にルイズと一緒でもいいのか?
「……わかった。じゃ、早く寝ましょ」
あれこれ考えているうちに、ルイズはふっと身体から力を抜いてそう言った。あっさり踵を返すと、
屋根裏部屋へ向かってしまう。何となく拍子抜けしてしまいながら、俺はその後を追った。
女子寮のルイズの部屋にあるのより小さいベッドに、二人で潜り込んで就寝する。
あまり寝心地が良いとは言えないけど、仕事で疲れてるおかげですぐに睡魔が襲ってくる。
もう重たくなっている瞼を薄く開いて、俺の手を枕にしているルイズに目をやると、
こちらを向いて猫みたいに身体を丸くし、早くもすやすやと規則正しい寝息を立てていた。
遅ればせながら状況を説明すると、今は学院が夏休みになっている期間。
ルイズは姫さまからの要請によって、平民の暮らしの中にとけ込み
世間の情報収集をする任務を任せられた。
その後、色々あって俺たちは『魅惑の妖精亭』という酒場で働きつつ、
客から巷の噂や世評を聞き出すという仕事をすることになったのである。
平民に混じって給仕や水商売紛いの仕事をさせられることや、
住み込みという形であてがわれた粗末な屋根裏部屋に最初は不満たらたらだった
ルイズだが、今では結構順応して、それなりにまともに生活している。
会ったばかりの時よりもずっと融通が利くようになったな、なんて
ちょっと嬉しくなる一方、俺には少し気になることがあった。
さっき廊下で顔を合わせた時もそうだったけど、少しルイズがよそよそしくなったのだ。
ちょっとしたことで殴ったり蹴ったり、俺の金を使い込んだり、他の女の子を見てるだけで
難癖付けてきたりという表面的な横暴さは全く変わってない。
けれど、もっと深いところで俺に壁を作ってるというか、遠慮しているのを時々感じる。
その原因は……、まぁ、大体検討はつく。俺が惚れ薬を飲んでしまった時のことだ。
あれ以来、ルイズには”マッサージ”も頼まれないし、必要以上に触れることもない。
そのわりには一緒のベッドで寝て、腕枕なんかもしちゃってるわけだけど、
惚れ薬の時の一件は何というか、俺たちの間でタブーみたいになっている。
「(良いことなのか、悪いことなのか……)」
わからない。けど、変に気まずいままでいるよりは、無かったことにしておく方が
マシかもしれない。今はそれどころじゃないほど毎日慌ただしいんだから。
鈍くなった頭の隅でそう結論付けると、傍らにルイズの体温を感じながら、俺は眠りに落ちた。
■2
「上手いこと、貴族の娘っ子を起こさずに出られたじゃねぇか」
「あぁ、おかげさまでね」
夜型生活が続いてるおかげで、こんな時間から出歩くことは珍しくなった午前の日差しの下、
デルフを携えてチクトンネ街を歩く。トリスタニアの中心地だけあって、虚無の曜日でもないのに
大通りは人混みでごった返し、剣と喋ってる通行人がいても大して目立たない。
中央広場に到着し噴水の所に目をやると、待ち合わせをしているらしいたくさんの人の中にも
妙に目立つ大きな杖がまず目に入った。その傍らには、噴水の縁にちょこんと腰掛け、
いつものように黙々と本のページをめくっている小さなマント姿。
「あ、いたいた。おーい、タバサ!」
手を振って駆け寄ると、タバサはすぐに顔を上げ、本を閉じてマントの中にしまい込む。
「わり、待ったか?」
「いいえ。わたしこそ、たまの休日に呼び出したりしてごめんなさい」
聞くと、タバサは僅かに申し訳なさそうな色を見せて答えた。彼女らしからぬ言動に、少し驚く。
「え? まぁ、どうせ休みっていってもやることなんか無いし」
「それなら良かった」
今度は、安心したように表情を和らげるタバサ。他の人に比べたら僅かな変化だけど、
そのいつもよりずっとくだけた様子に、思わずどきっと胸が高鳴る。
「それで、今日はお礼をしてくれるんだっけ?
前にも言ったけど、そんな大した事なんてしてくれなくても構わないぞ?」
「わたしの気持ちの問題もあるから、受け取って欲しい」
念を押すと、タバサは俺の目をじっと見つめてそう返した。他意の感じられない、
純粋に恩返しがしたいのがよくわかる瞳。そこまで言われたら、無下になんてできない。
「そ、そっか。それじゃ、有り難く好意は受け取るけど……、どんなことしてくれるんだ?」
「その前に。お昼はもう済ませた?」
タバサは質問に答えずに、そんなことを聞いてきた。
俺が首を横に振ると、彼女は「丁度良かった」と頷き、街中へと俺を促した。
タバサと共に歩いてやってきたのは、半地下のような所にある酒場の前。
昼間は食事やデザートを出すレストランになっているらしく、メニューの看板が出ている。
他の食事所とは少し毛色が違う所として、メニューとは別に演劇の宣伝ポスターみたいなものが
店先に貼られているのが目についた。タバサはそのポスターを、確認するようにじっと見ている。
「んー? イーヴァルディの……、何だろ。劇場の宣伝か?」
劇のタイトルらしく大きく書かれている文字は、『イーヴァルディ』という部分だけ読めた。
前にタバサから少し文字を教わったおかげだ。
「『イーヴァルディの用心棒』。このお店のステージで、旅の小劇団が公演してる」
なるほど。よく見ると、11時30分から昼の公演、となっているのが読めた。
「評判が良いと聞いた。食事をしながら観られるのだけど……、劇には、興味無い?」
「ううん、面白そうじゃん。入ろうぜ」
答えると、タバサはこくりと頷いた。
連れだって半地下への階段を降りた先は、思ったよりも広くて小綺麗なレストランだった。
フロアの広さは『魅惑の妖精亭』と同じくらい。大きく異なる点として、
小芝居や歌の公演に使えるステージが、各々のテーブルから見える場所にしつらえてある。
「いらっしゃいませ。お二人でしょうか?」
「はい。劇を観たいのだけど、良い席は空いてる?」
落ち着いた様子でウェイターに応じるタバサ。少し早めの時間なせいか、
ステージのすぐ近くにあるテーブルにつくことができた。
メニューを受け取ったタバサはそれを軽く一瞥すると、俺に見えるように差し出す。
「あれから、字の勉強はしてる?」
タバサは向かいに座った俺の方へ軽く身を乗り出し、そんなことを聞いてきた。
「うーん、あんまりやってないかな……」
急に聞かれて、曖昧な返事を返す。実は、ルイズの詩作の手伝いをしてもらった後、
タバサには何度か字の読み方を教えてもらっていた。おかげで今では子供向けの本くらいなら
多少は読めるようになっていたけど、夏休みに入ってからは本を開く機会も無かった。
「続けることが大事なのに。じゃあ、そのメニュー、上から読んでみて」
「ん。えーと、『日替わりランチセット。ユルの曜日……、キノコと何とかのパスタ』」
「『キノコとエピナル草のクリームパスタ』」
軽く家庭教師みたいなことをしてもらいながら、今日の日替わりメニューであった
ホットサンドイッチのセットを二人前注文する。ほどなくして運ばれてきた山盛りのサンドイッチを
二人で囓っているうちに、ステージの上に簡素な書き割りが備え付けられ、灯りがついた。
「お、始まるみたいだ」
一つめのサンドイッチを飲み込んでタバサに言うと、彼女は小さく頷いて半身を舞台へ向ける。
旅装束と長剣を身につけたなかなか男前な役者と、ふりふりのやや子供っぽいドレスを
纏ったお嬢様風の可愛らしい女性。メイド服をかっちり着込んだ色っぽい長身の女性の三人が
舞台に並び、三者三様の恰好で礼をする。
それに合わせて、店内から拍手が響いた。いつの間にか、テーブルのほとんどに
お客さんが座っている。タバサも小さく手を打っているので、俺もそれに習う。
三人の役者さんはいったん舞台袖に引っ込み、『イーヴァルディの用心棒』が始まった。
■3
ロ 口 □
『イーヴァルディの用心棒』は、その名の通り、イーヴァルディの勇者が旅の途中で経験した
小さな冒険譚のひとつという設定のお話だった。
といっても、このお話ではイーヴァルディは狂言回しのような役割であって、
主役はどちらかというとお嬢様とメイドの方。物語の冒頭も、お嬢様の登場から始まる。
とある国のとある地方貴族の家に育ったお嬢様。彼女は名のある貴族の令嬢であるにも
関わらず、魔法がからっきし苦手であった。そのため家族からは疎んじられ、コンプレックスの
裏返しから、すぐに周りに当たり散らす、我が侭で根性曲がりな性格になってしまっていた。
そんな彼女の扱いに困った両親は、娘をさっさと嫁に出してしまおうとする。
会ったこともない男と強制的に結婚させられることを嫌がったお嬢様は、家出を決意する。
家出して、独力で何らかの手柄を立てることで自分の才能を両親に認めさせることで、
無理な婚姻を考え直させようと思ったのである。
お嬢様のそんな暴走に付き合わされたのが、彼女の家で働くメイドの一人。
お嬢様と乳母姉妹であり、幼なじみでもあるそのメイドは、例え家に背くことになっても、
幼なじみであるお嬢様の願いを無下にすることなどできない。
一人で家を出る勇気が無いお嬢様の気持ちに気付いたこともあり、
ほとんど保護者のような役割で、お嬢様の家出の片棒を担がされたのである。
冒頭、どこぞの街道を行くお嬢様とメイドの会話で以上の舞台設定が語られ、本編に入る。
賑やかな街についたお嬢様とメイドの二人だったが、メイドが目を離した間に、
お嬢様は行商人から胡散臭い宝の地図を購入してしまう。
こんなのアテになりませんよと内心で嘆息するメイドを尻目に、お嬢様はもう希代の財宝を
発見した気分。その隠し場所が魔物巣くう山奥の洞窟だと知ると、用心棒が必要だと思い立つ。
そんな折、ガラの悪い男といざこざを起こしてしまったお嬢様に、とある青年が助け船を出す。
大柄なならず者を軽くあしらったその青年こそ、旅の勇者イーヴァルディ。
その名前は隠すイーヴァルディだったが、お嬢様は彼を半ば無理矢理用心棒として雇ってしまう。
元来お人好しなイーヴァルディは、お嬢様の傍若無人っぷりと危なっかしさを放っておけず、
メイドの懇願もあって三人揃って財宝探しの冒険をすることになる。
このお芝居、ここからが面白かった。体裁こそイーヴァルディの冒険物語になっているが、
その実、お嬢様とメイドにイーヴァルディを加えた三人の掛け合いによる、
コメディや寸劇のような思わず吹き出してしまうお笑い要素がメインなのである。
舞台装置は極めて簡素で、小道具すら省略してパントマイムで表現されるシーンも多々あった。
舞台の上に立つのはたった三人の役者さんなのに、その素人目にもわかりやすい演技は
ことによると大がかりな劇場演劇以上に観る者をのめり込ませてくれた。
優しくてお人好しだけれど剣の腕が抜群で、いざというとき頼りになるイーヴァルディに、
まずメイドが惚れ込んでしまう。彼女は事あるごとにイーヴァルディの世話を焼き、
時にはその魅力的な身体まで使ってモーションをかける。
ところが、お嬢様の方もイーヴァルディを憎からず思っていて、メイドが彼にベタベタするのを
気に入らない様子。はっきりした態度には出さないまでも、二人の仲を妨害に走る。
肝心のイーヴァルディといえば、色恋沙汰には全くの鈍感で、二人の気持ちに全く気付かない。
わざとやってるんじゃないかとすら思える絶妙さでメイドの誘惑を煙に巻き、
お嬢様のさりげないアプローチを華麗にスルーする。
話が進むに連れて、お嬢様の暴走が過激になったりメイドの微妙な腹黒さが滲み出てきたり、
テンポの良い展開に引き込まれてこちらも笑ったりニヤけたり大変だった。
一歩間違えれば悪ノリになってしまう寸劇の合間に、自分を認めてもらいたいと
彼女なりに努力しているお嬢様の真剣さや、そのお嬢様の幸せを切に願っているメイドの気持ち。
そして、そんな二人の関係を理解した上で、引き受けた用心棒の仕事を全うし、
見守ってあげようとしているイーヴァルディの優しさなどが少しずつ描写される。
■4
そして、一行の旅が目的の場所に近付くと、彼らの中に一抹の寂しさのような物が生まれ始める。
宝探しを目的とした旅であるのに、三人はこの旅そのものを楽しんでおり、出来ることならば
ずっとこの三人で居続けたいとも思ってしまうのである。
けれど、そんなことは叶わない。三人で暗黙の内に生まれたけじめとして、
一行は旅の終着点として、財宝が眠るとされる洞窟に踏み入る。
ここから先のクライマックスは、それまでのコメディ色とはうって変わって手に汗握る展開だった。
洞窟の中、長年のカンによってイーヴァルディは隠し通路を見つけ出す。
その先には数々の罠が待ちかまえており、これだけ厳重な警戒が手つかずで
残っているということは、財宝は本当に存在するのかもしれないとイーヴァルディは言う。
果たして、財宝を秘めた宝箱は見つかった。しかし、イーヴァルディの言葉に
舞い上がってしまっていたお嬢様は、不用意に宝を手にとってしまい、罠を作動させてしまう。
崩れ落ちる床。何とか三人とも命は取り留めたが、お嬢様とメイドは足に怪我を負ってしまう。
そんな中、洞窟に巣くうオオカミに囲まれる三人。例えイーヴァルディといえど、
無数の敵から動けない二人を守り通すことなど不可能に近い。
そこで、メイドは言う。わたしを置いて、お嬢様を背負って逃げてください。
お嬢様は宝を持ち帰って、両親に自分の力を示して、幸せになってください、と。
それを聞いたお嬢様は、歩くこともままならない足でゆっくりと立ち上がり、こう返す。
わたしは貴族よ。これくらいのオオカミなんて、軽く片付けられるわ、と。
今まで満足に使えたことがない魔法を唱えるべく、杖を振りかざす。
二人の瞳が、イーヴァルディに向けられる。自分を置いて、この子を助けて。
イーヴァルディは何故か満足げに頷くと、大きく息をのんで――。
二人を両の小脇に抱え上げ、オオカミの群れの中へと突っ込んだ。
無茶だ、有り得ない、と当惑する二人を無視して、イーヴァルディは洞窟の外へ向かいただ走る。
得意の剣も使うことができず、襲い来るオオカミを撃退することもできない。
その足に背中に、はオオカミの牙や爪が次々に突き刺さる。
けれども、まさしく勇者の力を発揮したがごとく、イーヴァルディは疾風のように駆け抜けた。
ついに、洞窟を出る。しかしさすがにイーヴァルディも満身創痍、今にも倒れそうな状態。
彼が左に抱えたメイドの喉笛へと、オオカミの一匹が襲いかかる。
避けきれない、絶体絶命の刹那……、オオカミは、突如の烈風にはじき飛ばされた。
お嬢様が、初めて魔法を成功させたのである。イーヴァルディの勇敢という言葉を越えた行動に
心打たれたお嬢様は、自分の幼なじみであり、無二の親友であるメイドの危機に、
ようやくその才能を開花させることができたのだった。
傷を癒し終わり、別れの時がやってきた。手に入れた財宝はさほど貴重なものでは
無かったけれど、お嬢様は財宝よりも大事な物を手に入れることができた。
それは貴族にとって、魔法を使えるようになったことよりも、もっと不可欠なものである。
お嬢様は、自分と旅を共にしてくれた用心棒に、自分の領地で仕えてくれと言いたいのを
胸の奥に飲み込んで堪える。彼もまた、もっと大事な使命を持っていることに気付いていたから。
だからお嬢様は、隣にいる掛け替えのない幼なじみのメイドと共に、
近くを訪れる機会があったら遠慮せずわたしの家に寄りなさい、歓迎するわと笑いかける。
そして笑って手を振り、イーヴァルディは用心棒の契約を終え、再び旅立った。
彼の背中を見送った後、お嬢様とメイドの二人も、自らの領地へと歩き出すのだった。
ロ 口 □
■5
「いやー、面白かった!」
レストランを出て、午後の日差しを仰ぎながら一言。笑いありハラハラドキドキあり、
ちょっとしんみりありの、非常に満足できるお芝居だった。つい幕間には飲み物や食べ物の
注文もしすぎてしまったし、劇の終了後にはチップを弾んだ上、役者さんに握手までしてもらった。
「こんな穴場みたいな場所での劇、よく知ってたな、タバサ」
笑って後ろのタバサを振り向くと、タバサも心なしか満足げな表情をしていた。
「評判を耳にしてたから。それに、あなたはこういうのを好みそうだと思った」
「ベストチョイスだぜタバサ。高尚すぎたり小難しいかたったりする話より、
こう、気分が良くなれる話の方が俺に合ってるよ、ありがとな。タバサはどうだった?」
「わたしも、楽しめた」
俺の好みまで考えて、この劇を紹介してくれたのか。
嬉しくなって、思わずタバサの頭を撫でてしまう。こういう形での”お礼”なら大歓迎だ。
「あぁ、確かに面白い劇だったぜ。色んな意味でな」
タバサには聞こえないくらいの小声で背中のデルフがそう言って、含み笑いをする。
なんか妙に機嫌が良いみたいだけど、色んな意味でってどういうことだろ。
「あの小劇団は、良く知られている物語を題材に、娯楽として楽しめるようにアレンジして
演劇にするのをスタイルにしている。頭の固い貴族には受けにくいけれど、
演技も演出も工夫されているし、根強いファンはいっぱいいるみたい」
なるほど、だからあんな目立たない場所で公演してても、拍手は盛大だったのか。
「そっか。良いもの紹介してくれてサンキュな。また機会があったら、一緒に観に来ようぜ」
タバサの小さな頭を、もう一度なでなで。なんとなく、可愛い妹がお兄ちゃんのために
プレゼントを工夫してくれたみたいな感じで、妙に嬉しくなってしまう。
「……また、一緒に?」
「ああ。駄目か?」
聞くと、タバサはふるふる首を横に振った。うん、と満足して俺は頷く。
「タバサの恩返し、嬉しかったぜ。せっかくだし、まだどこかで遊んでいくか?」
通りを並んで歩きながら、タバサにそう言うと、
「まだ、お礼は済んでない。これからが本番」
そんなことを言い返された。
「これからが、って……」
あんまり色んな事してもらっちゃっても、逆にこっちの方が申し訳ないんだけど。
そう思っていると、タバサは俺のパーカーの袖をくいっと軽く引っ張った。
「あそこ」と指した先は、大きな店構えの本屋。タバサに連れられて、そこに入る。
本棚の間をするすると歩くタバサについていくと、彼女は棚から一冊の本を取り出した。
タイトルは……、俺でも読める。『イーヴァルディの勇者 物語集1巻』。
「これ、今のあなたなら大体読めると思う。わからないところはルイズに聞いたりして、
字の勉強に使って。さっき観た、『イーヴァルディの用心棒』の元になった話も入ってる」
そう言って、タバサはその本をカウンターに持って行こうする。
「えっと、いいのか? このせか……、ここの本って、高いんじゃないのか?」
「気兼ねするなら、わたしが買って、あなたに貸すっていう形でもいい」
あっさり言い切って、タバサはお金を払ってしまう。そう言われたら無下に
断るわけにもいかない。ありがたく好意を受け取ることにした。
「本をプレゼントしてくれるのが本番か? ありがとな」
「いいえ。まだある」
「ええ!? さすがに、お礼のしすぎじゃないか?」
「次が本命」
本屋を出た後、タバサはまだ俺を案内する予定があるらしかった。
恐縮してしまいつつも、俺を連れまわすタバサは何だか気持ちが弾んでいる様子で、
こっちもウキウキした気分になってくる。タバサとこんな風に街中を出歩くなんて、
少し前までは想像もしなかったことだ。
■6
足取りも軽くトリステインの城下を通り抜け、ブルドンネ街の市場を過ぎる。
いつの間にか裏路地の方に入っていき、なんとなく既視感のある風景だなと思っていると、
一軒の武器屋の前でタバサは歩みを止めた。そっか、同じ店ではないけど、ここって
ルイズがデルフを買ってくれた場所の近くだ。
タバサは俺がついてきているのを確認すると、武器屋のドアを開く。
「いらっしゃい。……あぁ、お嬢ちゃんか」
「頼んでおいた物は出来てる?」
中にいたのは、デルフを売ってた店の店主よりも年配だけれど、落ち着いた雰囲気の
気のよさそうな老人だった。タバサの顔を見ると、白髭を蓄えた愛嬌のある顔を綻ばせる。
「何か頼んでたのか?」
「簡単な加工だよ。使うのはそこの彼かい?」
俺がタバサに聞くと、店主の爺さんが代わりに答えた。外見に似合わない
しっかりした足取りで戸棚に向かうと、そこに置いてあった革製の品物を手に取る。
「少し、上着を捲って」
タバサは俺にそう言ってきた。店主のお爺さんも同意見な様子で俺を見ているので、
言われた通りにしてみる。お爺さんは俺の腰……、いや、ジーンズのベルトに軽く触れて、
感心したように頷いた。
「うむ、言われたとおりだね。ちょっと手直しするだえけで使えるよ」
「タバサ、どういうこと?」
薄々検討はついていたけど、一応質問する。爺さんが持っているのは、
革で出来たホルスターだった。ホルスターといっても、拳銃を入れるものではなく。
「ナイフを贈ろうと思って」
そう、小型の刃物を腰に下げておくためのものだった。タバサは商品の陳列棚から、
あらかじめ目をつけたおいたらしい一本のナイフをとってきて、俺に手渡しする。
「ナイフって、そりゃいくらなんでも高価すぎないか? 悪いよ」
それを受け取った瞬間、左手のルーンが反応した。20センチ程の刃は肉厚でありながら
鋭く研ぎ澄まされており、作業にも格闘戦にも十二分な性能を発揮することが
持っただけで感じ取れる。このナイフ、良い物だ。飾りや玩具紛いの代物じゃない。
「……あなたが、身を守れるために」
乗り気じゃない俺の目をじっと見て、タバサはそう言った。
「『月の涙』の時も、この前わたし達があなたのお店に行った時も。
あなたが武器をもう一つ常備していれば、状況がもっと楽になっていた。
今後も、剣が使えない状況はあるはず。お守りだと思っても良い、受け取って」
その言葉に、今までの『お礼』とは明らかに異なる色を感じた。今までにタバサが
してくれたのは、恩返しとして俺を楽しませてくれるためのものであったけど、
今度のは違う。俺に必要な物を、俺に欠けている物を考えて補ってくれる行為。
俺がタバサを守って、助けたことに対するお礼であるのなら、これが本当の意味での
”お返し”ということなのだろうか。
「いいじゃねぇか、メイジの娘っ子の言うことももっともだぜ。有り難く貰っておきな」
「あ、ああ……」
デルフの言葉につい頷いてしまった所で、ホルスターの手直しを終えた店主が、
俺のジーンズのベルトにそれを備え付けてくれる。ここにナイフをしまっておけば、
パーカーの裾が長いおかげで、いわゆる隠し武器のように携帯できるというわけだ。
「ん、よく見たらその剣、春先まで赤鼻の店に並んでた剣か。
てことは、この彼がその『使い手』って事かい」
「おーよ。良く覚えてくれてたね爺さん。こいつが俺の相棒さ」
喋ったのを聞いて気付いたのか、店主の爺さんは目を丸くする。
そういえば、デルフを買った店の店長、赤い鼻してたっけ。デルフの奴、
他の店の店長にまで『使い手』以外には使わせないみたいなこと言ってたのか。
「ふむ……」
「な、何ですか?」
今度は俺の顔や体を見回す爺さん。俺の腰にホルスターがしっかり備え付けられると、
「いや。大事に使ってやんな。その剣も、このナイフも」
満足げに息をつき、ポン、と俺の肩を叩いた。
■7
その後も、タバサと一緒にトリスタニアの街中を歩き回った。
さきほどタバサが言ったとおり、俺へのお礼の本命はナイフを贈ってくれることだったらしく、
特にこれといった目的地は定めないまま、市場を見て回ったり露天を冷やかしたり、
ルイズや妖精亭の人へのおみやげを買ったりしているうちに、街は夕暮れに染まっていった。
一日、タバサと一緒に色んな所をまわって、彼女は今まで思っていたよりも
ずっと感情豊かな子だということに気付いた。
表情や仕草の微妙な変化を悟れるようになったというのもある。けれど、いつのまにか。
俺とタバサが知り合ったばかりの頃よりも、彼女は自分の気持ちを、表に出して示して
くれるように変わってきている気がする。
タバサ自身に心境の変化があったのか、それとも俺に多少はうち解けてくれたのか。
どちらにせよ、嬉しいと思う。だって、今のタバサと一緒に出歩いていて、楽しいって
思えるのだから。もっと彼女の色んな姿を見てみたいって思うのだから。
けど、お昼に見た『イーヴァルディの用心棒』の劇じゃないが、楽しい時間にも終わりは来る。
夜の帳が降りた頃、俺たちの足は自然と街の中心地へ向かっていた。
二人で待ち合わせた、チクトンネ街の中央広場でお別れする、ということだろうか。
噴水前に着く。日本みたいに街灯が充実しているわけではない薄暗い場所だったけど、
そこでは昼間と同様、待ち合わせをしているらしい人がちらほら見られた。
待ち人と会えたらしい男女の二人連れが、腕を組んで身を寄せ合いながら広場を出て行く。
昼と違うのは、この時間に待ち合わせた後は、男女の……、大人の時間ってことらしい。
それを意識した途端に罪悪感のようなものが湧き上がってきて、ここにタバサと共に
居ることが、とても後ろめたい、禁忌を犯している気分になってくる。
「えっと……、タバサ」
名残惜しいと思っている自分がいることにも気付きながら、意を決して口を開く。
ここでさよならしよう、と続けようと思った矢先、タバサが俺の袖をきゅっと掴んだ。
いつのまにか俺と一緒にいる時の、タバサの癖みたいになってしまった仕草だ。
「……夕食も、ご馳走する。わたしの泊まる宿の一階が、レストランになってるから」
タバサらしくない、今思いついたことをすぐ言葉にしたような提案だった。
けど、月明かりにきらめく青い瞳に見つめられて、断ることなんてできなかった。
気付けば、俺とタバサの並んで歩く距離は、ともすれば肩が触れ合いそう。
周りにいる、人目をはばからないカップルと同じとは言わないまでも、
今日の昼間に会ったばかりの時よりも、明らかにずっと近くなっていた。
繁華街を通り、タバサが予約しているらしい宿に着く。スカロン店長には申し訳ないけど
『魅惑の妖精亭』よりもずっと高級感のある建物で、一階の店も酒場ではなく、
貴族やお金持ちがディナーを楽しむレストランといった店構えだった。
上の宿に部屋をとっていたタバサは、名乗るとすぐに店奥の席に案内された。
出された料理は学院の夕食と同じくらい豪華なもので、久しぶりの貴族向けの食事に
タバサと一緒に舌鼓を打つ(でも、マルトー親父さんの料理の方が美味かったかな)。
食後に出された甘口のワインを少しずつ飲んでいると、店の外に雨音が聞こえてきた。
「雨」
「ああ、そうだな」
何か白々しいように思えるやりとりの後、雨音はすぐに大きくなった。
水気を含んだ慌てた足音や軒先を打つ太鼓のような響きが聞こえてきて、
土砂降りであることが容易に想像できる。どうしよう、もっと帰りにくくなっちゃったな。
タバサの様子を伺うと、目があった。微かに上気した頬で、俺の方をじっと見ている。
アルコールのせい……、だよな? 俺の顔まで熱くなってるのも。
何だか気まずくなって、手に持っていたグラスのワインを一気にあける。
ふう、と一息つくと、タバサのグラスも空になっていた。
■8
「……部屋に、来る?」
次いでタバサが言ってきたことに、俺は危うくむせそうになった。
とんでもないことをさらりと言ったタバサは、いつもと同じ、澄んだ青い瞳で俺をじっと見ている。
何だ? また『月の涙』の時みたいな冗談か? どう反応していいのか俺が困っていると、
「雨が止むまで。……それに、話したいことがある」
タバサはそう言い、ちらりと周りのテーブルのお客さんを一瞥した。
人目があると話しにくいことなのか。タバサの様子は、いたって真剣な雰囲気に見える。
「……ん。お邪魔するよ」
俺が想像してしまったような、やましい意図は無さそうだ。
俺が返答すると、タバサは小さく頷いて席を立った。
レストランの上階、タバサのとった部屋に案内される。タバサが軽く杖を振ると、
妖精亭の屋根裏部屋とは比べるのも失礼なくらい立派な部屋が灯りに照らされた。
椅子をすすめられ、そこに座り込むと、タバサは立ったまま口を開いた。
「トリステインが、アルビオンへの本格的な侵攻作戦を進めてるのは知ってる?」
いきなり本題、といった口調。一瞬呆気にとられてしまった後、少し思案する。
「……街の人とかは、そんな事を言ってるけど。ルイズも否定はしてない」
風評を集める仕事のために、わざわざ酒場で仕事をしているくらいだ。
ある程度の世相くらいは耳に入ってくる。けれど、
「でも、なんでタバサが俺にそんなこと?」
「あなたの主人……、ルイズは、戦争に従軍するつもりでいるらしい。
そして、王宮も彼女の力を想定に入れた上で計画を進めている」
「え……?」
今度こそ、驚かされた。なぜ彼女がそんなことを知ってるんだろう、いや、それ以前に。
「な、なんでだよ。だって、ルイズは」
「彼女がただの『ゼロのルイズ』じゃないことくらいわかる。
もちろん、あなたがただの使い魔じゃないことも」
う……、相手は他ならぬ、あの聡いタバサだった。隠し通せると思う方が甘かったのかも。
「ルイズやあなたが、並みのメイジを凌駕する力を持っているのは理解してる。
これまでもその力で、何度も成果を挙げ、危機を乗り越えたこともわかる」
タバサはそこまで言って、小さく息をつき。
「……けれど、戦争なら、死ぬかもしれない」
静かなその台詞の後、雨音だけが俺たちのまわりを支配した。
ゆらめくランプの灯りの向こうで、タバサがじっと俺を見ている。いつもの、無表情で。
いや、違う。今ならわかる。タバサの姿から、焦りや、不安や、憤りといった感情が
微かに滲み出ているのが見て取れる。まるで、『月の涙』の時のように。
「――だ、大丈夫だよ。そう簡単に死んだりしない」
「なぜ?」
努めて明るい調子でやっと口を開いた俺に対し、タバサは責めるような色でそう返した。
「なぜ、って……」
「死にたくないと思っても、死ぬわけがないと思っても、死ぬのが戦争。いいえ、戦いは全てそう。
今まで死の危機を何度も乗り越えられた。だから次も大丈夫、なんて通用しない。
だからこそ次には死ぬかもしれない」
「……死は、思っているよりもずっと身近にある」
そう言ったタバサの表情は、いつのまにか明確な悲壮の色に歪んでいた。
今まで、なるべく考えないようにしていたことだ。俺はこの世界に来てから、
何度も『危うく死にそうな目』にあった。一歩間違えば簡単に死んでいた。
そして、同じような危機に直面したら、その時も助かる保証なんてどこにもない。
今のタバサの言葉は、そんな俺を心配しているからというだけで言えるものじゃない。
俺だけに対して放たれた台詞じゃない。タバサは、実際に知っている。
死が身近にあることを。今自分が生きていられることですら、奇跡に近いということを。
そして、彼女もまた、戦争と同等以上に危険な目に、今後も遭うことがわかっている。
だから、あえて今、俺にこんなことを言っているんだ。
「あなたは、わたしを守ってくれた。けれど、わたしがあなたを守ってあげることはできない」
タバサは遠慮がちに、こちらへ歩いてきた。誘われるように、俺は立ち上がってしまう。
「……それでも、あなたに死んでほしくない」
タバサは瞳を伏せ、絞り出すようにそう言った。
理屈も何もない、そのために協力できるわけでもない、
それを言ったからといって、何かが変わるわけでもない、ただの希望。
けど、今の瞬間わかった。タバサは、その一言が言いたいために、
わざわざ俺を呼び出して、こんな時間、二人きりになるまで連れまわしたんだ。
言葉にするのは簡単だけど、ことタバサが俺に伝えるには、重い意味がある気持ち。
胸の奥から、言葉じゃ言い表せないものがこみ上げてくる。
そんな気持ちを伝えてくれた彼女に、何かを返してやりたくなる。
けど、何も出来ない。今、何をしたって、彼女へのお返しになんかならない。
その気持ちに応えるなら、『俺が死なない』以外の応え方なんて存在しないんだから。
「……タバサ」
俺はそう言って、目の前のタバサの手をとった。小さい、本当に小さい子供みたいな
細くて白い手が、俺の手に包まれて温もりを伝えてくる。
「俺も、タバサとまた一緒に芝居を観に行ったりしたい。一緒に食事もしたい。
本を紹介してもらったり、字を教えてもらったり、街を見て回ったりしたい」
タバサの方も、俺の手をきゅっと掴んできた。
「だからタバサも、な?」
明確な言葉は使わず、最後にそう言って、俺はタバサに笑いかけた。
タバサは表情をふっと和らげて、力強く頷いて返してくれた。
■9
∞ ∞ ∞
「きゅい! どうしてあっさり帰しちゃったの! 勿体ないのね、理解できないのね!
お泊まりは? キセージジツは? 一夜のアヤマチはー? シルフィ、期待してたのに〜!」
「自分でも理解できてない言葉を使わないで」
翌朝、トリスタニアを発ち、学院へと至る道すがら。
シルフィがわたしを背に乗せながら、好き勝手なことをわめき立てる。
彼女の言うとおり、深夜になる前に、雨が小降りになったのを見計らって
彼は下宿している店へと帰っていった。
「だってだーって! 聞き耳立ててたらおねえさま、せっかく二人きりになったのに
やれ戦争だのやれ死ぬだの、くっらーい事ばっかりのたまって! あれじゃサイトだって
ドン引きなのね、せっかく盛り上がってたかもしれない気分も台無しなの!」
「別に何も盛り上がってない」
「だったらおねえさまが盛り上げるのです! シルフィは聞きました、サイトみたいな子は
義理堅いから、一度やることやっちゃえばちゃんと責任とってくれるって!」
「誰から聞いたの」
「キュルケなのね。ゼロでピンクの子と話してた。ところで”やること”って何なの?」
どこから突っ込んでいいのかわからない。わたしは小さくため息をつき、
開いた本へと視線を落とす。けれど、中身はなかなか頭に入ってこない。
「でも、サイトの方からまたデートしようって言わせたのは素晴らしいのね。
次はこんな煮え切らない結果にしちゃ駄目よ、おねえさま」
デート。その言葉に、ぴくりと肩が震えた。わたしはそんなつもりで呼び出したわけじゃないし、
わたしも彼もそんな言葉は一度も使わなかった。 けど、彼はどう思っているのだろう。
昨日のこと、そして、また一緒に出かけようって行ってくれたこと。
袖が触れ合うような距離で歩いたこと。何でもないお店を巡るだけでも、彼と一緒だと
感じることがまったく違ったこと。彼が笑顔を見せてくれるのが嬉しかったこと。
もし、もし。彼の方も、わたしと同じように感じてくれたなら……、建前はどうあれ、
そこに生まれた気持ちが、『デート』って言われているものなんじゃないだろうか。
目を閉じ、小さく首を振る。そんなの、どうあっても関係ない。少なくとも昨日の時点で
わたしがしたかったのは”お礼”をすること。彼を守ってくれるかもしれない、武器を贈ること。
それだけのはず。それ以上の意味なんて求めない。
……でも、その後の。宿の部屋に呼んで、あんなことを言ったのは。
あの言葉には、実質的には何の意味もない。サイトの助けになるわけでもないし、
むしろ不安を煽るだけの結果になるかもしれなかった。
それでも言わずにいられなかったのは……、わたしだ。わたし自身のため。
わたしの気持ちに、整理をつけるためだった。彼のためだなんていえない。
「いいこと? おねえさま。夏休み中にはもう無理かもしれないけど、次に会ったら
もっと積極的にアプローチするのね。シルフィの見立てでは、あと一押しで落ちるわ!」
「そんなことしない」
「なんでなのね!?」
一言で切り捨てたわたしの言葉に、シルフィが驚愕する。
「ねぇねぇ! なんでなの! サイトが戦争に行くっていっても、まだ時間あるでしょ?
おねえさま、サイトのこと好きって認めたんじゃないの? 違うの?」
「……どちらでも、同じこと」
「?? シルフィにはわかんないのねー! きゅい!」
空中でじたばた暴れ始めたシルフィを放っておいて、今は遥か後ろになった
トリステインの城下町を振り返る。
わたしの気持ちは、関係ない。わたしがするべきことを優先するだけ。
もしも、仮に。全てが終わって、全てが解決したときに。
それでも、彼が誰の物にもなっていなかったなら、もしかしたら……。
小さく、自嘲の笑みが浮かぶのがわかった。そんな、有り得ない可能性を考えてどうするの。
ちょっとした寂しさを胸の奥に押し込んで、わたしは『雪風のタバサ』に戻る。
燦々と照りつける、強すぎるくらいの真夏の日差しが、なぜか心地よく感じられた。
つづく
[[前の回>X00-27]] [[一覧に戻る>Soft-M]]
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: