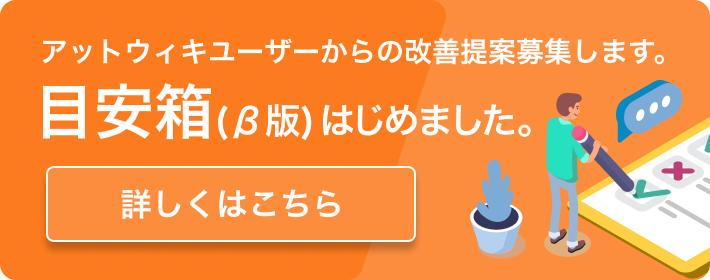365 名前: Please Mr.Lostman [sage] 投稿日: 2007/09/23(日) 23:21:55 ID:JoDKp6D9
青年は、馬に乗って必死に街道を駆けていた。元々急ぐ旅でもなかったし、愛馬の体を傷つけたく ないという思いもあったので、鞭や拍車の類は一切身につけていない。それでも全速力で走ってくれ る辺り、馬にも危険な状況だということが分かっているのかもしれない。 (婆ちゃん、この辺りなら絶対安全だって言ってたのに!) 静かな自信に満ちた表情で断言していた祖母の顔を恨めしく思い出しながら、青年はちらりと後方 を振り返る。遠くでもうもうと土煙が立ち込め、その向こうからは馬蹄の音が無数に聞こえてきて いる。向こうも諦めるつもりはないらしい。 (無事に逃げ切れるだろうか) 青年は不安だった。相手は大人数だし、全員馬に乗っている。脚力は同程度のようだから、今のと ころは差は縮まらないが、しつこく追い回されては持久力の方に限界が来る。 どうしたものかと思案に暮れていたとき、青年はふと、前方を見慣れない鳥が飛んでいるのに気がついた。 (フクロウ、か?) まだ時刻は昼間である。夜行性のフクロウが飛んでいるというのはどうも腑に落ちない。奇妙に 思ったとき、突然フクロウが飛びながらこちらを振り向いた。 「オイデ、オイデ」 しかも喋った。ギョッと目を見張る青年に対して、フクロウは悠々と翼を広げたまま、街道脇の森 に向かって飛んでいく。見ると、そこに馬でも何とか通れそうな程度の獣道が延びていた。 (どうする) 青年は判断に迷う。森は奥が見えないぐらいに薄暗く、フクロウがその奥に誘うというのは、まる で魔女に手招きされているような状況である。 だが、迷いは一瞬だった。青年は手綱を絞り、馬を森の獣道に入らせる。 (どうせ、このまま逃げていてもいずれは力尽きてしまうだろう。それなら、いっそ、あの鳥の主に 賭けてみるしかない) 青年がそう決心できたのは、何故か喋るフクロウというもの自体に大して警戒心や不審感を抱かな かったというのも大きい。 「昔、お友達の家に行ったとき、飛んできたフクロウが喋り出してね。ビックリして気を失っちゃったのよ」 そんな風に、祖母が笑って話していたからかもしれない。 青年はフクロウの背を追って、ひたすら馬を駆けさせる。幸い、この獣道に入ってから、背後の蹄 鉄の音は遠ざかりつつあった。先導がいるこちらと違い、向こうは道なき森の中を走るのと同じだ。 速度が落ちるのは当たり前だった。 (これなら、逃げ切れるかもしれない) 青年の胸に安堵が広がる。獣道はじょじょに上に向かって傾斜してきて、登り道になった。その内 森から抜け出すと、そこは小高い丘の中腹だった。フクロウは、丘の上に向かって飛んでいく。青年 も後を追った。 小高い丘を登りきると、そこに一軒の家が建っていた。小さな柵に囲まれた、小さな家である。そ の庭先のテーブルの前に、一人の老婦人が腰掛けている。フクロウは老婦人のそばに飛んでいくと、 空気に溶けるように消えてしまった。 (やっぱり、魔女なのか) 青年は再び緊張する。老婦人は、こちらを見て穏やかに微笑んだ。 「こんにちは。旅のお方かしら」 その皺だらけの顔を見ると、全身からすーっと緊張が消えていった。その老婦人は見たところ青年 の祖母と同年代ぐらいだったので、親近感が沸いたのかもしれない。青年はほとんど無警戒に馬を家 の敷地に乗り入れさせ、その背から下りた。 「お騒がせしてしまって申し訳ありません。あのフクロウは、あなたが?」 「ええ。なんだか下が騒がしかったから、幻を飛ばしたのよ。誰かに追われているようね」 老婦人はティーポットを傾けてカップに紅茶を注ぎながら、ゆったりした口調で言った。 「ご存知なら、すぐに逃げてください。今は森を抜け出すのに手間取っているでしょうが、連中はす ぐにここに登ってきますよ」 「あら、向こうはずいぶんとご執心なのね」 「あ、いえ。もしかしたらもう諦めているかもしれませんが、念には念をいれませんと」 青年を追ってきている男たちは、この近辺を縄張りにする盗賊らしかった。先程のような森が街道 脇に広がっているため、潜伏するには好都合なのだろう。青年も、馬に乗って街道を進んでいる途中、 突然前後左右から襲い掛かられたのだ。馬が自分の判断で走り出してくれていなければ、今頃どう なっていたことか。 366 名前: Please Mr.Lostman [sage] 投稿日: 2007/09/23(日) 23:22:41 ID:JoDKp6D9
「とにかく、早く逃げてください。足腰のお加減が悪いのでしたら、僕の馬の背にお乗せしますので」 青年が申し出ると、老婦人は少し首を傾げた。 「それはありがたいのだけれど、もうその子は限界なんじゃないかしら」 青年は、はっとして馬の様子を見る。確かに息は絶え絶えだし、もう疲労の極みにあるようだった。 だがそれでも、「まだ行ける」と言うように、気丈に一声鳴いてみせる。愛馬に対する愛おしさが胸 にあふれ、青年は自然とその頬を撫でてやっていた。 「好かれているのね、あなた。見た目どおり、いい人みたいだわ」 「いえ。愛馬をこんな目に合わせている、とんでもない飼い主です」 せめてこいつだけでも逃がしてやろうと、青年は手綱を放して、どこかへ行くよう愛馬を促す。だ が、馬はその場を動かず、じっとこちらを見つめていた。 「あなたと離れたくないみたいね。ここで死んでもいいから一緒にいる、という気持ちみたいよ」 老婦人はふと、遠くを見るように目を細めた。 「わたしにも昔、そんな人がいたのだけれどね」 そのとき、丘の下の方から無数の馬蹄の音が響いてきた。はっとして振り返ると、ずっと向こうか ら馬に乗った集団が丘を駆け上ってくるのが見える。彼らは、こちらが身を隠すよりも早く、家の前 に到着した。 「おうおう、ずいぶんと逃げ回ってくれたもんじゃねえか、ええ」 先頭に立った男が、馬上からこちらを睨みつけてきた。 「だが、それもここまでよ。抵抗せずに大人しくするなら、せめて苦しまないように殺して、と」 そこで初めて老婦人に気付いたらしく、男は彼女を見て眉根を寄せた。 「なんだ、こんなとこに一人で住んでいやがるとは、妙なババアだな。おい婆さん、どうせ老い先短 い退屈な人生だろうよ。せっかくだからまとめて殺して、テメエのわずかな財産は俺らが有意義に 使ってやるから有難く思え。まあ、こんな枯れ木みてえなババアの財産なんか、酒の一杯にもな りゃしねえだろうがな」 男たちが高笑いを響かせた。 青年は、どうにかしてこの親切な老婦人だけでも逃がせないものかと思案する。 そのとき、老婦人が青年の背後で盛大にため息を吐いた。 「やれやれ。これでも三十年ぐらい前までは引く手数多だったんだけどねえ。もうそんな目じゃ見られない、か」 どことなく寂しげに呟きながら、老婦人はテーブルに両肘をついて、鋭い目つきで盗賊たちを見据えた。 「警告してあげるわ」 「なに」 男が高笑いを止めて、怪訝そうに老婦人を見る。彼女は淡々とした口調で諭すように言った。 「今あなたが枯れ木と呼ばわったこのババアはね、自尊心のせいで愛しい人とも一緒になれなかった ような、馬鹿みたいに気位の高い人間なの」 「だからなんだ」 「要するにね」 老婦人は、枯れ木のような細い腕を、テーブルの上に置いてあった木の棒に伸ばした。 「わたしがまだギリギリのところで怒りを抑えている間に、とっとと尻尾巻いて逃げ出しなさいって ことよ。その豚より醜い顔と野良犬より薄汚い体を引き摺って、今すぐわたしの前から消え去りな さい。さもないと」 木の棒の先端を男たちに向けながら、老婦人は皺だらけの顔に皮肉げな笑みを浮かべる。 盗賊たちは今や完全に笑いを納め、殺気だった気配を発しながら各々の武器を構えていた。先頭の 男が、顔を真っ赤にしながら怒鳴った。 「さもないとどうするってんだ、ええ、このババアが!」 367 名前: Please Mr.Lostman [sage] 投稿日: 2007/09/23(日) 23:24:05 ID:JoDKp6D9
盗賊たちが、一斉に馬を走らせようとする。それと同時に、老婦人が短く何かを呟いて、軽く杖を振るった。 その途端、突如としていくつもの爆音が重なり合って轟いた。見ると、男たちが振り上げた武器が、 何の前触れもなく爆発四散し、周囲に金属の破片を撒き散らしていた。その破片が男たちと男たちの 馬に突き刺さり、周囲が悲鳴で満たされる。 そんな凄惨な光景を見て、老婦人はにっこりと笑った。 「さもないと、次は体が弾けて、今の外見以上に見苦しい死に様を晒すことになるわよ」 そうすることに躊躇はないとでも言いたげに、老婦人はこれ見よがしに木の棒を回してみせる。盗 賊たちの中から悲鳴が上がった。 「このババア、メイジだぞ!」 「逃げろ、燃やされちまうぞ!」 口々に叫びながら、男たちは無我夢中で逃げ去った。 後には、すまし顔で紅茶を啜る老婦人と、今の顛末をただ呆然と見守ることしか出来なかった青年、 そして疲れたようにその場に座り伏せる彼の愛馬だけが残された。 「失礼な連中ね」 老婦人が不満げに呟いたので、青年はようやく正気に戻った。何をどう言ったらいいものかと迷う 彼を、老婦人は軽く手招きした。 「こちらへどうぞ。せっかくだから、この枯れ木のようなババアの茶飲み話に付き合ってくださいな」 老婦人が悪戯っぽく言う。その表情を見ていると、先程の彼女に感じた恐怖心が自然と薄れていくようだった。 結局、青年は愛馬を庭先の木につなぎ、老婦人の茶飲み話に付き合うことになった。
桶を借りて水を注ぎ、馬の前に置いてやってから、青年は老婦人の向かい側に腰掛けた。 「ずいぶんと大切にしているのね」 夢中で水を飲んでいる馬を見つめて、老婦人が微笑む。何となく照れくさくなって、青年は頭をかいた。 「祖母の言いつけで、動物は大切に扱うようにしているんですよ。祖母はすごく動物好きでしてね。 特に犬が大好きで、我が家には10匹や20匹では足りないほどの犬が」 老婦人の暖かみのある雰囲気に、自然とそんなことを話してしまう。そのときふと、彼は家の扉に、 一本の剣が飾ってあるのに気がついた。鞘も柄も、ずいぶんと古びている大きな剣である。 「あれは何ですか」 「ああ、あの剣ね」 老婦人は家の方を見て目を細める。その瞳から、隠しきれない愛情が滲み出していた。 「あれはね、ある人と交わした、約束の証よ」 「約束、というと」 「必ずまた戻ってくるっていう、約束」 老婦人はそう言って目を閉じる。 約束の証に剣を置いていくということは、相手は剣士だったのだろうか。しかし、先程魔法を使っ たのを見る限り、老婦人はメイジのはずだった。ということはおそらく貴族階級の出身のはずである。 (それで相手が剣士っていうのは、どうも不思議だな。いや、そもそも、そんな人が、どうしてこん なところに一人で住んでいるんだろう) いろいろと興味が沸いてきたが、不躾に尋ねるのは躊躇われる。そのとき、老婦人がふと呟いた。 「犬、ね」 「え、なんですか」 「ああいえ、さっき、あなたのお婆さまが犬を大切にされていると仰ってたでしょう」 「ええ、そうですが」 犬を妙な名前で呼ばわる祖母の姿を思い出し、青年は頷く。 「わたしのそばにも昔、そんな感じの人がいたのよ」 話の流れからするに、多分その「犬のような人」というのが、剣の持ち主なのだろう。頭の中で素 早く情報を整理しながら、青年は尋ねた。 「犬のような人、と言うと、召使か何かですか」 もしもこの推測が当たっていれば、老婦人は昔道ならぬ恋をしたということになる。だが、彼女は 首を横に振った。 「いいえ。ある意味、召使よりも位が低かったわ。だから、わたしもずいぶんひどい扱いをしたものだけど」 老婦人は懐かしむように微笑んだ。 「それでもその人は、わたしのことを一生懸命守ってくれたし、愛してもくれた。わたしの方も、 段々彼に心を惹かれていったわ」 「へえ。でも、今はご一緒ではないようですが」 話したくないことかもしれないと思いつつ、どうしても興味が抑えきれなかった。老婦人はあっさりと頷いた。 368 名前: Please Mr.Lostman [sage] 投稿日: 2007/09/23(日) 23:24:50 ID:JoDKp6D9
「ええ。いろいろあって、その人とは一緒にはなれなかったわ。彼には帰るべきところがあったから」 「帰るべきところ、ですか」 「ええ」 その場所を見つめるように、老婦人は空に向かって頭を傾ける。 「とても、遠いところよ。帰るのも、こちらに戻るのも大変なぐらいに」 「でも、お二人は愛し合っておられたんでしょう」 「そうね。だから、わたしが望めば引き留めることも出来たのかもしれないけど、そうはしなかった。 変に高いプライドのおかげかしら、どんな理由があったとしても、間違ってると分かっていること は出来なかったのよ。彼はそこにいろいろなものを残してきていたはずだから、一度は必ず帰るべ きだったのよ」 老婦人はティーカップに両手を添えて、静かに目を閉じた。 「でもわたし、彼を帰したのを後悔したことは、今まで一度もないわ。正しいことをしたんだし、それに」 老婦人は、いい夢でも見ているかのように、幸せそうに微笑んだ。 「彼はね、約束してくれたのよ」 「何をですか」 「自分なりにけじめをつけたら、必ずわたしのところに戻ってきてくれるって」 紅茶を一口啜り、老婦人はため息を吐くように言った。 「もう、四十年以上も昔の話になるわね」 「じゃあもしかして、あなたは、今でもその人のことを待ち続けているんですか」 その気の遠くなるような歳月を思いながら男が問いかけると、老婦人ははにかむように頷いた。 「ええ、そうよ。彼と別れてから、わたしはずっと一人で待ち続けた。恋敵だった友達が他に相手を 見つけても、あの人はもう帰ってこないから忘れろと説得されても、そんな男のことは忘れてやる と、誰かに愛を囁かれても。わたしはただひたすら、彼だけを待ち続けた」 老婦人は、自分の細い腕を見つめて、少しだけ悲しそうな顔をした。 「そうしている内に、こんな痩せた枯れ木のような老婆になってしまった。今はもう、誰もわたしの ことなど覚えてはいないでしょうね。それでもまだ、わたしは彼を待っているの。まだ、あの約束 を信じているのよ」 そう言って微笑む老婦人の顔は、今は確かに皺だらけだが、昔は相当な美貌を持っていたであろう ことを窺わせる。 青年は何も言えなくなってしまった。彼女の人生は、他人の目で見れば明らかに不幸なものだろう。 これほどの美貌や貴族階級という地位があれば、当然つかめるはずだった人間としての幸せを顧みる ことすらせず、ただただいつ帰ってくるか分からない思い人を待ち続けた女。そうしている内に誰か らも忘れ去られ、錆びついてしまった約束の証の剣だけを抱えて、こんな寂しい場所に一人佇む、痩 せた枯れ木。 「あら、ごめんなさいね」 老婦人は茶目っ気のある笑みを浮かべた。 「あなたが真剣に聞いてくれるものだから、ついついこんな楽しくない話をしちゃったわ」 「いえ、楽しくないだなんて」 「そんなことよりも、外のことを聞かせていただけないかしら。こんなところにいると、世の中の流 れに疎くなってしまってね」 「外のこと、ですか。そうですね」 青年が自分の知る限り最近の情勢を話し始めると、老婦人は「まあそうなの」「それはそれは、世 の中ずいぶんと変わったものねえ」と楽しそうに相槌を打ち始める。その表情は明るく、ほとんど空 虚とすら思えるこれまでの人生を、ほとんど感じさせなかった。 (いや、少なくとも、彼女にとっては空虚なんかじゃなかったんだな) 青年には、彼女が不幸だとは思えなかった。今目の前にいる彼女が、不幸や悲惨といった文字から はかけ離れているほど、活力に溢れているように見えるからだ。 この痩せた枯れ木は、今にも花を咲かせそうなほどに、空に向かって大きく枝を広げている。 目の前で愉快そうに笑っている老婦人を見ていると、自然とそんな情景が頭に浮かび、青年も自然 と微笑みを浮かべていた。 369 名前: Please Mr.Lostman [sage] 投稿日: 2007/09/23(日) 23:25:37 ID:JoDKp6D9
そうしてしばらく話をしたあと、青年はティーカップを置いておもむろに立ち上がった。 「それでは、そろそろお暇します。紅茶、ごちそうさまでした」 「そう。ごめんなさいね、旅の途中だというのに、こんな寂しいババアの退屈な茶飲み話につき合わ せてしまって」 老婦人は冗談っぽい口調でそう言った。青年は笑って首を振る。 「いえ。とても楽しかったです。祖母にいい土産話が出来ましたよ」 「ありがとう。あなたのお婆さまにもよろしくね。ところで」 と、老婦人が不意に青年の頭を見て、懐かしそうに目を細めた。 「お婆さまも、あなたみたいに綺麗な黒髪をしてらっしゃるのかしら」 青年は自分の黒い前髪をつまみながら、祖母の姿を頭に思い浮かべる。 「そうですね。僕が子供の頃はまだ黒い髪の方が多かったかな。最近はもうすっかり白髪ばかりに なってしまいましたが」 「そう。いえね、昔わたしと恋敵だった人も、黒髪だったからね。そのせいかしら、あなたと長話な んかしたくなったのは」 老婦人は口元に手を当ててくすくすと微笑んだ。 「ところで、これからどうなさるのかしら」 「ちょっとした用事で村を出てきて、それはもう済ませてしまいましたからね。あとはもう、帰るだけですよ」 青年の馬は、休んだおかげで少しは元気を取り戻したようだった。まだあまり無理はさせられない が、今から丘を下りて街道に戻れば、日が落ちる前に今日泊まる予定だった宿場町にたどり着けるだろう。 「まあ、それほど急ぐ訳でもありませんし、帰りは護衛つきの隊商にくっついていくなりして、出来 る限り安全になるように心がけるつもりですが」 「ええ。その方がいいでしょうね。さっきのあなたのお話を聞く限り、またハルケギニア中に不穏な 気配が漂っているみたいだし」 老婦人は、少し心配そうにそう言った。 青年は馬を連れて丘の下り始めに立ち、家の方を振り返った。中天を過ぎて日暮れへと向かう太陽 が、老婦人の背後から暖かな日差しを注いでいる。 「それでは、いろいろとお世話になりました」 「ええ、道中気をつけて」 微笑んでそう言いかけた老婦人が、不意に目を見開いて絶句した。 一体どうしたのかと思ったとき、青年は老婦人の視線が自分を通り越していることに気付く。自分 の背後にある、何かを見ているのだ。 振り向くと、誰かが森を抜け、丘を登ってこちらに向かってきているのが見えた。遠目にも分かる 白髪頭から、それが老人であることが分かる。 その老人は、痩せて見える体にも関わらず力強く背筋を伸ばして、まっすぐこちらに向かって歩い てくるのだった。 (まさか) 信じられないものを見ているような老婦人の表情から、青年はある予感を覚える。自然と胸が高 鳴った。そして、自分がとても劇的な瞬間に立ち会おうとしていることに気付き、邪魔にならないよ う慌てて馬を連れ、脇に避けた。 370 名前: Please Mr.Lostman [sage] 投稿日: 2007/09/23(日) 23:26:23 ID:JoDKp6D9
丘を登ってきた老人は、青年には目もくれずに老婦人の前に立ち、 「久しぶり。約束どおり、戻ってきたよ」 と優しい口調で声をかけた。 老婦人はその言葉で動揺から立ち直ったようだった。少々そわそわした様子で、 「あら、どちら様かしら。私、痩せた枯れ木みたいな老人を友人にした覚えはないのですけれど」 と澄まして言う。老人は苦笑いを浮かべた。 「相変わらず意地の悪い奴だな。俺がお前を見間違えると思うのか」 それを聞いてどことなく安堵したように、老婦人は得意そうな微笑を返した。 「それはわたしだって同じよ。あなたがどんな風になっても、絶対に見間違えない自信がある」 そこまで言って、微笑が崩れた。皺だらけの顔が歪んで泣き笑いの表情になり、老婦人はたまらな くなったように、老人の胸に飛び込んだ。 「お帰りなさい。ずっと、ずっと待ってたのよ」 「ああ、ただいま。ごめんな、こんなに遅くなっちまって」 老人が優しい手つきで老婦人の頭を撫でる。ようやく帰ってきた思い人の胸の中で顔を上げ、老婦 人はそっと微笑んだ。 「本当、遅れすぎだわ。おかげでこんなに老けちゃって、今日なんか痩せた枯れ木みたいなババア だって言われちゃった」 「それは俺だって同じだよ。向こうじゃ妖怪枯れ木ジジイなんて呼ばれてたんだぜ」 「まあ」 二人は抱き合ったまま見つめあい、若者のように笑いあった。若者のように、という表現は正しく ないかもしれない。青年から見れば、老婦人と老人は、そこらの若者などよりもずっと明るい笑い声 を響かせている。 「本当に、待っててくれたんだな」 老人が言った。 「当たり前じゃない。約束したもの。でも」 老婦人が、悪戯っぽい笑みを浮かべた。 「正直、ちょっと不安だったわね。あんたってかなりの助平だったもの。向こうで、わたしのことな んか忘れて他の女とくっついてるんじゃないかって、何度も疑ったわ」 「そりゃ俺だって同じだよ」 老人も苦笑する。 「モグラみてえな俺と違って、お前は美人だったものな。俺がいない間にコロッと他の男になびいち まうんじゃないかと、気が気じゃなかったさ」 老婦人が、少女のように唇を尖らせた。 「まあ、失礼ね。わたし、そんな不貞な女じゃありませんことよ」 「お前こそ、俺の一途さを疑ってもらっちゃあ困るね」 「何言ってんの、昔あれだけフラフラして、わたしを泣かせてたくせに」 「そりゃお前がなかなか俺の気持ちに応えてくれなかったからだろう」 二人はまた笑いあう。先に笑いを収めたのは、老婦人の方だった。 「わたしは、あなた以外の人と愛を語り合ったことなんて一度もなかったわ。ただずっと、あなただけを待ってた」 老人も、自分の胸の中の老婦人の顔をじっと見つめて頷いた。 「俺もさ。お前以外の女なんて目に入らなかった。ただずっと、お前に会うために、ここに戻ってく る方法を探し続けてたんだ」 「それは寂しい人生だったこと」 「そうでもないさ。まだ、これからがある」 371 名前: Please Mr.Lostman [sage] 投稿日: 2007/09/23(日) 23:27:10 ID:JoDKp6D9 そう言って、老人は一度老婦人から体を離す。懐に手を入れて、手の平に収まるぐらいの小箱を取 り出した。老婦人が無言で受け取って蓋を開けると、中には大粒のダイヤをはめ込んだ指輪が収めら れていた。 「これ」 老婦人が、戸惑うように老人と指輪を交互に見比べる。老人は深く頷いた。 「ずいぶん遅れちまったけどな。俺の気持ちは変わってないよ」 「本当にいいの?」 老婦人は不安げな表情で問いかけた。老人が眉をひそめる。 「何が」 「見ての通り、わたしは本当に、痩せた枯れ木みたいになっちゃったわ。こんなババアと残りの人生 を過ごそうなんて、いくらあなたでも冒険が過ぎるんじゃないの」 老婦人は、自分の細い腕を見て泣きそうな顔をする。老人は呆れたように肩を竦めた。 「さっきも言ったろ。痩せた枯れ木みたいになったのは俺も同じだよ。それにな」 老人は眩しそうに目を細め、壊れものを扱うような優しい手つきで、老婦人の皺だらけの頬を撫でた。 「痩せた枯れ木なんていうけど、俺には今でも、お前が枝一杯に満開の花を咲かせてるように見えているよ」 老婦人の頬がかすかに赤くなった。 「言い過ぎでしょ、こんなババアに。顔は皺だらけ頭は真っ白けで、もう見るとこなんかないし」 ここに来て急に自信をなくし始めたように、老婦人は悲しげに自分の白髪をいじっている。 老人はうんざりしたように頭に手をやった。 「お前って相変わらず面倒な女だな。分かった、じゃあはっきりと言ってやるよ」 老人は老婦人の手を取り、強く彼女を抱き寄せた。かすかに息をつまらせる彼女の眼前まで顔を近 づけ、先程の言葉どおり、はっきりとした口調で言う。 「ババア結婚してくれ」 老婦人の顔が一瞬で真っ赤に染まった。老人の手を乱暴に振り解くと、先程までのしおらしさが嘘 だったかのように激しく怒鳴る。 「なによそのプロポーズ。ふざけてんの」 「うるせーな、お前があんまりババアババア言うから仕方ねえだろ」 拗ねたようにそっぽを向く老人に、老婦人はますます顔を赤くする。 「だからって」 「あのな」 老人は咳払いすると、再び真顔になって、熱っぽい口調で言い出した。 「俺は、お前がどんだけ年食おうがしわくちゃになろうが痩せた枯れ木みたいになろうが、そんなこ とはどうでもいいんだよ。美少女だろうがババアだろうが関係ねえんだ。美少女なら美少女のお前 が好きだし、おばさんならおばさんのお前が好きだ。だから、ババアならババアのお前が好きなん だよ。要するに、お前が好きなんだ。愛してるんだよ。だから言うんだ」 そう言って、老人は再び老婦人の手を握り締めた。 「ババア結婚してくれ」 老婦人の顔の赤みは、とっくに引いていた。彼女は呆れたように老人を見上げ、ため息を吐いた。 「あんたって、本当に全然変わってないのね」 「だから、お互い様だろ。で、返事は」 「そうね」 老婦人は、指輪をそっと左手の薬指にはめた。それを老人に見せながら、にっこりと微笑む。 「いいわ。そのふざけたプロポーズ、受けてあげる。痩せた枯れ木みたいなジジイと、くたばるまで 一緒に暮らしてあげるわよ」 先程の怒りの仕返しとでも言うような、皮肉っぽい口調である。 「それは正しくねえな」 老人も負けずに皮肉っぽく返す。 「正確には、くたばるまで、じゃねえよ。くたばった後もだ」 老婦人は大袈裟に顔をしかめた。 「なにあんた、犬のくせに貴族の娘と同じ墓に入ろうっての」 「当然だろ。そのぐらいする気がなけりゃ、ここには立ってねえよ」 老人は自信ありげに断言する。 老婦人は微笑ながら両手を大きく広げ、彼を抱きしめる。彼もまた、骨ばった腕で彼女を包み、強 く、強く抱きしめた。 「ここまで来たんだ。どこまでだって一緒に行くさ」 「ええ。どこまででも、着いてきてみせなさいよ」 二人は互いに囁きあうと、少しだけ体を離して見詰め合った。そして、どちらからともなくおもむ ろに顔を寄せ合い、静かに唇を重ねあう。 夕陽の中で体を寄せ合う二人が、今一時だけ若者に戻ったように思えて、青年は何も言えずにただ ただ黙って彼らの姿を見つめていた。 372 名前: Please Mr.Lostman [sage] 投稿日: 2007/09/23(日) 23:28:09 ID:JoDKp6D9
「ヘッ、こんな辺鄙なところで、汚ぇジジイと枯れたババアが三文芝居をやっていやがるとは思いも しなかったぜ」 突然、背後から嘲笑を含んだ声が響き渡った。青年は慌てて振り返る。見ると、丘の少し離れたと ころに、荒々しい雰囲気の男が立っていた。後ろには、先程逃げた盗賊たちを引き連れている。 (しまった。あの連中、頭目をつれて戻ってきたのか) しかも、新たに現れた頭目は、先程の盗賊たちとは比べ物にならないぐらいに危険な目をしていた。 部下がチンピラだとすると、この男は極道だ。悪の道を極めた人間だと嫌でも悟らせるような残忍な 気配が、青年の背筋を震わせる。 「久しぶりだってのに、とんだ邪魔者の登場だな」 「本当ね」 老婦人と老人は、静かに体を離して闖入者を睨みつけた。 「俺の子分をずいぶん可愛がってくれたみてえじゃねえか」 言葉に憤怒を滲ませながら、頭目が馬を下りてゆっくりとこちらに近づいてきた。 「舐められたらやっていけねえ身分なんでな。悪ぃが全員まとめて始祖ブリミルの御許へ行ってもらうぜ」 頭目は、腰に下げていた長い得物を抜き放った。驚いたことに、それは剣や銃ではなく、杖だった。 頭目は目を閉じ、静かに詠唱を始める。炎が飛んでくるのか大地が割れるのか予想もできず、青年 は咄嗟に目を閉じ、顔を手でかばう。 しかし、頭目が詠唱を終えても、派手な音は何一つしなかった。おそるおそる目を開けると、そこには信じられない光景が広がっていた。 「風は偏在するってな」 頭目の得意げな声が、いくつも重なり合ってその場に響き渡る。それもそのはず、先程まで何もな かった場所に、頭目と同じ姿の男が5人も立っていたのだ。 「分身の魔法か。ずいぶん懐かしいものを使うねえ」 老人がふざけた様子で口笛を鳴らす。頭目を恐れているような感じは全くなく、それは老婦人の方 も同様だった。 「スクウェアクラスの魔法を使えるような男が、こんなところで盗賊なんかやってるとは思わなかったわね」 彼らが全く慄く様子を見せなかったためか、頭目は少し調子を狂わされたらしい。意外に端正な顔 をゆがめ、唾を飛ばして怒鳴る。 「うるせえな。親父もお袋も大罪人だったんでな。表街道は歩けねえのよ。だが俺はやるぜ。お袋か ら受け継いだ盗賊団と、親父から受け継いだ『閃光』の二つ名と風魔法の才。幸い今の世は乱世だ からな、腕一本でどこまでものし上がってやるさ」 二つ名のことを聞いたとき、老人と老婦人は目を丸くして顔を見合わせ、よく出来た冗談でも聞い たように笑いあった。頭目がさらに顔を赤くする。 「何がおかしいんだ」 「いいえ、別に。ただ、ずいぶんと大それた望みだと思ったのよ」 「全くだな。さって、それじゃ、やりますか。な、あいつ、持ってきてくれよ」 「はいはい」 老人の頼みに答えて、老婦人は軽やかな足取りで家の方に向かった。どうせこんな老人達には何も 出来まいと高をくくっているのか、頭目は特に何も言わない。 老婦人は、玄関に飾られていたあの古びた大剣を持って戻ってきた。 「はい、どうぞ」 「うわ、なんでこんなボロくなってんだこいつ」 老人は剣を受け取ると、嫌そうに顔をしかめた。老婦人が肩をすくめる。 「あんたが行っちゃったあと、『相棒が戻るまで起こさねえでくれな』とか言って、こんな風になっ ちゃったのよ。あれ以来一回も抜いてないわ」 「相変わらずだなこいつも。まあいいや、抜けばまた元に戻るだろ」 気楽そうに言って、老人は剣を鞘から引き抜いた。途端にどこかからいびきが聞こえてくる。 373 名前: Please Mr.Lostman [sage] 投稿日: 2007/09/23(日) 23:29:03 ID:JoDKp6D9
「おいデルフ、起きろよ」 老人が剣に向かって話しかける。一体何をしているのかと思ったとき、不意にいびきが止んだ。 「んあ……なんだよ人がせっかく……って、ひょっとして相棒かい」 寝惚けた声が、驚いた声に変わる。青年は目を見張った。どうやら、喋っているのはあの刀身が錆 びた剣らしい。 (そういや、婆ちゃんの昔の友達も、喋る剣を持ってたとか言ってたっけ) そんなことを思い出す青年の前で、剣は感心したような、あるいは面白がるような口調で喋り出す。 「こりゃたまげたね。まさか本当に戻ってくるとは……それにしても、ご主人様共々痩せた枯れ木み たいになっちゃってまあ」 「相変わらず口の減らねえ野郎だな。だが安心したぜ。状況は分かるな?」 老人は苦笑しながら鞘を背中につけ、右手に握った剣に問いかけた。剣がのんびりと返事をする。 「まあ大体ね」 「だったらそんな錆びついたなまくらの振りなんかしてねえで、とっとと本領発揮しやがれ」 「へいへい。全く剣使いが荒いんだから」 剣は、内容とは裏腹に嬉しそうな声で文句を垂れながら、突然その錆びついた刀身から光を迸らせ た。次の瞬間、その刀身は一瞬前まで錆びついていたのが信じられないような、磨き上げられた鉄の、 鈍い輝きを宿していた。 「どうだい。俺っちは昔と何も変わらねえだろうが」 「ちぇっ、一人だけ若返りやがって。まあいいけどよ」 「おい、馬鹿げた芝居はもう終わりか」 それまで黙っていた頭目が、嘲るように言った。 「そのご立派な剣で俺と勝負しようってのか。あんまり舐めんなよ。テメエみたいな枯れ木ジジイが、 そんな玩具でメイジに敵うとでも思うのか」 「テメエこそ、ちょっと数が増えたぐらいで歴戦の勇者に勝てるなんて、自惚れが過ぎるんじゃねえのか」 老人は自信ありげに笑うと、柄を握っている右手に、ゆっくりと左手を重ね合わせた。 「かかって来いよ。枯れてもなお衰えぬ伝説ってやつを、お前に見せてやるよ」 呟きと共に、老人の左手の甲が眩く輝き始める。 「そんな子供騙しで!」 分身した頭目たちが、老人に向かって一斉に魔法を放った。老人はそれを避けようともせず、ただ 静かに剣を振り上げる。 そして青年は、伝説を見た。 374 名前: Please Mr.Lostman [sage] 投稿日: 2007/09/23(日) 23:30:31 ID:JoDKp6D9
五分後には、既に勝負がついていた。 剣の作用か老人の腕によるものか、あらゆる魔法を無効化された頭目は、ムキになることもなく素 早く退散した。素人目に見ても、実に鮮やかな引き際である。辺境の盗賊団とは言え、やはり頭に収 まる人間は普通のチンピラとは違うらしい。 こうして、日暮れの丘に再び静寂が戻ってきたのである。 「お疲れ様。なんだ、すっかりヨボヨボになった思ってたのに、昔と少しも変わらないじゃない」 「そりゃそうだ。ルーンは健在だし、一日だって鍛錬は欠かしてないからな」 かなり激しく立ち回ったように見えたが、老人は息を乱してすらいない。その年に似合わぬ頑強さ に感嘆する青年の前で、老人は呆れたようにため息を吐いた。 「しっかし、ついてそうそうこんな物騒なことになるとは思いもしなかったなあ」 「そうね。最近、また世の中が乱れてきてるみたいだし」 老婦人は、青年の方をちらりと見ながら言う。老人は驚いたように眉を上げた。 「そうなのか」 「ええ。ねえ、さっきの話、この人にも教えてくださらないかしら」 「あ、はい」 促されて、青年は二人の方に歩み寄る。老人が怪訝そうに首を傾げた。 「そういや、さっきからちょっと気になってたんだが、あんたは誰なんだ」 「ああ、僕は」 青年が自己紹介するよりも早く、老人は何かに気付いたように目を見開いた。 「まさか、こいつの愛人とか」 「違うわよ、馬鹿ね」 老婦人が例の木の棒で老人の頭を小突く。 「と言うか、失礼でしょう。こんな若い人に、そんな疑いをかけては」 「そうだよな」 老人はほっと息を吐く。 「こんな痩せた枯れ木みてえなババアを気にかける男なんて、俺ぐらいしかいるはずねえもんな」 「一言余計なのよこの枯れ木ジジイ! 老人らしくない喧嘩が始まったので、青年が説明を始めるのには少し時間がかかってしまった。 375 名前: Please Mr.Lostman [sage] 投稿日: 2007/09/23(日) 23:31:05 ID:JoDKp6D9 かつてのアルビオン王国の滅亡に端を発する一連の戦争が終結して以来、ハルケギニアにはつい最 近までそこそこ穏やかな時間が流れていた。 だが、ニ、三年ほど前から、その平和にも徐々に翳りが見え始めていた。 そのきっかけがなんだったのかは、一般民に過ぎない青年には分からない。 ただ、そんな一般民にも分かるぐらい、ハルケギニアの至るところで戦乱の種が芽吹き始めていた。 ゲルマニアでは、最近勢力を伸ばしてきたツェルプストー家が、現皇帝家と一触即発の状態にある。 既に偶発的な小競り合いが頻発しており、表面上はその都度和解に妥協しながらも、裏では互いに兵 を集めて開戦の機会を窺っているという噂である。 ガリアでは、ずっと権力の座に居座り続けたイザベラ前女王が最近になって急逝した。次代の王に は二人の有力候補がいる。前女王の嫡男と、王家に縁深いオルレアン家の嫡男である。血筋から考え れば前女王の嫡男が王位に着くのが当然であるが、資質としてはオルレアン家の嫡男の方が圧倒的に 優れているため、各々を王にと推す派閥同士が対立し合い、内乱寸前の様相を呈してきているという。 トリステインも状態は同じようなもので、数年前に王政が幕を下ろして以来、新たな支配者の座を 巡る争いが未だに収まっていない。今現在は旧近衛隊の隊長であり、鋼鉄の女という異名でも知られ る老女傑、ミラン卿がギリギリのところで治安を維持しているが、それも限界が近いのだという。 旧王家が滅亡して以来各国分割統治の状態にあるアルビオンでも、不可思議な力を持つハーフエル フの女性を教祖として崇める謎の宗教団体が、日に日に発言力を高めており、ここでも近い内に大規 模な騒乱が勃発すると予想されている。
「という訳で、僕が住んでいる田舎の村でも、住民は不安な日々を送っているんです。僕が今回こん なところまで出かけることになったのも、所用以上にハルケギニアの情勢を知るという目的が大き かったですし」 長い説明を聞いた老人と老婦人は、顔を見合わせて苦笑した。 「どうやら、お前と一緒に静かな老後を送るには、困難が多すぎるみてえだな」 「そうみたいね。さて、どうしましょうか」 答えは予想出来ているとでも言いたげに、老婦人は自信に満ちた瞳で老人を見た。老人もまた、当 然と言わんばかりに頷いた。 「決まってんだろ。行くともさ」 「そうね。あんたって、そういう奴よね」 「やれやれ、仕方ねえから俺っちも付き合ってやるよ」 老人の背中で、剣が鞘から少し抜け出して喋る。老人と老婦人は、顔を見合わせると、意地の悪い 笑みを浮かべて言った。 「当たり前だろ」 「今まで寝てた分、刀身が砕けるまで働いてもらうわよ」 「うひゃあ、勘弁してくれよ」 剣が情けない声を上げて鞘に引っ込む。老人と老婦人は、また顔を見合わせ、声を上げて笑った。 青年が説明している間に夕暮れも遠くに去り、暗い夜空には月と無数の星々が浮かんでいる。満点 の夜空を見上げながら、老人は穏やかに呟いた。 「じゃあ、もう少しだけ、頑張ろうな」 「ええ。今度はもう離れない。ずっと一緒よ」 老人と老婦人は、その言葉を証明するように、固く手を取り合う。 その光景を見たとき、青年の背筋に震えが走った。 この、世界中の誰からも忘れ去れた二本の枯れ木は、日の光の代わりに夜空から降り注ぐ星の光を 浴びて、大輪の花を咲かせることだろう。その花の香はハルケギニアの至るところに届き、人々を希 望の朝へと導いていくに違いない。 何故か、そんな予感が全身を震わせていた。 (婆ちゃんへの土産話が、また一つ増えたみたいだな) そんなことを考えながら、青年は老人と老婦人の背中をいつまでも見つめ続けた。
かくしてこの日、忘れ去られた伝説は、ハルケギニアの片隅で再び花開いた。 この地が再び平穏な時間を取り戻すのは、これより五年ほど後のことである。