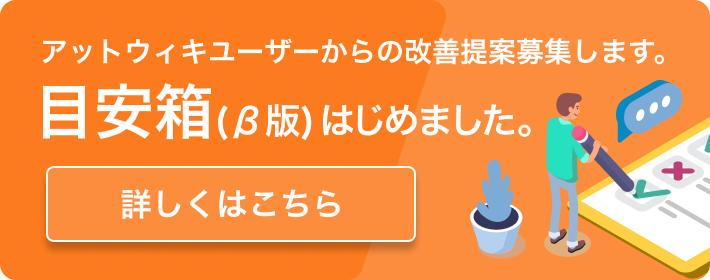384 名前: 名無しさん@ピンキー [sage] 投稿日: 2007/09/24(月) 00:01:03 ID:TCTq6+1K 予定の時間より遅れましたが、投下作品の余韻のほうが大事と思い自粛しました。 んだば、許可も得たので失礼して。
今でも夢に見る。あの炎に包まれた光景を。
コルベールの朝は早い。軍人だったころの癖が抜けきらないのもあるが、教師としての 職務だけに飽き足らず、趣味の研究までしているのだ。時間はいくらあっても足りず、睡 眠時間を削ってまで日々を過ごしている。 そんな彼を義娘はいつも叱る。もっと体を大事にしなさいと。 食事に頓着をしない彼のために栄養を考えた食事を作り、風邪を引かぬようにと冬には 拙いながらもマフラーを編んでくれる。 実にできた娘だった。コルベールにはもったいないほど、優しく育ってくれた。
義父が、過去に彼女の村を焼いたとも知らないで。
義娘の優しさに触れるたび、コルベールは言葉では言い表せぬ痛みを何度も胸に抱いた。 彼の体を気遣う優しさが痛い。彼の背中を追って同じ教職を選んだという尊敬が痛い。 父と慕ってくれる愛情が痛い。ことあるごとに向けられる笑顔が痛い。
何よりも許せないのは――一瞬でも罪を忘れてしまいそうになる自らの心の弱さだった。
その度にコルベールは己の罪深さを心に刻む。彼女は、罪の証なのだと。
窓から差し込む光に目を細め、コルベールの思考は中断された。いつの間にか、太陽は ずいぶん高く上っていたらしい。時計を見れば、もうすぐ授業の時間だった。
「やれやれ」
ぎい、となる椅子から立ち上がると、傍らに畳んでおいたマントを羽織る。その動作は のろのろとしたもので、どうにも気が乗らない様子だ。 別段、コルベールは授業に行くのが嫌なのではない。かつて血に濡れた手で何を教える と思わないでもないが、だからこそ、子供たちには学んで欲しいのだ。魔法で壊す以外の 何かを。 だが、それを教えるべき生徒たちは今たったの半数しかいない。コルベールが嫌う血で 血を洗う戦争のせいで。 糞くらえだった。彼らのうち、何人が戻ってこれるというのか。戻ってきたとしても、 その罪に耐えられぬものは必ず出てくるはずだ。コルベールと同じように。 怒りのせいだろうか。誰もおらぬ廊下を歩くコルベールの鼻を、忘れかけていた硝煙と 血の匂いが掠める。聞こえぬはずの悲鳴が耳に届き、感じるはずのない感触が腕を伝う。 知らぬ間に、手は杖を硬く握り締めていた。まるでこの先の廊下の角で誰かに出会った としても、すぐに対処できるように。
「何を馬鹿な」
かぶりを振って自らに言い聞かせたが、一度心についた火は容易に消えそうになかった。 もはや、足音だけでなく衣擦れすらも消している。 そうして、自らが作り出した静寂の中、ようやくコルベールは気づいた。
「……っ静か過ぎる!」
なぜ気付かなかった――胸のうちをつく焦燥。走りながら、コルベールはマントを脱ぎ 捨てた。 これは、戦場の空気だ。 385 名前: 名無しさん@ピンキー [sage] 投稿日: 2007/09/24(月) 00:01:37 ID:ECRxxlmx II/ メンヌヴィルにとって、女子供しかおらぬという学院の制圧など、ひどく気乗りしない 任務だった。彼が望むのは強者との戦い。無論、女子供の焼ける匂いは凡百の男を燃やす よりはよほどメンヌヴィルを興奮させるが、それは渇いた喉を潤すには程遠い、その場し のぎにしか過ぎない。 今でも彼は思いを馳せるのだ。目の光を奪ったかつての上官を焼いてみたいと。 その妄想に比べれば、実の燃える匂いなどすべて屑のようなものだった。届かないと、 メンヌヴィルに思わせたのは彼だけだったし、実際届かなかったのも彼だけだった。 その至上をわずかでも連想させるために、メンヌヴィルはいまだ傭兵などという仕事に ついているのかもしれない。
「さて、そこのお前はどう思う?」
震える炎の少女を前に、メンヌヴィルは空を見ながら問いかけた。答えを期待したわけ ではない。この少女に期待することなど、せいぜいいい匂いで焼けてくれと思うぐらいだ。 そしてその予想通り、少女は問いかけに答えることはしなかった。恐怖に身を竦ませ、 怯えているだけだ。 視線を外している内に逃げようとも立ち向かおうともしない。もっとも、彼の瞳は既に 死んでいる。故に見ていようがいまいが変わりないのだが。
「ふむ、同じ炎使いなのが仇になったか」
少女の炎は、実に立派なものだった。力の程は大したことはなかったが、応用力が素晴 らしい。非力を理解し、状況に即して行使する魔法を選ぶ判断の速さで言えば、メイジと してならかなりの腕になるだろう。あるいは目が見えていたころの彼ならば、負けるまで いかずとも、深手を負っていたかもしれない。 だが、その秀でた判断力が今となっては仇となる。少女は震えていた。わかるのだろう、 二人の間にある絶対的な力の差が。メンヌヴィルがかつて思い知ったように。少女もまた メンヌヴィルとの力の差を知ったのだ。
「惜しいな。あと五年、いや、三年遅ければ、それなりの勝負になったやしれぬものを」
言葉とは裏腹に、その口調は実に楽しげだった。強者との戦いも面白いが、前途ある 才能あふれる若者を焼くのも、メンヌヴィルの趣味には実に合致する。 愉悦に口を歪ませルーンを唱えると、煌々と辺りを照らす巨大な火球が頭上に浮かぶ。 人一人を燃やすには、明らかに過剰な火力だった。これでは肉が焼けるどころか一瞬で 骨まで燃えつきてしまうだろう。だが、刹那に消える儚げな匂いもまた乙なものだ。
「花火のように、白炎に消えろ」
そうしてメンヌヴィルが杖を振り下ろし――一面は炎に包まれた。肌を焼く熱気の中、 メンヌヴィルは強く息を吸い込む。鼻がひりつくがかまいはしない。一瞬で消える匂いを 楽しむためならば、多少の火傷などむしろ望むところだった。 だが、その望むべき匂いはいつまでたってもやってこない。ただ鼻に届いたのは、想像 以上に強い肉の焼ける匂い。 これほどの炎を放ったのだ。機を逃し匂いを嗅ぎ取れぬことはあっても、こうまで肉が 焼ける匂いが続くことなどあるはずがない。 訝しんでメンヌヴィルは獲物の温度を探った。が、放った炎が余りに強烈だったせいで うまく感知できない。
「っち」
舌打ちして、メンヌヴィルは聴覚に意識を集中させた。炎のはぜる音は確かに邪魔だが、 温度と匂いに頼るよりはマシだった。その中で、彼は風の音とありえぬ声を聞いた。
「大丈夫だったかい」
「――お父さんっ!!」
それは、かつての上官の声だった。 386 名前: 名無しさん@ピンキー [sage] 投稿日: 2007/09/24(月) 00:02:15 ID:ECRxxlmx III/
「コルベール、コルベールコルベールコルベール! 炎の蛇、隊長殿!!」
歓喜の声でメンヌヴィルは叫んだ。興奮のあまり、今にも襲い掛からんばかりの勢いだ。 それがわかっていながらなお、コルベールは振り返ることを拒んだ。目の前には怯えた 我が子がいるのだ。警戒は忘れない。だが、幾百の敵を打ち払うより、娘の心を守ること をコルベールは選ぶ。 身に纏っていた風の魔法を解除すると、コルベールは優しく娘に語りかけた。
「さあ、逃げなさい」
「でもお父さん、やけど、ひど、あ、そんな、ダメだよ、死んじゃうっ!」
だが、守られたのはまたしてもコルベールのほうだった。助かったことよりも何よりも 先に、まず父親の心配をしたのだ。震える指先は、焼け爛れた皮膚を気遣うように何度も 何度も中空で撫でるように行き来した。涙を流してないのが不思議だった。 思えば、この子が最後に泣いたのはいつだっただろうか。コルベールにはもはや覚えが ないほど昔のことだ。その子が今、涙を流さず泣いている。 そうして決意を胸に秘めると、娘を案じる父親と部下に命令する上司の中間のような、 例えようのない中途半端な笑みを浮かべ娘の頭を撫でると、コルベールはひとつ頷いた。
「心配ない。後ろの彼は僕が倒そう。生徒たちの安全は任せた」
その言葉に、娘は息を呑んだ。思案しているのがわかる。自分も戦うと考えてるのか、 あるいは、一緒に逃げようと言おうとしたのかもしれない。聞けばきっと自分はそれを 受け入れてしまうだろう。 残り少ない後ろ髪を惹かれる思いで娘の顔を視界から追い出すと、コルベールは即座に 立ち上がる。振り向けばわかった。そこにいたのは、かつて己を殺そうとした部下だった。 あまりの皮肉さに、コルベールは人知れず臍をかんだ。折りしも、部下が襲い掛かって きたのは娘の村を焼き払ったときだ。 過去はいつまでもその背に付きまとい、思いがけぬ時に現在に襲い掛かってくる。
「せめて、すべて私に咎が来ればよいものを」
かぶりを振って、コルベールは呟いた。声量に反し、そこには隠しきれぬほどの怒りが 込められている。その矛先は、自分であり、メンヌヴィルであり、天にいる神であった。 あの子から母を奪ったのは誰だ。故郷を奪ったのは誰だ。炎で全てを失った子に、炎の 才能を与えたのは誰だ。そんなあの子に、再び炎と相対させたのは誰だ。
「どうした、早く行きなさい」
この場から娘を逃がそうとするのは、何もその身を案じてばかりのことではなかった。 怒る自分を、過去に戻ろうとする自分の姿を、コルベールは見せたくなかったのだ。 その声の硬さに気づいたのか、娘は立ち上がると、ようやく学院のほうへ走り始める。
「誰か呼んでくるから! だから、それまで絶対死なないでね、おとーさん!!」
口の端に、笑みが浮かぶ。まったく、自分は恵まれすぎている。それこそ、今死んでも いいくらいだ。 猛る心を落ち着かせて守るべきものを心に刻み付けたコルベールは、全ての神経を目の 前の敵に集中させた。 387 名前: 名無しさん@ピンキー [sage] 投稿日: 2007/09/24(月) 00:02:58 ID:ECRxxlmx 「待たせね」
「は、かまわんさ。会えぬと思っていた貴方に今再びまみえることができたのだ、不意を ついて焼いてもつまらなすぎる。それに今生の別れだからな。 しかし驚いたぞ、隊長殿。貴方にまさか娘がいたとは。年のころはせいぜい二十歳か。 あの事件のあとに妻でも迎えたか?」
「血の繋がりはないさ。彼女は……あの事件の数少ない生存者だ」
「は、はははははは! なんと、なんという馬鹿げたことをしているんだ、隊長殿! まさか焼き残しをしたはおろか、その生き残りを引き取って育てるとは! 命令に反逆 するなど、俺の知る隊長殿では考えられんわ」
呵々大笑するメンヌヴィル。それを見て、コルベールは直感的に悟った。この男もまた、 あの事件の裏側を知っていると。 杖を握り締め、コルベールは眼前の敵を強く見据える。
「そうだな、お前の知る炎の蛇はもういない。今ここにいるのは、ただ一人の父親だ」
「それは同情か? 贖罪か? あるいは、自虐の趣味でもできたのか?」
メンヌヴィルの隠そうともしない嘲りを受けてなお、コルベールの表情の表情は凪いだ ままだった。だが、その内心は違う。自らの侮辱などどうでもいい。ただ、娘を傷つけた この男が一秒でも長く生きていることが耐えられなかった。 顔では表せぬほどの激情がコルベールの胸のうちにはあった。同じように、抑揚のない 声でコルベールは語りかける。
「そのどれかかもしれないし、全てかもしれないし、どれも当てはまらないかもしれない。 私自身にもわからないし、一生わかるつもりもない。お前が望むような答えを、私は持ち 合わせてはいないんだ。だから、言えるのはただひとつだけ。 一応聞いておこう。メンヌヴィル、降伏するつもりはないか?」
犬歯もあらわに笑い、メンヌヴィルは杖を突きつけた。
「痛みや熱に浮かされ狂ったか、隊長殿。まさか本気で言ってるわけではあるまい」
一言ルーンを唱えれば、即座に炎が飛び出してくるだろう。 そのような状況において、コルベールは、盲しいているというのによく正確に切っ先を 向けられるものだな、とどこか遠くに思いながら、なんとその瞳を閉じた。 瞼の裏に映るのは、自分が殺した妊婦の姿。炎に焼かれながらもお腹を庇い、そうして 死んでいった。任務でなければ、到底できるはずもないむごい仕打ちだった。 ――その任務は嘘だった。すべてに裏切られたコルベールがその胎の子が生きていると 聞いたとき、彼は決めたのだ。彼女の万難を焼き払う炎になることを。 再びコルベールが目を開く。その顔には、笑みが浮かんでいた。メンヌヴィルに劣らぬ、 獰猛な獣の笑みだ。
「そうか、それはよかった」
「は?」
呆けた返しをするかつての部下に、その手に杖が握られていることが不自然に思えるほ ど優しい、それこそ生徒に者を教えるような口調でコルベールは語りかけた。
「何、“僕”はどうにも娘のことになると短気なようでね。オールド・オスマンの傍など 近寄らせたくないほどなのだ。まして娘を傷物にしようとした男を許せるほど、“僕”の 気は長くない。だから言ったんだよ。 ――お前が降参してくれなくてよかった、と」
言って、コルベールは駆け出した。哄笑とともにメンヌヴィルが迎え撃つ。 二十年越しの戦いが、今始まる。 388 名前: 名無しさん@ピンキー [sage] 投稿日: 2007/09/24(月) 00:03:45 ID:TCTq6+1K IV
戦いはまず機先を制することから始まる。既にして炎に焼かれてしまったコルベールの 不利は否めない。体力にも余裕がない。長引けば長引くほど、コルベールの敗色は濃厚に なっていく。まして、二人の間には二十年もの実戦の月日が隔たれている。 相手は盲人、反応できぬ接近戦で一気にけりをつける――そう判断したコルベールは、 長い杖をレイピアのように見立て、メンヌヴィルの太い首に杖を突き出す、と見せかけて その足元を狙った。 フェイントだった。いきなり接近戦を挑む奇襲に加え、上半身、それも一撃で戦闘力を 失える首への攻撃に意識を集中させ、その反対に相手の足をまず奪う。 盲人相手に慎重すぎるかも知れぬが、体格差は余りにも歴然としている。偶然の一撃が、 コルベールにとって致命傷にならぬ保証はない。 限られた体力の中にあって、コルベールのかつての冷徹な思考が蘇っていた。 だが、メンヌヴィルはそのコルベールの予想の上をいった。杖を突き出すのにあわせ、 すっと足を後ろにやったのだ。 体重を乗せた突きが空振り、杖が固い地面に突き刺さる。驚愕に目を開くコルベールの 無防備な腹を丸太のような蹴り足が襲う。 だが、一撃をかわされた程度で負けるような者が、どうして特殊部隊の隊長にまで昇り つめられよう。それが例え過去のことであっても。 襲い掛かる蹴りを冷静に眺めながら、コルベールは体重が乗せられた杖に力を込めた。 いや、正確には、その力の向きを変えたのだ。前に傾いでいた体が、ベクトルを変えられ メンヌヴィルの左側面から離れるようにと流れていく。 無造作とも思われた一撃は、そのままコルベールの回避手段に繋がっていたのだ。
「っく」
「ちっ」
同時に舌打ち。お互い、今の一撃を外したのは大きい。 コルベールは大きく体力を削られ、メンヌヴィルは相手を倒す絶好の機会を失った。 だが、それでも有利なのはやはりメンヌヴィルだ。圧倒的な体力の差がある。
「どうした、隊長殿。もう息が上がっているぞ」
答えず、答える余裕もなく、コルベールはルーンを唱える。今の一撃でわかった。敵を 盲人と侮り接近戦を挑んだのは過ちだった。彼の感覚は、確かにコルベールを捉えている。 残りわずかな体力でメンヌヴィルを打ち倒すのはもはや無理だろう。不利を承知して、 魔法で挑むしかなかった。 コルベールの杖先に長い炎が生まれる。火球をいくつも連ねたその様は、うねる蛇腹を 連想させた。コルベールの二つ名でもある炎の蛇。破壊しか巻き起こさぬ赤い炎。
「は、はははは! ようやくだしたか、隊長殿! それだ、それを見たかったのだ。俺の 光を奪った炎の蛇。 格闘など捨て置け。それではつまらん、炎で来い。さあさあさあ、俺はずっと、それを 殺したくて仕方なかったんだ! 今ここに、俺はようやく過去を越える!!」
笑いながらルーンを唱えたメンヌヴィルの周りに浮かぶ白々とした五つの火球。恐らく その温度は、優に千を超える。ちりちりと傍に立つメンヌヴィルの肌すらをも焼いている。 それだけの炎を生み出しているメンヌヴィルの精神にはどれほどの負荷があるのだろう。 だというのに、彼が苦しむような気配はまるでなかった。魔法を維持するだけで額に汗を 滲ませているコルベールとは、余りに対照的だ。 389 名前: 名無しさん@ピンキー [sage] 投稿日: 2007/09/24(月) 00:04:37 ID:TCTq6+1K 「行けっ」
長引かせるのはまずいと判断したコルベールがまたしても先手を取る。陽炎を纏う炎の 蛇が、獲物を狙うようにメンヌヴィルに向かって突き進む。言葉もなく、メンヌヴィルは 杖を振った。白炎の球が蛇を襲う。 一つ。蛇はメンヌヴィルの炎など意に介さない。 二つ。その炎すら飲み込んで、蛇は大きくその体を成長させる。 三つ。さら巨大化した蛇が、赤から白へと色を変える。 四つ。色が、完全な白に変わる。 五つ、つまり最後の火球を飲み込んだところで、コルベールは蛇の制御を手放した。貴 重な体力を振り絞って生み出した炎の蛇だが、このままでは先に自分が潰れてしまう。 蛇が、悲鳴のような爆音を残してあたり一面に炎を撒き散らした。 沸騰した血液のようなそれを腕で振り払おうとして――首筋に感じた悪寒に従い、その 場を大きく飛びずさる。全力で、受身も考えず。 本能は理性よりも正確だった。コルベールの死角、メンヌヴィルの背後から、六つ目の 火球が数瞬前までコルベールがいたところに襲い掛かったのだ。即座に飛び跳ねなければ、 命はなかっただろう。 もはや、メンヌヴィルは体術でも魔法でもコルベールの御しきれる相手ではない。その 証拠に、後先考えずに逃げたはずのコルベールの右足は、墨のように炭化していた。
「ぐ、う……」
額を脂汗が滝のように流れる。何とか姿勢を正そうとするが、もはや片足で立ち上がれ るほどの体力はコルベールに残されていない。座りなおすことだけで精一杯だ。 そうして、炎の壁のその向こうから、メンヌヴィルがその姿を現した。悠々と歩くその 様はもはや勝者のそれだ。顔には口が裂けてしまいそうなほど深い笑みが浮かんでいる。
「どうだ、コルベール! ついに俺は、お前の蛇を殺したぞ。白炎が蛇を飲み込んだのだ。 ああ、このときをどれほど待ちわびたことか。俺の念願のひとつが、ようやく今ここに 叶ったのだ!! そして、残る願いは後ひとつ……貴様の、焼ける匂いを嗅がせてくれ」
言って、再びメンヌヴィルの周りに火球が浮かぶ。流石にその色は先ほどとは違い赤い 炎ではあるが、底知れぬ精神力だけは十分伺える。余裕すら伺えた。 たとえこの炎を凌ごうと、次の一手でコルベールは殺される。 コルベールにできることは、座して死を待つだけだ。
――そう、炎を凌ごうとするのであれば。
「メンヌヴィル」
顔を伏したコルベールの問いかけ。無視して炎で燃やせばいい。だが、勝者の余裕から メンヌヴィルはその声に答える。
「なんだ、コルベール。かつて部下だったよしみだ、末期の言葉なら聞いてやろう」
っく、と低く喉から漏れる息を、メンヌヴィルは確かに聞いた。まるで嗚咽のような声 だ。だが、目の見えぬ彼にはわかる。 それは、嘲笑だ。 390 名前: 名無しさん@ピンキー [sage] 投稿日: 2007/09/24(月) 00:05:38 ID:TCTq6+1K 「死を前に狂ったか? まあいい、残す言葉がないのなら――」
死ね。そういう前に、コルベールが面を上げた。強い意志でメンヌヴィルを睨み付け、 その手に杖を握り、
「さようならだ、メンヌヴィル」
コルベールの頭上に炎が生まれた。あまりにか細い、吹けば消えるような小さな炎。
「は、はははは。やはり狂ったか! その程度の炎など俺の前では塵に等しい。 確かにさようならだ、コルベール。さあ、お前の匂いを嗅がせてみろ!!」
メンヌヴィルの杖と、意思に答え、火球がコルベールを襲う。対するは、今まさに風に 吹かれ、鬼火のようにゆらゆらとゆれる炎。 だが、消えるのを待つまでもない。その前にメンヌヴィルの火球に飲まれて消える。
だがなぜだろう。放ったはずの火球の温度が、どんどんと弱く小さくなっていくのは。 なぜだろう。小さかったはずの鬼火の温度が、どんどんと強く大きくなっていくのは。
「これは、竜の血?」
優れた嗅覚を持つメンヌヴィルの鼻が風に漂う異臭を嗅ぎ取った。そうして、気づいた 時には遅かった。メンヌヴィルの五感は、逆流してきた炎の中に囚われた。
V/
「優れた蛇は、温度だけでなく風をも読む。目先の勝利に溺れた貴様は、風を読み間違え たのだ、メンヌヴィル」
炎に焼かれ、悶え苦しむかつての部下を眺めながら、冷静にコルベールは評価した。 蛇は、臥して獲物を狙う。それを忘れたメンヌヴィルの手から勝利がすり抜けたのは、 もはや自明の理と言える。 戦いを楽しむ者と勝利を目指す者。その違いが、勝負の明暗を分けたのだ。
「かつて上官だったよしみだ。教えてやろう。 炎はな、風のないところ、真空では燃えぬのだ。そして真空には空気が流れ込む。そこ に錬金した燃料油を流し込めば、どのような火種だろうと爆炎になる。 エンジン――貴様は知らぬだろうが、それの応用だ」
それは、かつてコルベールが使っていた「爆炎」に酷似していた。違うのは、炎炎土で はなく、炎土風に変えただけ。辺りの水蒸気を、コルベールが知る燃料油ではなく、更に 気化、炎上しやすいガソリンに錬金。その上でゼロ戦のエンジンからヒントを得た気圧差 を利用してバックドラフトにも似た状況を引き起こす。 サイトから聞いた異界の技術などからコルベールが開発した、新たな殺戮魔法だった。
「すまないな、サイト君。私はどうにもこのようなことしかできぬらしい」
地面の上から空を見上げ、主に従い遠く戦場へと赴いた少年に詫びる。 そうして空を見上げたまま、コルベールはゆっくりと大地へ仰向けに倒れていった。 391 名前: 名無しさん@ピンキー [sage] 投稿日: 2007/09/24(月) 00:06:35 ID:TCTq6+1K VI/
炎に焼かれながら、メンヌヴィルは笑った。もはや声帯までも焼け付き、呻き声にしか 聞こえぬが、確かにメンヌヴィルは笑っていた。
「素晴らしい、やはり貴様は素晴らしい、コルベール! 届かぬ。届いたと思ったが、やはり届かなかった。真にお前が焼ける匂いを、ついぞ俺 は嗅ぐことができなかった。それがどうしようもなく嬉しい! やはり俺は間違っていな かった。お前に目をつけた俺は、間違ってなどいなかったのだ」
声帯すら振るわせず、心だけ、己だけに向けた言葉をメンヌヴィルは絶叫する。肉すら 沸騰し、蒸発していく中でメンヌヴィルはただ己の正しさだけをかみ締めていた。 そうして――気づく。
「ああ、この、匂いだ」
夢にまで見た理想の匂い。届かないはずのその匂いが、今、メンヌヴィルの鼻にある。 気づけば簡単だった。メンヌヴィルが燃やしてしまった時点で、その匂いはもはや届く ものでしかない。どれほどの強者であろうと燃やしてしまえば、嗅いでしまえば、それは 届かぬ匂いではないのだ。 では、真に届かぬ匂いとは、望むべき匂いとは、メンヌヴィルが勝てぬはずの相手から もたらされるのではないだろうか。そう、自らを焼くほどの炎の使い手に燃やされること こそ、ずっと彼が望んでいた結末だ。 それが、メンヌヴィルが傭兵を続けていた理由だった。 なら、もう生にしがみつく必要はない。
「さらばだ、隊長殿」
そうして、灰だけを残してメンヌヴィルの肉体はこの世から消え去った。
VII/ アニエス。アニエス・シュヴァリエ・ド・ミラン。トリステイン王国銃士隊隊長。
そして――ダングルテールの生き残り。
炎に過去を故郷を焼かれた彼女は、何よりも炎とそれを扱う火のメイジを憎む。だから、 彼女はコルベールとメンヌヴィルとの戦いが始まろうとするのを目の当たりにしたとき、 迷わずその背後を撃つことを決めた。 無論、コルベールが教師であり、メンヌヴィルが学院における異邦人であることなど、 一目見ただけで看過できる。そして、二人が炎のメイジであることも。 幸い、メンヌヴィルの注意はコルベールばかりに注がれていたため、背後を取るのは 容易だった。有効射程からはいささか距離はあるが、位置的にはそこがベストだ。 コルベールが勝てばよし。負ければ、そのときは背後から奇襲を。 敗北が死に繋がることなど容易に想像できるが、それがアニエスの下した判断だった。 幸いにも、勝負はコルベールの勝利に終わった。メイジ殺しと称されるアニエスの背に 冷たい汗が流れるほどの勝負に、無傷とは言わないまでもコルベールは勝利したのだ。 なれば、好かない相手でも捨て置くわけにはいくまい。いつの間にか白んでいた手から なんとかして銃把を取り離すと、いまだ熱気覚めやらぬ中庭をアニエスは歩んでいく。
392 名前: 名無しさん@ピンキー [sage] 投稿日: 2007/09/24(月) 00:07:53 ID:TCTq6+1K
「これは……」
近寄ってみれば、コルベールはひどい有様だった。所々醜く焼けただれ、服が肉に張り 付いている。ひどいのは右足だった。完全に炭化し、もはや崩れかかっている。 これだけの傷を負ってよくも――アニエスの背筋に戦慄とも憧憬ともいえぬ、不思議な 感情が走った。 痛みは精神の集中を乱す。相手の魔法を崩す際、それをよく多用するアニエスにとって、 この目の前の男はあまりに規格外だった。 だが、驚いてばかりもいられない。アニエスに施せる処置などほとんどない。早く水の メイジを呼んで、治療してもらうしかない。
「意識を失ってるのが幸いしたか」
言って、男の傍らに膝を付く。呼ぶ前に、することがあったのだ。肉と服が完全に溶け 合う前に、それを引き剥がさなくてはならない。本来は清潔な布でもあればいいのだが、 そんなものはどこにもない。陛下からいただいたマントで代用するしかない。不本意だが。
「まったく、なぜ私が炎使いなどのために――」
愚痴りながら、コルベールの身を起こそうと首に手を回し――
VIII/
指揮官がいないのが幸いだった。もはやメイジが残っていないと油断していた敵部隊を 銃士隊と協力して襲撃した。 各々は際立ったメイジであろうと、指揮系統が混乱したままでは対処など間々ならない。 連携だった攻撃を受け、彼らはたやすく瓦解した。無論、生徒たちに被害はない。少なく とも肉体面に限った範囲でしかないが。 だが、それを喜ぶ暇など彼女にはなかった。父が命の危険にさらされているのだ。例え あの偉丈夫に勝利しようと、あの火傷は命にかかわる。いや、そもそもそれ程の傷を負っ て戦いに挑むことすら無謀だったのだ。 オールド・オスマンに後の頼み、教師、生徒を含む数人のメイジと銃士隊の面々を連れ、 幸い、アルヴィースの食堂から中庭までは、それ程遠くはない。 焦りを胸に、全力でその距離を駆け抜け中庭に着いた彼女が見たのは、もはや面影しか 残らぬ焼け焦げた中庭と、倒れた父親、そして、倒れた父の傍らに佇む騎士風の女性だけ だった。彼女を焼こうとしたメイジはどこにもいない。 あるいは父を倒した後にどこかへ行ったのか――そのような益体もない思考が脳裏をよ ぎるが、とにかく、父の生存を確認するのが先だった。生きているなら、一刻も早く治療 しなくてはならない。そのための水のメイジも連れてきてあるし、彼女もさほど得意では ないが多少の治療魔法の心得はある。 いや、そもそも倒れた父を見た瞬間に、そのような判断をすべて投げ捨てて彼女は走り だしていたのだ。 だから、その騎士風の女性に銃を突きつけられたとき、彼女は立ち止まることも、何故 と問うこともせず、ただ走って「邪魔だ」と、その手を払いのけた。 止まれるはずもなかった。彼女はただ、父親を救いたいだけなのだから。 「お父さん、大丈夫!? よかった、まだ息がある。安心して、絶対助けるから!」
連れ立った他の者が困惑する中、彼女はただ癒しのルーンを唱えた。水の秘薬を用意 することなど思いつかない。そんな鬼気迫る様子だった。
「父、だと? そいつが、貴様の?」
その声はどうしようもなく震えていて、それでもアニエスの問いかけに答える余裕は彼 女にはない。背後で銃口を構えなおす気配がしたが、精神を削って治療を続ける。
「貴様は、そいつが昔何をしたのか知っているのか!! そいつは、そいつはな、私の、 ダングルテールの村を焼き捨てたんだぞ、村人ごと全部!!」 393 名前: 名無しさん@ピンキー [sage] 投稿日: 2007/09/24(月) 00:08:59 ID:TCTq6+1K
動揺が全員に伝わるが、構わない。助力が得られないなら、その分は自分で補えばいい。 肌に張り付いた焼け焦げた服をはがしながら、彼女は額に浮かんだ汗をぬぐう。 不得手な水の魔法を、既に数度炎を放った後で使っているのだ。負担は大きい。だが、 あきらめない。
「おい、きいているのか、そいつは――」
ついに、聞く様子を見せない彼女の肩に、アニエスの手がかけられた。無理矢理にでも 治療をやめさせたいのか、強引に自分のほうへと向き寄せようとする。 もはや限界だった。これ以上集中を削がれては、残りわずかな精神力を無駄に浪費して しまう。 そしてそれ以上に――この騎士が彼女は許せなかった。
「うるさいわね、知っているわよ、そんなこと!!」
かけられた手を振り払う乾いた音が中庭に響く。いまだ残る炎のはぜる音にかすれて消 えたが、なぜか強く耳に残る。そんな音だった。 思った以上に力を込めていたらしい。叩いた手を見れば、自分でも驚くほど赤くなって いた。払われた相手もこのような反応をするとは思っていなかったのか、愕然と目を見開 いている。手の甲をさすりながら彼女は言った。
「知ってるわよ、そんなこと。お父さんが昔特殊部隊にいたことも。その命令で、ダング ルテールって村を焼いたことも。 そして――私がその生き残りだってことも。 ……お父さんは、私が知ってることを知らないけどね」
IX/
だから、邪魔しないで――そう寂しげに笑った少女の言葉を、アニエスは理解できなか った。生き残り、ダングルテールの生き残り。それは、自分だけではなかったのか。 混乱のあまり、足元がふらついた。その背を部下が支えたが、それにも気づかず、 アニエスは低く呻く。
「なぜ、なら、なぜ助ける。そいつは敵だ。なら、殺さないと。皆の敵を、討たないと」
それは、自らに言い聞かせるような、呪文じみた言葉だった。ルーンではない。自らの 身をも焦がす呪いの言葉だ。
それを、ダングルテールの生き残りなら、誰もが持つべきではないのか。
すがるような視線で、アニエスは少女を見た。そこにはもう寂しげな笑みはなかった。 ただ真っ直ぐにアニエスを見据えその瞳で父を助けるのだと物語る。 息は荒く、顔中に汗をかいているというのに、どう見たって疲れ果てているようにしか 見えないのに、なぜだかアニエスは彼女を綺麗だと思った。思ってしまった。 そしてそれで終わりだ。もう、彼女に、そしてその父親に銃口を向けられない。 のろのろと懐に銃をしまい、その代わりに傷薬を取り出すと、少女に向かって放り投げ る。受け取った彼女が目を白黒させている間にマントの留め金をはずし、その間抜け面を 覆い隠す。
「傷薬だ。やけどに効くかどうかわからんが、ないよりマシだろう。それとマントもやる。 血を拭うなり、止血するなり好きに使え」
言ってアニエスはその場から離れていった。ついて来ようとした部下に身振りだけで手 助けを命令し、一人中庭を後にする。 たった一人の生き残り。そうではなかったという事実だけを胸に抱いて。 394 名前: 名無しさん@ピンキー [sage] 投稿日: 2007/09/24(月) 00:09:34 ID:TCTq6+1K X/
意識を取り戻した後、コルベールは盛大に娘に怒られた。かばうのはいいが、ちゃんと 自分も怪我しないようにしろ。嬉しかったけど。重傷なのに戦うなんて馬鹿げてる。私を 信用してないのか。一緒に戦えばよかった。心配させないで。一緒に逃げればよかった。 死んじゃうと思った。私の結婚式を見たくないのか。いや、相手はいないけど。 盛大な娘の愚痴は、一時間にも及んだ。オールド・オスマンのとりなしがあれば、その 倍は硬かっただろう。苦笑を浮かべるほかない。 奇跡的としか言いようがないだろう。コルベールは一命を取り留めた。治療に当たった メイジいわく、渡された傷薬の質がよほどよかったらしい。それがなければ、おそらくは 助からなかったろうと言われたほどだ。 当然だろう。魔法が使えぬ銃士隊。魔法で癒せぬ銃士隊。その隊長のアニエスが渡した 薬が悪いはずもない。 ただコルベールが気になるのは、なぜそれほどのものを仇の自分に使わせたのかだ。 聞いたのだ。彼女もまた、ダングルテールの生き残りなのだと。だから問いたかった。 なぜ自分を生かしたのかと。 だが、それを問う前にアニエスは学院を去っており、父の咎を知らぬ娘には尋ねられず、 結局謎は謎のままだ。そしてコルベールには確信にも近い予感がある。 自分がそれを知ることは一生涯ないだろうと。
「ちょっと、お父さん、聞いてるの。言っておくけど私、まだ許したつもりないからね」
それまでの疑問も忘れ、コルベール笑った。ただ、娘と再びこうして喧嘩できること。 その幸運がたまらなく嬉しい。足を一本失ったが、代償としては軽いものだ。 所詮この身は蛇。腕も足も惜しくない。 この年になると、いくら魔法の義足でも体力が間に合わない。恐らく不便を強いられる 普通の義足をつけることになるのだろう。リハビリも辛く険しい。 それでもコルベールは後悔しない。罪を忘れたわけではない。己に幸せが不釣合いなの もわかってる。それでも、ただ娘の無事だけを喜んで、コルベールはもう一度微笑んだ。
――END――