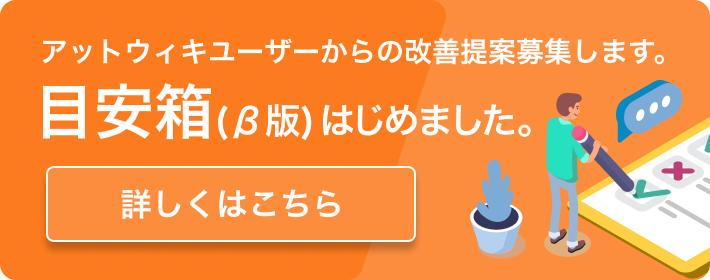王国の辺境にだって村はある。 トリスタニアから南に伸びる街道を、山を越え森を潜り、ずっとずっと海が見えるまで進んだ先に、その村はあった。 その村は一組の夫婦の率いる開拓団が開墾した土地に作られた村で、その名前をダイバ、といった。 海岸沿いの岩壁から取れる石灰岩と、海沿いにある森林から取れる硬い樹を組み合わせた白い家が目に眩しい。 そのダイバの村の入り口近くには、村長夫婦の経営する、宿屋がある。 その宿屋の入り口から、少年が出てきた。 少年は朝日に目を細めると、んー、と伸びをする。 少年の顔かたちは辺境の平民にしては整っており、健康的に灼けた肌に柔らかい鳶色の髪が風にそよいでいる。 少年は一息つくとすぐに海岸に向かって駆け出す。 日課の、朝の荷運びだ。 彼の仕事は朝一番に海岸に向かい、父の採ってきた魚介類を受け取って、宿屋で待っている母に届ける事だった。 五分ほど駆けていくと、すぐに海岸線が見える。 まだ登ったばかりの朝日を背に、何艘かの船が海岸に着いていた。
「父さん!」
少年の澄み切った声が船を牽く男達に届く。 そのうちの一人、ぼさぼさの黒髪に伸び放題の髭を生やしたむさ苦しい男が、手を振って応える。 少年はすぐにそちらに駆け寄る。
「どう?今日は沢山採れた?」
言いながら少年は船の上に設えられた大きな木箱を覗き込む。 その中は、活きのいい魚で溢れかえっていた。
「まあまあかな。大物はないけど、今日は青魚のいいのが取れたぜ」
言って男は木箱に手を突っ込んで、暴れまわる短い丸太のような魚を取り上げる。 それは、少年の大好物だった。 母の作る、この魚を使ったスープが、少年は大好きだった。 思わず顔をほころばせる少年に、父以外の漁師の一人、剥げた頭の初老の男が、大きなびくを手渡す。
「ほれ、今日の取り分もってきな! あと、ママさんによろしくな。今日も呑みにいくからってよ!」 「こらお前ら、人の嫁に手ぇ出すんじゃねえよ」
不器用にウインクする剥げの漁師に、少年の父は釘を刺す。 漁師達はその言葉にがははは、と下品に笑い、バーカ眺めるだけだよ、誰が人のお手つきに手ぇ出すかっての、と陽気に野次を飛ばす。 少年の父は漁師達と一緒に笑い、そして少年に言った。
「じゃ、俺は網直して帰るからさ、シモン先に帰ってな」 「うん、父さん!」
少年、シモンはにっこり笑うと、家路についた。
少年の名はシモン。 家名はない。両親が家名を持たないからだ。 彼が生まれたのは、このダイバの村ではない。トリスタニアのはずれの、小さな宿屋だった。 少年の両親は、少年が物心ついたときには開拓団を率いていた。 十数人の旅団を組み、定住する先を探していたのである。その道中、シモンは生まれた。 そして数年前、開拓団はこのダイバの地に辿り着いた。 ここはもとは、トリステイン王国の貴族、コルベール伯爵領の、未開の地であった。 そこをシモンの両親の開拓団が開拓し、村を作ったのだ。 風光明媚で魚介類も沢山取れ、年間を通して農作物の取れるここは、すぐに大きくなり、移住する人間や観光客のお陰で潤っている。 シモンはこのにぎやかな南の村が大好きだったし、その村長をしている両親をとても誇りに思っていた。 その両親の名は、サイトと、アン。 素性は不明だが、開拓団古参の村人の話によれば、二人は昔貴族だったらしい。 貴族の生活にあこがれないわけではなかったが、今の生活も十分楽しいからこのままでもいいかな、などとシモンは思っていた。
しかしその日、その平穏はあっさりと崩れ去った。
シモンがこの村唯一の宿屋である我が家の異変に気付いたのは、家の前の道に入る曲がり角を曲がってすぐだった。
「あれ?」
家の前に、町の家々の負けないくらい真っ白な、立派な六頭立ての馬車が停まっていた。 一目で、大貴族の乗る馬車だと、幼いシモンにも理解できた。 その馬車の扉が開き、小さな女の子が飛び降りてきた。 栗色の長いウェーブのかかった髪を揺らして、元気に飛び出す。 その勢いで羽織った黒いマントがふわりと浮き、その下の白いシャツと、黒いプリーツのミニスカートが目に入る。
「ママ!ここ、とってもいいところね!」
馬車の中に向けて、甲高い声で少女はそう言って、辺りを見渡す。 すると、その様子を見つめていたシモンと目が合った。 まずい、貴族と会ったらどうするんだっけ。 突然の事態に、シモンの頭の中は混乱してしまう。
「ねえ」
気がつくと、目の前にさっきの少女がいた。
「うわぁっ!?」
シモンは驚いて数歩、後ずさってしまう。 い、いつの間に?
「あなた、この町の子?」 「う、うん、そうだけど」
いきなりの接近に、貴族に対する礼儀とか、母から教わったその辺のことが、頭から一気に飛んでしまうシモン。
「じゃ、この町案内して!私ここ初めてだから!」
言って少女は遠慮なくシモンの手を握って歩き出す。
「え、まってよいきなりそんな!」 「ゴチャゴチャいわない!貴族の言う事は聞きなさい!」
いきなりそんな無法を言って、少女はシモンを引きずって歩き出した。
「うわぁ!なんてきれいな青!」
少女は海に着くなり、感動して声を上げた。 シモンは毎日見ているこの海だったが、たしかに初めて見たときは感動した。この世にこんなキレイな青があるのかと。
「すごいわ!これだけでもここに来た甲斐があるってものよ!」
少女はそう言ってはしゃぎ、くるくると回る。 シモンは早く魚を家に届けたくて気が気ではなかった。 少女に、もう帰っていいかな、と言おうとしたシモンだったが、少女の台詞でその言葉は止められてしまう。
「ありがとう!あなたのお陰でいいものが見れたわ! そういえば聞くの忘れてたけどあなた名前は?」
矢継ぎ早にそう聞いてくる。 シモンは少女の勢いに思わず応えてしまう。
「シモン」 「そう。じゃあ私も名乗らなきゃね。 私の名前はマナ・フランシスカ・ド・ヒラガ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール。 フルネームは長いから、マナでいいわよ」
言ってにっこりと笑う。 やっぱり貴族だったんだ、と思うと同時に、シモンは違和感を覚えた。 このマナという貴族の娘、貴族にしてはあまり平民を見下していないようだ。 平民のシモンに対して、あまり偉ぶった態度を見せない。
「君、本当に貴族なの?」
だからシモンがそう思ってしまった事も無理のないことで。
「…それ言われたの今年に入って五度目。 ママからもよく言われるのよ。もうちょっと貴族らしくなさいって。 でも私、『貴族らしく』って性に合わないのよね。なんかそういう身分の違いって意味ない気がするの」
言ってシモンの顔を覗き込む。
「そういうあなたこそ、平民のくせにえらく整った顔してるじゃないの。 ひょっとして、どっかの貴族の隠し子とか!」
冗談のつもりでそう言ったマナだったが、
「ひょっとすると、そうかもしれないんだ」 「え」
シモンの回答に面食らってしまう。
「あ、でも隠し子ってんじゃないよ。うちの父さんと母さんが、昔貴族だったんじゃないかって。 村の人もそう言ってるし」 「ふうん。没落貴族の落とし子ってわけ。なかなかステキな生い立ちね」
言ってマナはシモンの顔を覗き込むように見つめる。 整った顔を近づけられ、思わずシモンは赤面する。 すると、その整った顔が歪んだ。 整った顔は思い切り歪んで、その後鼻をつまんでシモンから一歩遠ざかる。
「何この匂い!くっさぁ!」 「あ、魚もってるから…って、早く家に届けなきゃ!」
シモンは慌ててびくを抱えなおし、もう一度家路を走る。 その後から、ちょっと離れて、マナがついてきた。
そして、シモンが家に着くと。 食堂を兼ねる一階で、母と見慣れない桃色の髪の女性が、もめていた。
「いい加減意地を張るのは止めて下さい、女王陛下!」 「…今の私は、女王ではありません。あなたこそ、こんな所にいていいのですか? 第二王位継承者でしょう。ルイズ・フランソワーズ」
…その、桃色の髪の貴族の女性は、母の事を、今確かに『女王陛下』と呼んだ。 一体、どういう事なんだ? その後ろから、マナが顔を出す。
「…あれ?ママなんでこんなとこに」
マナはシモンを置いてとことこと肩を震わせる桃色の髪の女性に寄って行く。
「ルイズママどうしたの?そんな怒って」
語りかけられると、その桃色の髪の女性は勢いよく振り向く。 その顔はマナにそっくりで、二人の血の繋がりを感じさせた。 …あれ?この人、どこかで見たような…。 シモンが記憶の糸を手繰ろうとすると。 その女性と目が合った。
「…じゃあ、あの子だけでもつれて帰ります」
その女性は、獲物を見つけた目で、シモンを睨む。 シモンの背筋に悪寒が走る。それは、遺伝子レベルで刷り込まれた反射行動であった。
「ダメです!あの子は、シモンだけは!」
言って母、アンはその桃色の髪の女性とシモンの間に割ってはいる。
「なら、お戻りください。トリステインには、あなたが必要なのです」 「…いえ!いいえ!国に必要なのは王ではありません!国を支える民なのです!」 「それは理屈です。王を戴かない国など、舵のない船も同じ。正当な血筋たるあなたが、王であるべきなのです」
二人はその場で言い合いを始める。 そして、その言葉に、シモンは衝撃を受ける。 自分の母は。女王なのか…? その疑問に、無視されて膨れていたマナが応えた。
「そっかー。あなたのお母さん、アンリエッタ女王だったのね」
大して驚いていないマナの様子に、シモンはさらに驚き、言葉をなくす。
「なんか驚いてるみたいね。私も驚いてるけどね。 でもママに聞かされてたから。この村に、かつて出奔した女王陛下がいるって」
そしてマナは、シモンの知らなかったトイステインの最近の歴史を語ってくれた。 十数年前、トリステインにはアンリエッタ女王という、気高く優しい女王がいた。 ところが、その女王は一人の騎士と恋に落ち、全ての地位をかつての王家の家系に連なる、ラ・ヴァリエールに譲り渡し、出奔したのである。 ラ・ヴァリエールはその血筋と功績で新たな王家となり、今のトリステインを治めているが、アンリエッタ女王の帰還を望む声は未だに止まない。 そこでラ・ヴァリエールは、あくまで一時的な代理として王家を名乗っているだけなのだという。
「そしてついに、女王陛下を見つけたってわけ」
シモンはまだ信じられない。 目の前で桃色の髪の女性と喧々囂々やりあっている母が。 毎朝、昼の仕込みに汗だくになって調理をする母が。 夜は、村の皆にせがまれて優しく歌う母が。 まさか、かつて王国を出奔した女王であるとは。 そんな中。
「ただいまー。なんか軽く食えるもん作ってよ、アン〜」
呑気な声をあげて、父が帰ってきた。
「あ」 「あ」
二人の女性がそっちを向き。 その場の空気が一瞬にして変化する。
「みつけたわよぉぉぉぉぉぉこの破廉恥犬ぅぅぅぅぅぅぅ」 「…ま、まさかその懐かしい呼称は…!ルイズか!」 「に、逃げてくださいサイトさん、シモンを連れて逃げて!」 「逃がすかぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!」
今までの厳かな空気はどこへやら。 ルイズと呼ばれたその女性はまるで肉食獣のように父に飛び掛り、そして母がその女性を父からひっぺがそうとする。 何が起きているのか理解できないシモンに、マナが説明する。
「…そう、んであの人が女王陛下なら、あの人の夫は、私のお父さんでもあるわけ」
え、とシモンの目が点になる。
「ママの話によると、私のお父さんってば、ものすごい種馬だったらしいのね。 あっちこっちに何人か、私の腹違いの兄弟がいるみたい。 確認してるだけでも、あなた含めて7人」
シモンの開いた口がふさがらなくなる。
「この分だと、あなたと女王様連れてトリスタニアに帰るのはほぼ決定ねー。 うちのママ、こうと決めたことはゼッタイ譲らないからねー」
シモンは完全に混乱していた。 だから、目の前のとんでもない状況よりも、今晩母がちゃんと青魚のスープを作ってくれるかどうか、そんなことを考えていた。
そして、この後、シモンたち一家はトリスタニアに半ば強制的に送還され。 王侯貴族を巻き込んで、トリステインの王位争いに巻き込まれていくのだが。 それはまた、別の話。〜fin